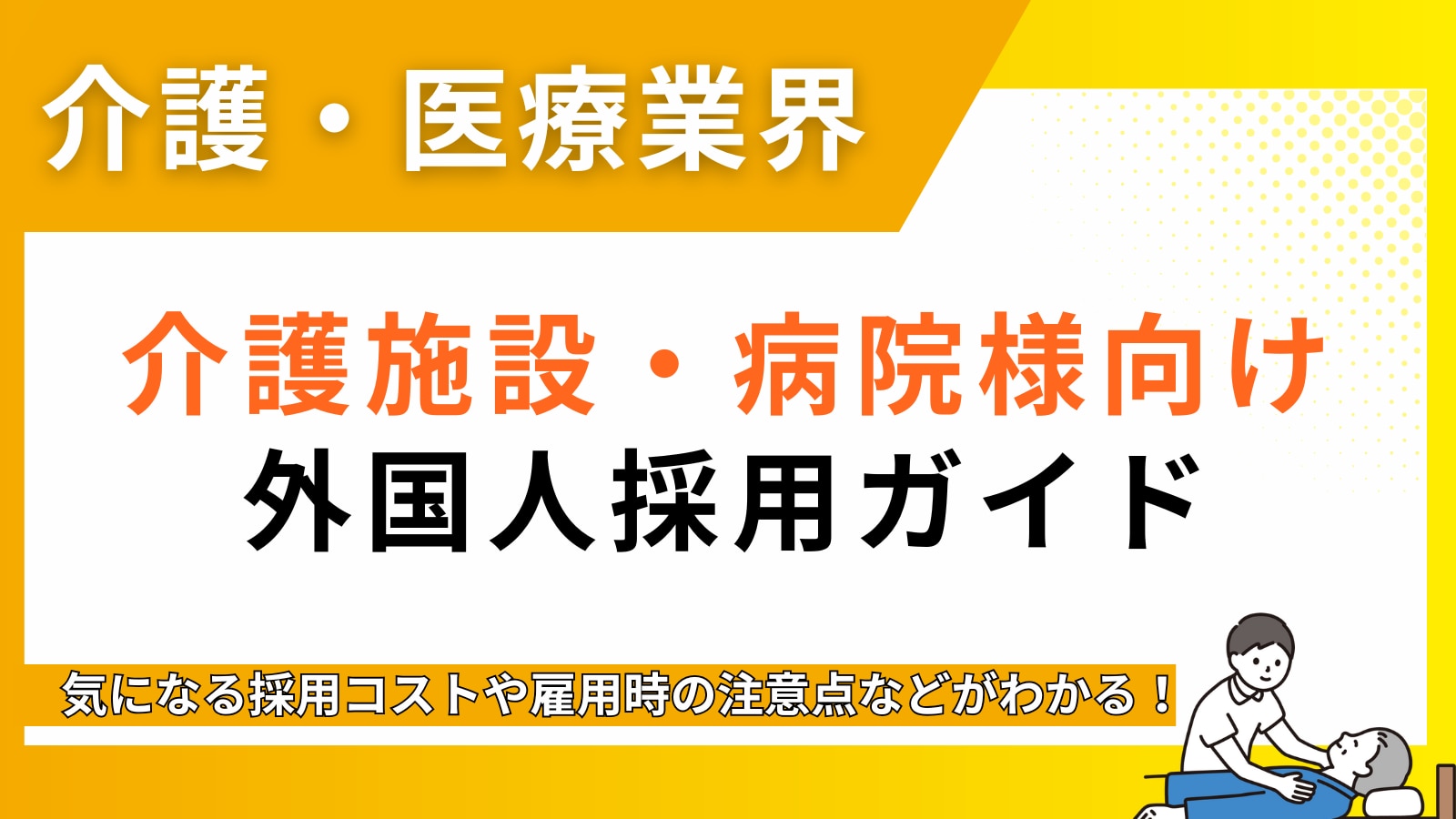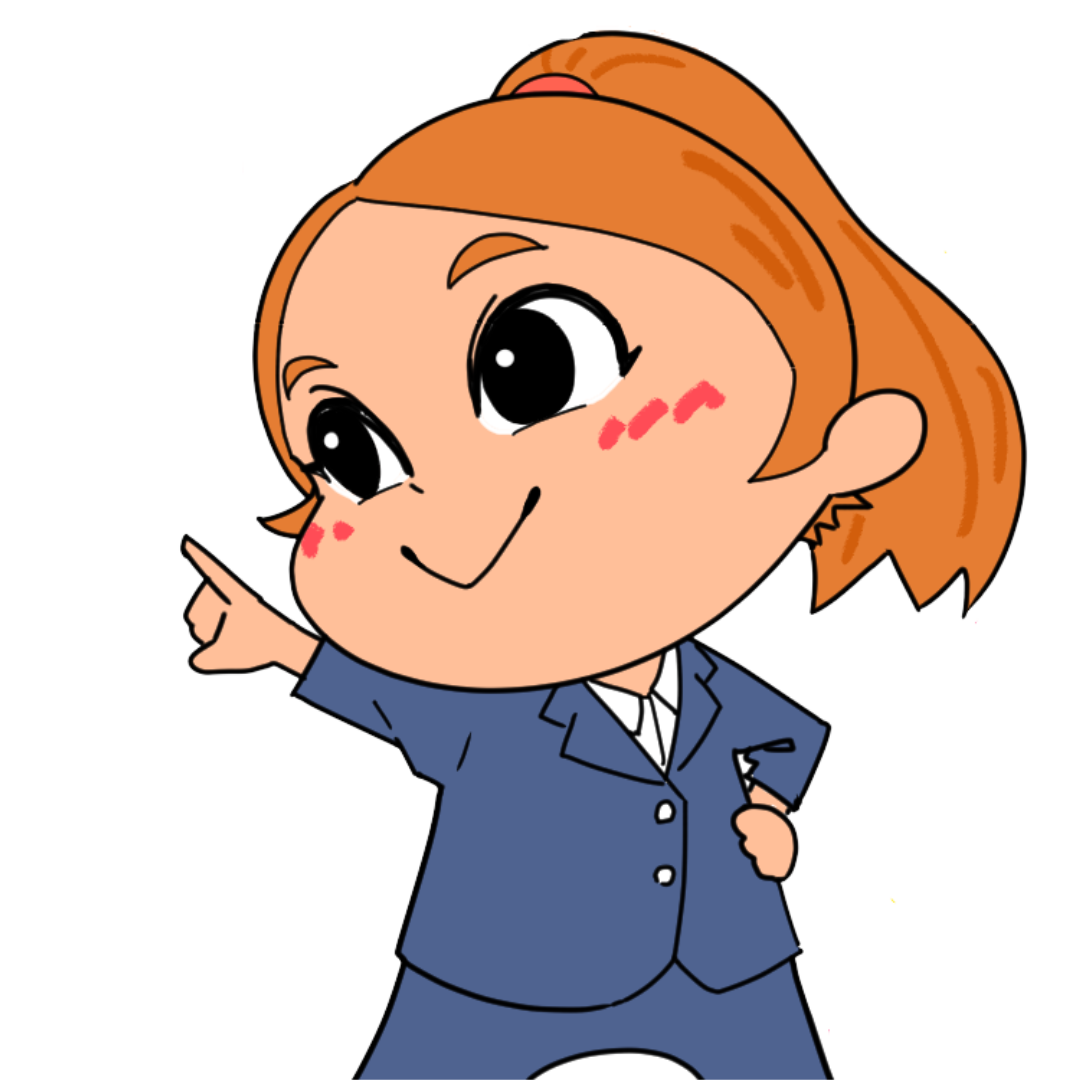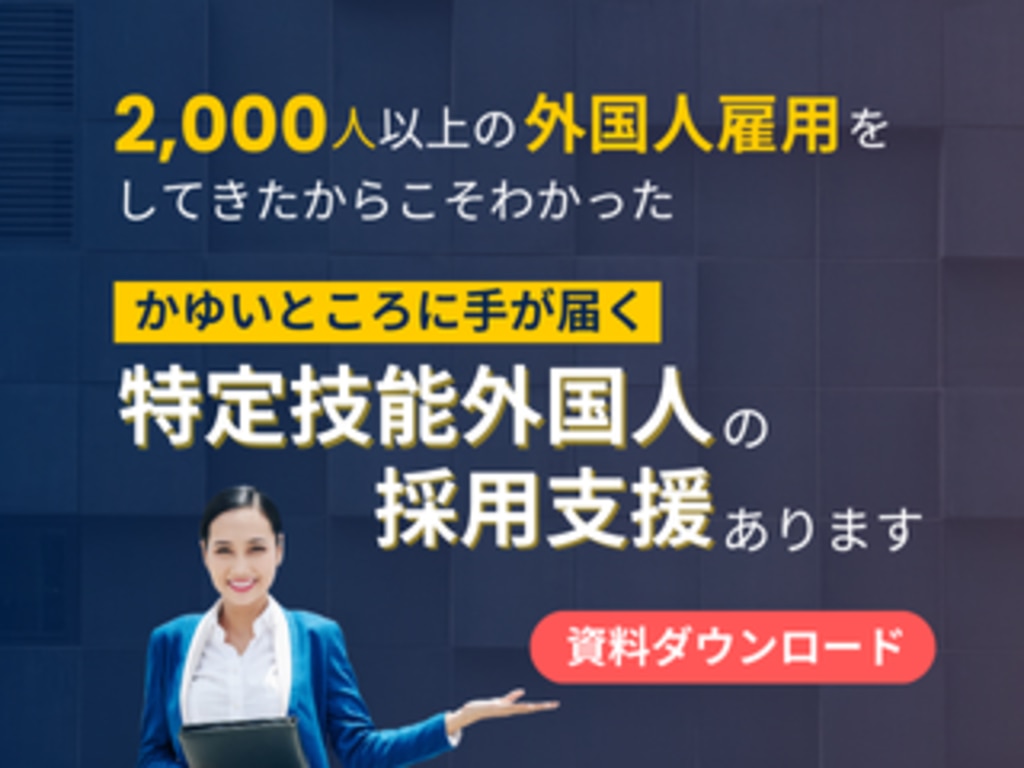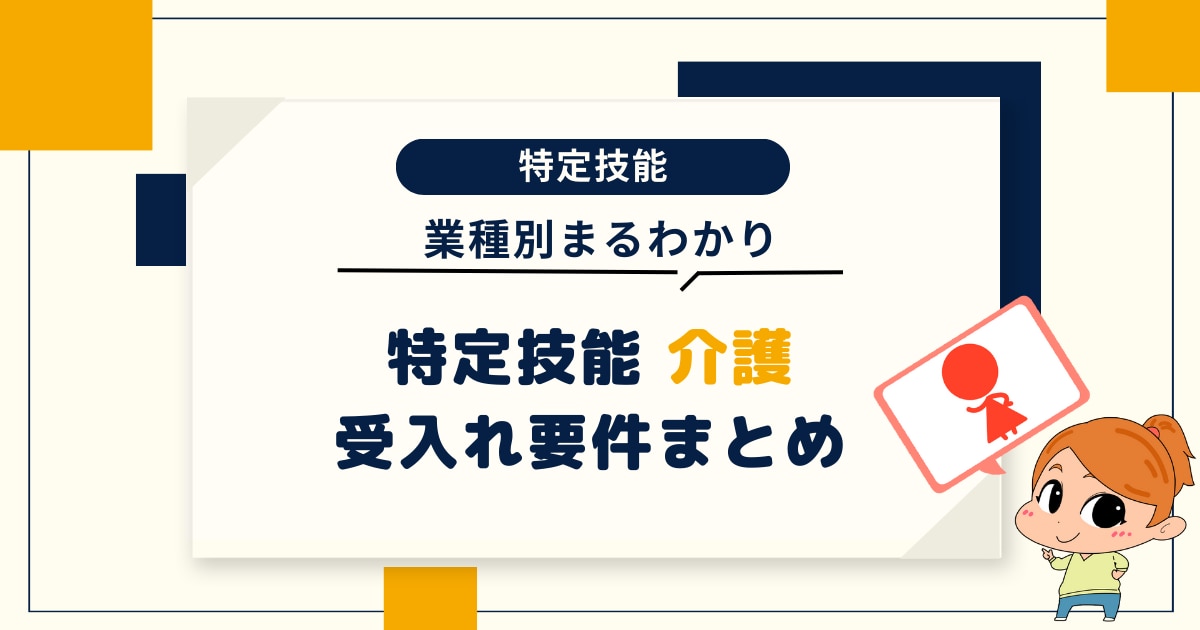
特定技能「介護」とは?要件・業務内容や採用のメリットを紹介
人材不足が深刻な業界で、その問題を解決するために外国人労働者の手を借りる“特定技能”は、介護業界にとって心強い味方となる制度です。
介護・外食業・宿泊・飲食料品製造業・ビルクリーニングをはじめ、全16分野が対象となっています。
本記事では、特定技能のうち「介護」分野にフォーカスし、制度の概要やメリット・デメリットをお伝えします。
人手不足に悩まれている介護事業者様は、ぜひご一読ください。
| 【介護施設&病院向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 日本語・介護知識を習得済みの特定技能人材なら、身体介護やコミュニケーションも安心です。 介護・医療業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |
目次[非表示]
- 1.特定技能「介護」の概要
- 2.【2025年最新】特定技能の訪問介護が可能に!現状や今後の動向について
- 3.特定技能「介護」が制定された経緯
- 4.特定技能「介護」の有資格者を受け入れるために満たすべき要件
- 5.特定技能「介護」の資格取得の要件
- 6.特定技能「介護」の採用の流れ
- 7.特定技能「介護」の有資格者を雇用するメリット
- 8.特定技能「介護」の有資格者を雇用するデメリット
- 9.特定技能以外の介護に関する在留資格
- 9.1. 在留資格「介護」
- 9.2.在留資格「特定活動」
- 9.3.技能実習「介護」
- 10.特定技能「介護」についてよくある質問
- 10.1.特定技能「介護」で雇用した外国人は5年後どうなりますか?
- 10.2.技能実習生と特定技能の介護の違いは何ですか?
- 10.3.特定技能「介護」の外国人を採用する費用の相場は?
- 10.4.特定技能「介護」の外国人の給料はいくらが相場ですか?
- 11.特定技能「介護」の有資格者を受け入れて、現場の人手不足を解消しよう
特定技能「介護」の概要
特定技能とは、一定の条件を満たした外国人労働者が日本国内で働くことのできる在留資格です。
介護を含む16分野が対象となっており、特定技能「介護」を有している外国人労働者は、以下の条件のもと、日本国内の事業所で介護業務に従事することができます。
業務範囲
特定技能「介護」の資格を持つ外国人労働者には、身体介護などの業務と、それに付随する支援業務を任せることができます。
具体的には、以下の業務が挙げられます。
特定技能「介護」の資格所有者に任せられる業務の一例
- 入浴・食事・排泄の介助
- レクリエーションの実施
- 機能訓練の補助
上記以外にも、事業所内でのお知らせポスターなどの掲示や物品の補充など、付随業務と判断されるものであれば特定技能「介護」の業務として任せることが可能です。
雇用形態
特定技能「介護」が該当する“特定技能1号”では、原則的にフルタイム社員としての雇用のみが認められています。
つまり、特定技能「介護」を持つ外国人労働者を、アルバイトや派遣社員として雇用することはできないということです。
また、給与額や労働時間などの労働条件は、日本人の従業員と同等あるいはそれ以上でなくてはなりません。
受入れ人数
特定技能「介護」を有している外国人労働者の受入れ人数は、事業所単位で、日本人等の常勤の職員(雇用保険被保険者)の総数が上限となっています。
なお、「介護」分野で例外的に上限が定められているのであり、特定技能1号の受入れ人数は基本的に上限がありません。
介護のほか、建設など一部業種のみで上限が定められていますのでご注意ください。
受入れ可能な施設
特定技能「介護」を有している外国人労働者は、以下の施設で働くことができます。
特定技能「介護」の受入れ可能施設
- 児童福祉法関係の施設・事業
- 障害者総合支援法関係の施設・事業
- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
- 生活保護法関係の施設
- その他の社会福祉施設等
- 病院又は診療所
ただし、上記に該当するすべての施設で受入れが可能というわけではなく、一部例外条件があります。
たとえば、“障害者総合支援法関係の施設・事業”でも児童デイサービスやケアホームでは特定技能「介護」の外国人労働者を受け入れることはできません。
具体的な対象施設は、厚生労働省の公開している資料をご確認ください。
参照元:厚生労働省「対象施設」
| 【介護施設&病院向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 日本語・介護知識を習得済みの特定技能人材なら、身体介護やコミュニケーションも安心です。 介護・医療業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |
【2025年最新】特定技能の訪問介護が可能に!現状や今後の動向について
特定技能制度の開始から2025年3月まで、特定技能「介護」を有している外国人労働者でも、訪問系サービスは受入れの対象外となっていました。
しかし、2024年6月19日に実施された厚生労働省の『第7回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会』にて、訪問系サービスも対象に加えるという方針が決められました。
そして、2025年4月から、介護職員初任者研修課程を修了し、介護事業所等での実務経験(※)を有する技能実習生および特定技能外国人については、訪問介護をはじめとする訪問系サービスの業務に従事することが認められます。
受入事業者は、事前に利用者と家族へ説明を行うとともに、以下の項目の遵守が必要です。
外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
① 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
② 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
③ 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
④ ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
⑤ 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと引用:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(報告)」
(※)介護事業所等での実務経験が1年以上あることを原則とします。
なお、このような変更がされるようになった背景としては、やはり人材不足の深刻化が挙げられます。
厚生労働省が2024年1月に発表した資料『訪問系サービスなどへの従事について』では、2022年度の訪問介護員の有効求人倍率は15.53倍である旨がわかりました。
対し、同年度の施設介護職員の有効求人倍率は3.79倍です。
両者を比較すると、介護職のなかでもとりわけ訪問介護員の人手不足は深刻な問題となっていることがわかります。
また同資料では、2040年には28万人以上もの訪問介護員が必要になることが見込まれており、その目標を達成するにはおよそ32,000人もの人員を確保しなければならないとされています。
現時点での訪問介護員の人員不足解消はもちろん、将来的に必要な人員を確保するためにも、外国人労働者の手を借りる必要が出てきているということです。
参照元:厚生労働省「第7回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料」、厚生労働省「訪問系サービスなどへの従事について」
特定技能「介護」が制定された経緯
そもそも特定技能制度は、日本の労働力の不足に対応するために2019年に創設された制度です。
近年、日本では人口減少や少子高齢化に伴い、労働人口が減少しており、人手不足が深刻化しています。
その問題を解決するための一つの手段として、外国人の労働力に着目して制定されたのが、この特定技能制度です。
特定技能制度のうちの一つである介護分野も、ほかの分野と同様に人手不足が叫ばれています。
介護需要が高まるのに対し、国内介護人材の確保が難航しているため、特定技能「介護」が制定されたのです。
特定技能「介護」の有資格者を受け入れるために満たすべき要件
事業所の人手不足を解消するため、特定技能「介護」の有資格者である外国人労働者の雇い入れを検討しているご担当者様もいらっしゃることでしょう。
特定技能「介護」の有資格者を受け入れるには、事業者側も一定の要件を満たさなければなりません。
以下2つの要件をご確認ください。
1号特定技能外国人支援計画を立てる
「介護」分野に限らず、1号特定技能外国人を雇用する企業には、雇用する外国人労働者への支援が義務付けられています。
そのため、まずは具体的な支援の計画を立て、“支援計画書”というものを作成する必要があります。
企業が支援すべき具体的な内容は以下をご覧ください。
1号特定技能外国人を雇用する企業が支援する内容
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎
- 住居の確保および生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流の促進
- 転職支援
- 定期的な面談および行政機関への適切な通報
上記を見るとわかるように、受入れ企業に求められる“支援”には、仕事はもちろん、日常生活や社会生活に関することも含まれています。
これらの支援を具体的にどのように実施するのか、また責任者・担当者は誰になるのか……といった細かな内容を決めましょう。
計画内容が決まったら“支援計画書”を作成し、必要書類とともに出入国在留管理庁に提出します。
介護分野における特定技能協議会の構成員になる
特定技能「介護」の制度を活用し外国人労働者を受け入れる企業は、在留資格を申請する前に特定技能協議会に加入しなければなりません。
2024年6月14日以前は、特定技能1号外国人を初めて雇用した日から4か月以内に加入する決まりとなっていましたが、2025年3月現在は事前加入が必須となっています。
なお、既に加入しているのであれば、追加の加入は不要です。
特定技能「介護」の資格取得の要件
外国人労働者自身が特定技能「介護」の資格を取得するルートは、4種類あります。
ともに働く仲間となる外国人労働者は、どのような過程を踏んで雇用となるのか? を把握するためにも、以下の内容を押さえておきましょう。
指定の試験に合格する
介護技能評価試験および、2種類の日本語試験に合格すれば特定技能「介護」の資格を取得することができます。
日本語試験は、介護日本語評価試験が必須となっており、もう1つは日本語能力試験(「N4」以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テストのいずれかを選ぶこととなります。
介護日本語評価試験は、指示文は現地語ですが、問題文は日本語です。
介護業務での声かけや現場で作成する文書など、介護の現場で必要となる日本語の問題が出題されます。
介護福祉士養成施設を修了する
介護福祉専門学校や短期大学など、日本国内にある介護福祉士養成施設の介護福祉士養成課程を修了すれば、特定技能「介護」の資格を取得できます。
これは、介護福祉士養成課程を修了していれば一定の専門性や技術・知識および、業務に必要な日本語能力を有していると見なされるためです。
EPA介護福祉士候補者として4年の在留期間を満了する
EPA介護福祉士候補者として、期間満了まで研修した実績があれば、十分な介護技術と日本語能力が認められるため、在留資格「介護」を取得できます。
そもそも“EPA介護福祉士候補者”とは、EPA(経済連携協定)に基づき、介護福祉士の資格取得を目指して日本国内の介護施設で就労・研修を行っている外国人労働者のことです。
介護福祉士という日本の国家資格の取得を目指して、4年間の研修を受けているため、「一定のスキルが担保されている」と判断することができます。
技能実習生として第2号技能実習を修了する
在留資格「技能実習」の取得者で、第2号技能実習を修了している外国人は、一定の要件を満たせば特定技能「介護」への移行が可能です。
この「技能実習」は、日本でしか得られない技術や知識を学んでもらうことを目的とした在留資格です。
特定技能と異なり、日本国内での労働力の確保を目的としておらず、学んだ技術を本国へ持ち帰ってもらうという、国際協力を目的としています。
そのため、技能実習生は本来、実習期間が終了すると帰国しなければなりませんでした。
しかし特定技能に移行することで、日本で働きつづけることが可能となります。
第2号技能実習を修了しており、なおかつ実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められれば、特定技能に移行することができます。
つまり、介護の第2号技能実習を修了していれば、特定技能「介護」への移行が可能ということです。
| 【介護施設&病院向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 日本語・介護知識を習得済みの特定技能人材なら、身体介護やコミュニケーションも安心です。 介護・医療業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |
特定技能「介護」の採用の流れ
特定技能「介護」の資格を有している外国人労働者を事業所で受け入れる流れは、対象者が日本国内に在留しているのか、それとも海外に在住しているのか、によって異なります。
まずは、日本国内に在留している外国人を特定技能「介護」で受け入れる場合の流れを見てみましょう。
【国内】特定技能「介護」の資格取得者を採用する流れ
- 外国人労働者と雇用契約を結ぶ
- 支援計画を策定する
- 在留資格の変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出する
- 在留資格を特定技能1号に変更する
- 就労開始
雇用契約を結んだら、支援計画に沿って適宜ガイダンスなどの支援を行います。
地方出入国在留管理局から、特定技能1号への在留資格の変更が認められたら、就労を開始することができます。
続けて、海外から来る外国人を受け入れる場合の流れは以下です。
【海外】特定技能「介護」の資格取得者を採用する流れ
- 外国人労働者と雇用契約を結ぶ
- 支援計画を策定する
- 在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に提出する
- 在留資格認定証明書を受領する
- 在外公館でビザを申請する
- ビザを受領し、外国人労働者が入国する
- 就労開始
日本国内の外国人を受け入れる場合と大きく異なるのは、在留資格認定証明書およびビザを申請する点です。
また、受入れ企業の義務である“支援”には出入国時の送迎も含まれるので、入国の際は事業者が所定の場所まで迎えに行く必要があります。
関連記事:特定技能外国人を採用する流れ
特定技能「介護」の有資格者を雇用するメリット
労働力の補充を主目的として制定された特定技能「介護」ですが、この制度を使って外国人労働者を雇用すると、事業者にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
メリット①人手不足の解消につながる
そもそもの特定技能「介護」の目的ではありますが、この制度を活用して外国人労働者を受け入れることで、現場の人手不足を解消に導くことができます。
出入国在留管理庁が公開している『主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数』によると、2024年6月末時点で特定技能「介護」で就労している外国人労働者は36,719人にものぼります。
つまり、国内の介護施設での人手不足が、この制度によって36,719人ぶん助けられているということです。
そして特に注目すべきは、若い労働者が多いという点です。
2020年に公開されたデータでは、介護分野の特定技能外国人のうち、70%以上が18~29歳ということがわかっています。
体力が必要な介護の仕事で、若い労働力を確保できることは大きなメリットとなるでしょう。
参照元:出入国在留管理庁「【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」、厚生労働省「特定技能外国人の受入れに関する介護事業者向けガイドブック」
メリット②1人での夜勤が可能
特定技能「介護」の有資格者は、日勤はもちろん、1人での夜勤も認められています。
なぜなら、この資格があれば日本人の従業員と同様の条件での勤務が可能であるためです。
24時間体制で人手不足を解決に導くことができるので、「日勤の人員は足りているけど、夜勤の人員が足りない……」とお困りの事業者様にとっても心強いでしょう。
メリット③配属後に人員配置基準に加えることができる
介護施設では、入所者の数に対して配置すべきスタッフの基準である“人員配置基準”が定められています。
特定技能「介護」の有資格者は、この人員配置基準に加えることができます。
同じ介護に関する在留資格でも、技能実習の有資格者の場合は配属後6か月が経過しなければ人員配置基準に加えられません。
ですから、この点は特定技能「介護」ならではのメリットといえます。
メリット④新設した事業所でも雇用できる
ほかの在留資格と比較した際の、特定技能「介護」ならではのメリットは、もう一つあります。
特定技能「介護」の有資格者は、新規事業所でも初年度から雇用が可能です。
対し、技能実習やEPAの有資格者は、3年以上の事業実績のある事業所でなければ受け入れることができません。
特定技能「介護」の資格を持つ外国人労働者を採用すれば、初年度から人員配置基準を満たすことができるということです。
特定技能「介護」の有資格者を雇用するデメリット
特定技能「介護」は、介護事業者にとってメリットの大きい制度であることがわかりました。
しかし一方で、避けて通れないデメリットも存在します。
以下で紹介するデメリットも踏まえたうえで、受け入れる体制を整えましょう。
デメリット①育成が難しい
特定技能「介護」に限った話ではありませんが、外国人労働者を雇用する以上は、日本で働くうえで必要なさまざまな知識・技術を教育しなければなりません。
特定技能「介護」を有している外国人労働者は、一定の日本語スキルと介護に関する知識が認められてはいるものの、新しく教える必要のあることは多くあるはずです。
言語の壁はもちろん、文化的な違いに関するサポートや適切な指導も必要になるでしょう。
日本人の労働者を雇用するよりも、この教育コストが一定かかる点は、デメリットといえます。
なお、スタッフ満足であれば、外国人リーダーを派遣したうえでの教育支援が可能です。
同グループの介護施設であるスーパー・コートでは、外国人スタッフを10年以上採用しており、その現場で培ったノウハウをもとに教育支援をいたします。
関連記事:介護現場で働く外国人と円滑にコミュニケーションをとるコツ
デメリット②採用にあたり煩雑な手続きが必要になる
特定技能制度は、「介護」分野に限らず、在留資格の手続きや各種ガイダンスの実施など、煩雑な工程を伴います。
国外在住の外国人を雇用する場合は、ビザの手続きも必要です。
また受入れ後も、在留資格更新手続きや各種支援があるので、“雇用さえできればそれで終わり”ではありません。
「人手不足解消のために外国人労働者を雇用したはずが、手続きに手間がかかってしまって、業務負担が改善されていない……」といった事態も起こり得るということです。
ただし、支援サービスを活用すれば、各種手続きや支援の手間をかけずに、特定技能「介護」の外国人労働者を受け入れることができます。
スタッフ満足では、業界最安級の低価格で、煩雑な業務を一律で請け負っております。
デメリット③技能実習とは異なり転職が可能になる
こちらも介護分野に限定しないデメリットですが、技能実習制度と異なり、特定技能制度には、基本的に転職制限がありません。つまり、各種手続きや支援を行ったうえで外国人労働者を迎え入れたとしても、本人が希望すれば予期せぬタイミングで離職してしまう可能性もあるということです。
特定技能「介護」から特定技能「外食」に、といったように異なる分野への転職は試験を受けなければなりませんが、同じ「介護」分野であれば試験を受ける必要なく転職が可能です。
人手不足を補うために制度を活用して雇用したはずが、転職となると事業者にとっては痛手となるでしょう。
なお、スタッフ満足では採用から入職後の定着支援まで、外国人コーディネーターが一貫して対応いたします。母国語で相談できる仕組みのなかで、外国人労働者本人の不安に寄り添うサポートを提供するため、離職率の低減にお役立ていただくことができます。
また、スタッフ満足を通じて雇用した人材が1年未満で退職した際は、追加の人材を無料でご紹介いたしますので、再度受入れを行う手間の削減が可能です。
| 【介護施設&病院向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 日本語・介護知識を習得済みの特定技能人材なら、身体介護やコミュニケーションも安心です。 介護・医療業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |
特定技能以外の介護に関する在留資格
特定技能「介護」以外でも、外国人労働者が日本の介護業界で働くための在留資格は存在します。
介護に関する在留資格
就労可能期間 | 入国時の日本語能力の目安 | 就労可能なサービス | |
特定技能「介護」 | 最長5年 | 「N4」以上相当 | 訪問系サービスは不可(今後解禁となる予定) |
在留資格「介護」 | 永続的 | 「N2」程度 | 制限なし |
在留資格「特定活動」(EPA介護福祉士候補者) | 介護福祉士の資格を取得できれば永続的 | ベトナム:「N3」相当 | 訪問系サービスは不可(介護福祉士資格取得後は、一定の条件を満たせば可能) |
技能実習「介護」 | 最長5年 | 「N4」程度 | 訪問系サービスは不可 |
以下で、それぞれの資格について詳しく解説いたします。
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、日本国内の介護福祉養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を持っている外国人が取得できる資格です。
介護福祉養成施設に入学する際は、日本語能力試験「N2」相当の能力が求められるので、在留資格「介護」を持っている時点で必然的に一定の日本語スキルも有していることになります。
そして在留資格「介護」の大きな特徴としては、介護職に携わる在留資格のなかで、唯一訪問系サービスにも対応している点が挙げられます。
特定技能「介護」もゆくゆくは訪問系サービスへの対応が示唆されているとはいえ、まだ本格的に対応には至っていません。
ですので、訪問系サービスで外国人労働者を雇用したい事業者様は、現状では在留資格「介護」の有資格者を雇用することとなります。
さらに、特定技能「介護」では働くことのできる期間は最長5年と決められている一方で、在留資格「介護」では永続的な就労が可能です。
特定技能から在留資格「介護」への移行方法について
上記でお伝えしたように、在留資格「介護」は訪問系サービスも対象となっており、さらに就労期間の定めがないという大きな特徴があります。
実は、外国人労働者本人に介護福祉士の資格を取得してもらうことができれば、特定技能「介護」から在留資格「介護」に切り替えて、そのメリットを活かすことができます。
そもそも在留資格「介護」の有資格者は介護福祉士の資格を持っているため、特定技能「介護」から移行するにあたっては同資格の取得が必要になるのです。
なお、介護福祉士の国家試験を受験するには、3年間の実務経験があることと、実務研修を修了していることが要件とされています。
そのため、特定技能「介護」の資格がある状態で3年間実務に携わったのちに介護福祉士の国家試験を受ける必要があるということです。
「この人には長く働いてもらいたいから、在留資格「介護」に移行させたい!」と思う外国人労働者が見つかった場合は、国家試験受験のタイミングを判断したうえでスケジュールを立てるとよいでしょう。
在留資格「特定活動」
在留資格「特定活動」は、ほかの在留資格と異なり、“特定活動”とよばれる活動に該当する個々人の事情に対して在留許可が認められる資格です。
この特定活動にはいくつか種類があり、そのなかでも法務大臣が告示する“告示特定活動”には“EPA介護福祉士候補者”とよばれる項目があります。
そもそもEPAとは、一定の要件を満たす外国人が日本の施設で就労・研修し、その国と日本のあいだでの経済関係の強化を目指す協定のことです。
この仕組みを活用し、EPA介護福祉士候補者として来日した外国人は介護福祉士の資格取得を目指しながら、日本国内の介護施設で就労し、研修を受けることとなります。
EPA介護福祉士候補者に与えられている期間は4年間です。
この4年間のあいだに介護福祉士の資格を取得できなければ、帰国しなければなりません。
資格を取得することができれば、永続的に日本国内で働くことが可能です。
なお、2025年3月現在、日本でEPA介護福祉士候補者の受入れを行っているのはベトナムとインドネシア、フィリピンの3か国のみです。
求められる日本語能力は国によって異なり、ベトナムは日本語能力試験「N3」相当、インドネシアとフィリピンは「N5」相当とされています。
技能実習「介護」
最後に紹介するのは、技能実習「介護」という資格です。
特定技能を含むこれまでにご紹介した資格との大きな違いは、その目的にあります。
特定技能や在留資格「介護」およびEPA介護福祉士候補者は、日本国内での労働力の確保を目的としているのに対し、技能実習制度の目的は海外への技術移転です。
つまり、この制度を活用して日本国内で技術を身につけた外国人が帰国し、自国でその技術を伝えることを目的としているということです。
そのため永住を前提としておらず、日本への在留期間は原則5年までと定められています。
なお日本語のスキルは、来日時点では「N4」相当が、1年後の試験では「N3」相当が求められます。
その後は1年目と3年目にそれぞれ試験があり、求められるレベルが上がっていくという仕組みです。
関連記事:技能実習生とは?制度利用前に確認しておきたい問題や受け入れ方法
特定技能「介護」についてよくある質問
介護の分野は人材が不足していることもあり、特定技能外国人の採用を検討している企業も多いでしょう。
ここでは、採用を検討するにあたり、よくある質問について回答していきます。
特定技能「介護」で雇用した外国人は5年後どうなりますか?
特定技能の在留期間は5年までと定められています。
ですが、5年後はすべての特定技能外国人が辞めてしまうわけではありません。
考えられるパターンは、大きく分けて2つです。
1つ目が在留期間の満了により、帰国するパターンです。
特に母国から出稼ぎを目的として日本で働いている外国人の多くは、帰国を検討することになります。
2つ目のパターンが、在留資格「介護」への移行です。
在留期限を迎えてしまえば引き続き特定技能の資格で働くことはできません。
ですが、介護福祉士の試験に合格できれば在留資格を「介護」に切り替え、引き続き日本で働くことが可能です。
ただ、受験資格を得るためには、3年間介護施設で実務経験を積み、介護職員実務者研修の資格を取得しなくてなりません。
介護職員実務者研修の資格取得には3~6か月以上かかります。
なお受験資格は「実務経験3年・介護職員実務者研修の資格」で得ることができますが、日本語レベル(N2レベル相当)の向上も必要です。
在留資格「介護」への移行を勧めるのであれば、受け入れ企業側や登録支援機関の協力も求められます。
技能実習生と特定技能の介護の違いは何ですか?
在留資格である特定技能との違いがわかりにくいと言われるのが、同じく在留資格の技能実習です。
似たようなものと理解している方もいるのではないでしょうか。
ですが、それぞれ以下のような違いがあります。
【技能実習と特定技能の違い】
特定技能 | 技能実習 | |
制度の目的 | 人手不足が問題となっている産業分野における労働力の確保 | 日本で学んだことを母国に持ち帰り、母国の発展に貢献させる |
在留期間 | 既定のタイミングで更新することで最長5年在留可能。 | 既定のタイミングで試験を受けて合格することで最長5年在留可能。 |
従事可能な業務範 | 身体介護や身の回りの世話などの業務が可能。 | 身体介護や身の回りの世話などの業務が可能。 |
受け入れ可能人数 | 常勤日本人社員の人数まで受け入れ可能。 | 比率による制限があり、常勤社員と技能実習外国人の比率は4:1まで。 |
転職の可否 | 可能 | 原則不可 |
日本語能力 | 日本語試験に合格が必要で日本語能力試験の合格ラインはN4以上 | 入国時の要件はN4程度 |
特定技能と比較すると技能実習の方ができないことが多く、従事可能な人数も限定されることになります。
新規に介護の分野で活躍してくれる外国人を採用していきたいと考えているのであれば、特定技能外国人の採用を検討してみると良いでしょう。
特定技能「介護」の外国人を採用する費用の相場は?
採用にかかる費用相場の目安は以下の通りです。
【特定技能「介護」の採用にかかる費用相場】
費用項目 | 費用相場 |
送り出し機関への手数料 | 20〜60万円 |
人材紹介の手数料 | 30~60万円 |
渡航費用 | 4〜10万円 |
在留資格申請費用 | 10〜20万円 |
住居準備費用 | 初期費用全般(住居の家賃によって異なる) |
事前ガイダンス等の費用 | 1.5〜4万円 |
支援委託費用 | 2〜4万円/月 |
在留資格更新費用 | 4〜10万円 |
上記のうち、すでに日本で暮らしている外国人を採用する場合は、送り出し機関への手数料と渡航費用、住居準備費用はかかりません。
ただ、現在住んでいる所と職場が遠い場合は引っ越しが必要になることもあり、そういった場合は国内在住の外国人であっても住居準備費用が発生することもあります。
関連記事:特定技能外国人受け入れにかかる費用相場とコストダウンのポイント
特定技能「介護」の外国人の給料はいくらが相場ですか?
厚生労働省による令和5年賃金構造基本統計調査を確認してみると、在留資格「特定技能」で働く人の平均賃金は19.8万円でした。[1]
ただし、これは特定技能全体の平均賃金です。
特定技能「介護」で外国人を採用する場合、給料は同様の業務に従事している日本人と同等以上に設定する必要があります。
最低賃金を満たしていれば良いと勘違いしないように注意が必要です。
そのため、相場は業務内容・地域などによって異なります。
現在、日本人が行っている業務を特定技能外国人に任せたいと考えているのであれば、当該業務を行っている日本人従業員に支払っている賃金を参考にすることになるでしょう。
一つの参考にしてみてください。
参考:厚生労働省:令和5年賃金構造基本統計調査[PDF]
関連記事:特定技能の賃金・給与の相場と決め方・賃金に関する注意点
| 【介護施設&病院向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 日本語・介護知識を習得済みの特定技能人材なら、身体介護やコミュニケーションも安心です。 介護・医療業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |
特定技能「介護」の有資格者を受け入れて、現場の人手不足を解消しよう
今回は、特定技能「介護」にフォーカスし、資格の概要や受入れの際に事業者が知っておきたいことをお伝えしました。
特定技能「介護」は、適切に活用すれば現場の人手不足を解消に導くことができます。
いずれは訪問介護も対象となることが決まっているため、今後はより多くの介護事業者の助けとなることでしょう。
なお、スタッフ満足では特定技能外国人の人材紹介や、採用支援を行っております。
採用~雇用後までの一括サポートも行っているため、現場の管理業務の負担軽減も可能です。
特定技能外国人の採用が初めてで、ご不安を感じられている事業者様は、ぜひご相談ください。