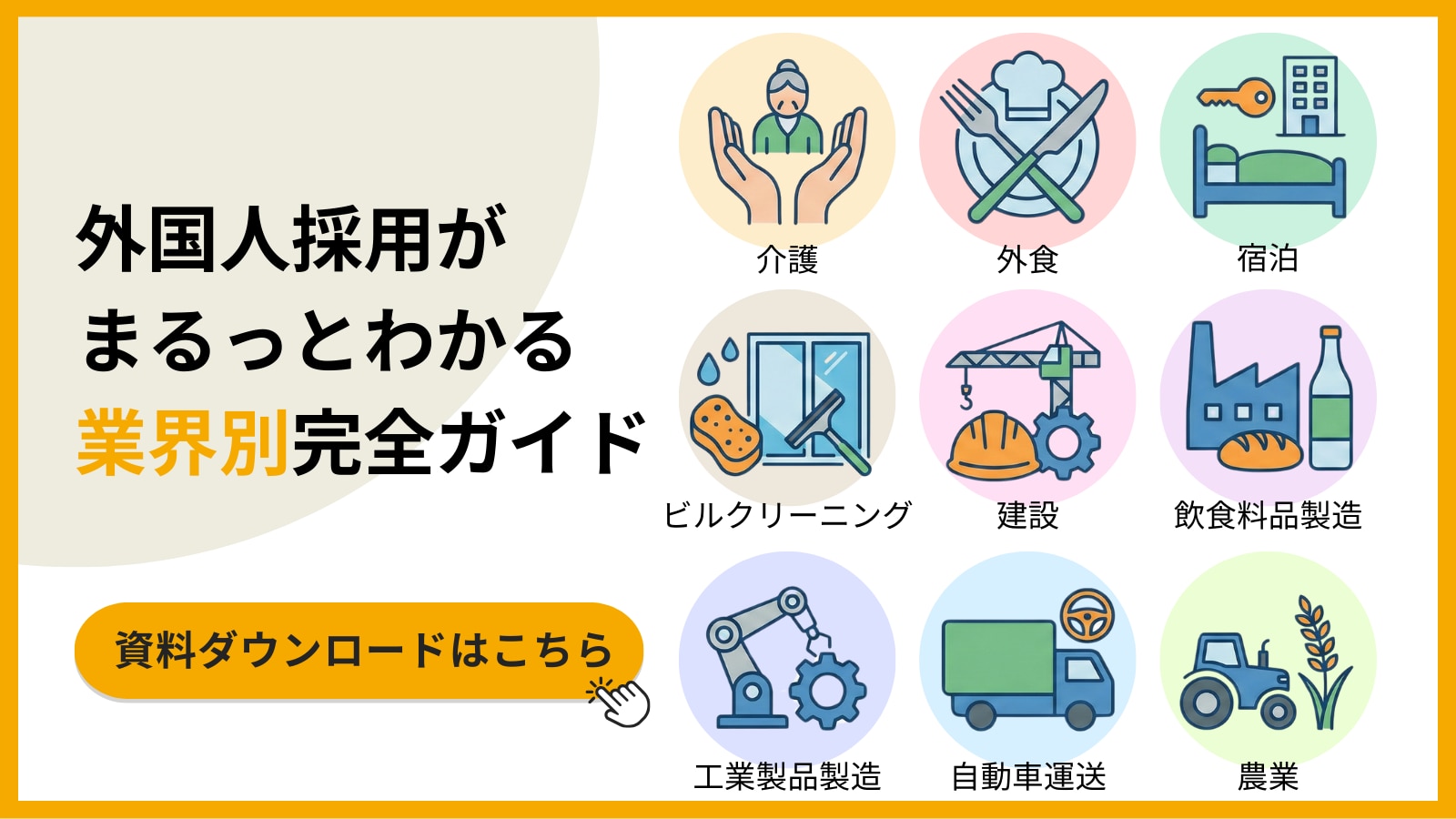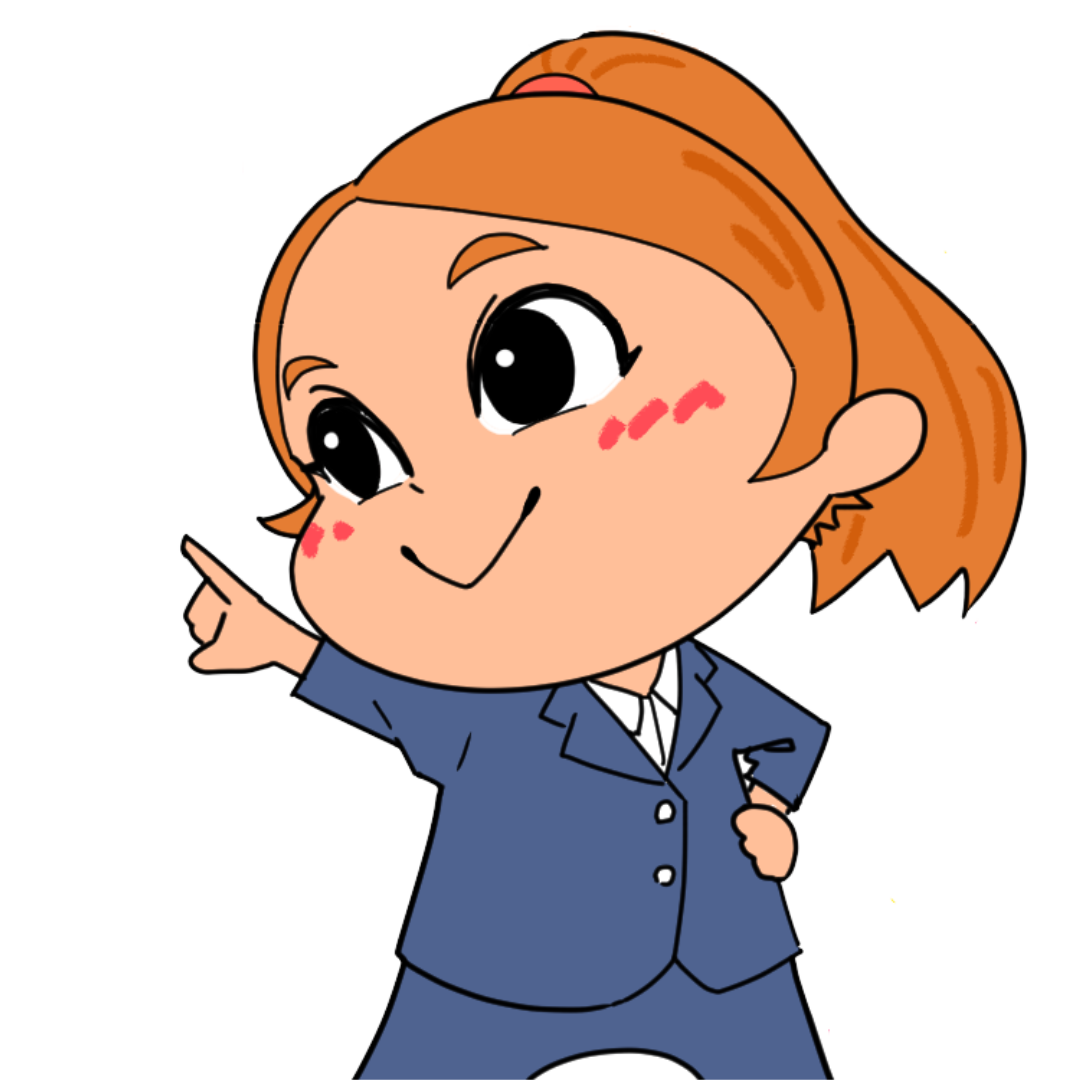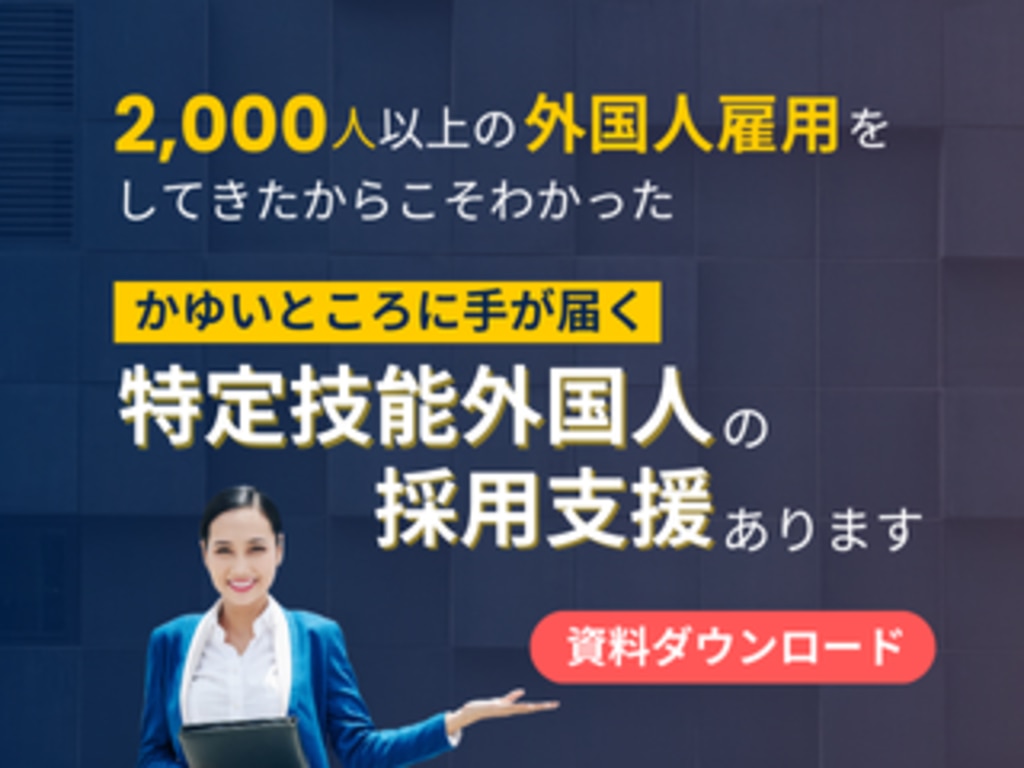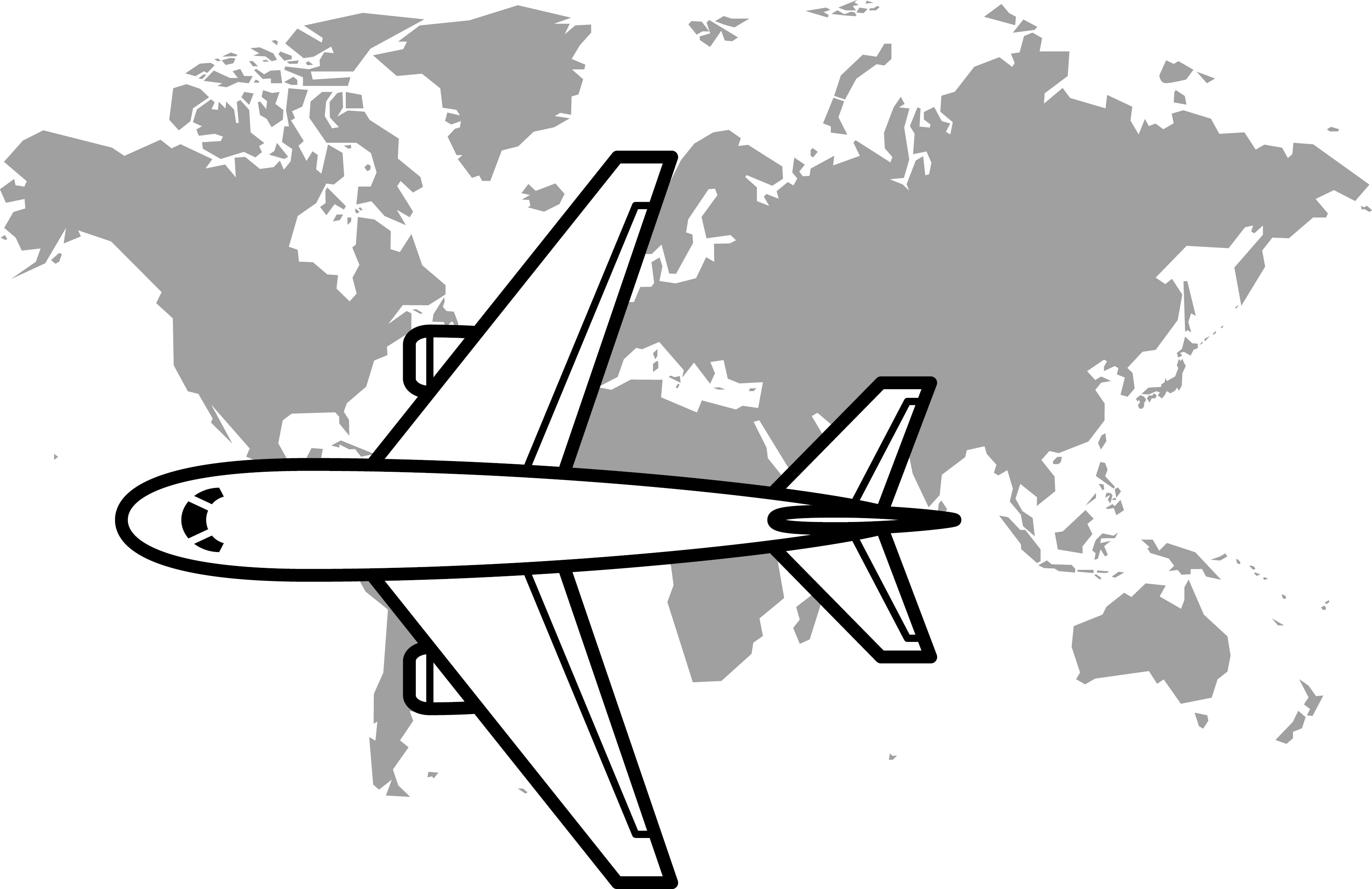
外国人労働者の不法滞在に気づかず雇うのは危険!理由を解説
外国人労働者を採用する際は、適切な手続きと確認が欠かせません。
特に、不法滞在者の雇用による不法就労助長罪には注意が必要です。
不法滞在者だと知らずに企業側が雇用した場合でも、罪に問われます。
近年では人手不足の解消に向け、外国人材の採用を検討する企業が増えています。
しかし、在留資格の確認不足や法的知識の不足により、思わぬトラブルに発展するケースは少なくありません。
採用時の確認が不十分だったために、企業が罰則を科せられるリスクも生じています。
本記事では、不法滞在の定義から不法就労助長罪の内容、企業が取るべき対策を詳しく解説します。
外国人材の採用を検討している企業の担当者は、ぜひ最後までお読みください。
目次[非表示]
不法滞在とは
不法滞在とは、日本に違法な形で滞在することです。
正規の手続きを経ていない入国や、在留期限が切れた後も日本に滞在し続ける状態が該当します。
外国人が日本に入国する際は、パスポートに記載された在留期限内での滞在を遵守しなければいけません。
期限を超えた滞在は法律違反となり、不法滞在者として罰せられます。
企業はこのような事態にならないためにも、応募者が不法滞在者でないか入念に確認する必要があります。
在留カードの確認を怠ると、企業側も責任が問われるため注意が必要です。
採用担当者は不法滞在に関する正しい知識を持ち、適切な確認手順を踏みましょう。
不法滞在の種類
種類 | 定義 | 具体例 |
|---|---|---|
不法入国 | 正規の手続きを経ずに日本へ入国すること | 偽造パスポートの使用、密入国など |
不法在留 | 在留期限を超過して日本に滞在すること | 期限切れの在留カード使用、更新手続き未実施など |
不法滞在の種類は、不法入国と不法在留の2つです。
それぞれの違いを理解すれば、企業が外国人材を雇用する際のリスクを減らせます。
不法入国と不法在留の特徴を詳しく解説します。
不法入国
不法入国とは、正規の手続きを経ずに日本へ入国する行為です。
有効なパスポートを所持せずに入国したり、他人名義や偽造パスポートを使用したりするケースが該当します。
また、上陸許可を受けずに日本に上陸した場合も不法入国です。
上陸許可の証印や記録などを避けるため、貨物に紛れるなど何らかの方法で審査窓口をすり抜けての不正入国も珍しくありません。
不法入国は入管法違反として厳しく取り締まられており、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金が科せられます。
該当する外国人を雇用した場合、企業側も不法就労助長罪の対象です。
外国人材を採用する時は、本人確認を慎重に進めましょう。
不法在留
不法在留とは、在留資格の有効期限が切れているにもかかわらず、日本に滞在し続ける行為です。
在留期限を超過した状態でのオーバーステイは典型といえます。
また、観光目的で入国した後にそのまま日本で就労し、滞在を続けるケースも対象です。
不法在留は職務質問や雇用主による調査などで発覚しない限り、見つからない可能性が高いです。
近年では規制が強化されているものの、毎年数千人以上が発見されています。
不法入国や不法上陸は、明らかに違法とわかった上で行われる場合がほとんどです。
しかし、在留資格の更新・変更漏れによる不法在留は、外国人自身が内容を理解していなかったために罪に問われる場合もあります。
このような事態を防ぐためには、企業側が外国人の雇用確認と管理を徹底しなければいけません。
不法滞在の外国人を雇うと罪に問われる?
企業が不法滞在の外国人を雇用すると、不法就労助長罪に問われます。
不法就労助長罪は入管法73条の2に規定され、外国人を不法就労させたり、不法就労をあっせんしたりした者に対する処罰を定めた制度です。
企業側が注意すべきなのは、故意でなくても処罰の対象になる点です。
例えば、在留カードの確認が不十分だった場合でも、過失があったとして罰則が科せられます。
2025年6月からは、罰則が厳罰化されます。
これまでは3年以下の懲役または300万円以下の罰金でしたが、5年以下の懲役または500万円以下の罰金へと引き上げられます。
状況によっては両方が科せられる可能性もあるため、企業にとっては重い処罰です。
そのため、外国人材を雇用する際は、慎重な確認と適切な手続きが欠かせません。
関連記事:不法就労助長罪とは?該当する3つのケースと企業が気をつけるポイント
不法就労とは
不法就労とは、日本で就労する資格を持っていない外国人が働く行為です。
不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりする、収入を伴う活動が該当します。
また、正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに与えられた資格以外の就労活動をすると不法就労です。
例えば、在留資格が留学に該当する場合、資格外活動許可を取得しても週28時間以内の就労しか認められていません。
制限を超えて働くと不法就労にあたります。
外国人材を雇用する企業側は、こうした制限を正しく理解しなければいけません。
適切な雇用管理ができるよう、正しい知識を身につけましょう。
不法就労助長罪による企業への罰則
不法就労助長罪に問われた企業には、厳しい罰則が科せられます。
現行法では3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
さらに、2025年6月からは罰則が強化され、5年以下の懲役または500万円以下の罰金へと引き上げられる見込みです。
不法就労助長罪による企業への罰則は、故意に不法就労者を雇用した場合だけでなく、確認不足などの過失があった場合にも適用されます。
例えば、在留カードをよく確認しなかった、不安点があったにもかかわらず専門家に相談しなかった場合なども、過失と見なされる可能性が高いです。
一方で、確認を徹底したにもかかわらず、偽造在留カードを見抜けなかった場合は、過失の有無について認識が変わることがあります。
不法就労助長罪となる可能性が高いパターン
企業が不法就労助長罪に問われるパターンは、3つに分類されます。
|
いずれのケースも、企業側に故意がなくても罰則の対象になる可能性が高いです。
企業側の確認不足や認識不足による過失でも、罪に問われます。
不法就労助長罪を防ぐには、これらのパターンを十分に理解し、採用時の確認を徹底しましょう。
パターン① 不法滞在の外国人を雇う
不法滞在の外国人を雇用するパターンでは、不法入国者や被退去強制者を採用する場合が該当します。
これらの外国人は、日本での就労が認められていない人たちです。
在留期限が切れているにもかかわらず、日本に不法滞在している外国人を雇用すると、不法就労助長罪の対象になります。
例えば、在留カードの更新手続きをせずに就労を継続させた場合や、偽造在留カードを使用して不正に就労させた場合です。
採用時の確認が不十分だったために、不法滞在者を雇用してしまうケースが珍しくありません。
そのため、企業は採用時に必ず在留カードの現物を確認し、在留期限や就労制限の有無を入念にチェックする必要があります。
パターン② 就労不可の外国人を雇う
無許可の就労をしている外国人を雇用すると、不法就労助長罪の対象になります。
例えば、就労できない在留資格で働かせたり、観光目的で入国した外国人に仕事をさせたりするケースです。
具体的には、留学や家族滞在などの在留資格を持つ外国人が、資格外活動許可を得ずに働く場合が該当します。
また、短期滞在ビザで入国した外国人の雇用も対象です。
企業側は応募者の在留資格を確認し、資格で認められている活動範囲を把握する責任があります。
仮に外国人本人が就労可能と主張したとしても、企業側で在留カードを確認し、必要な許可を得ているかどうかを慎重に確認しなければいけません。
パターン③ 在留資格の制限を超えて働かせる
就労可能な在留資格を持つ外国人でも、認められた活動範囲を超えた就労は不法就労助長罪に該当します。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人を、工場での単純作業に従事させるケースです。
在留資格では専門的な業務こそ認められていますが、製造ラインでの作業など単純労働は認められていません。
また、留学の在留資格で資格外活動許可を得ている場合、週28時間以内という就労時間の制限があります。
制限を超えて働かせた場合も、不法就労に該当します。
さらに、特定技能の在留資格であれば、定められた業種以外での就労は認められません。
企業は採用時に在留資格で認められている活動内容を確認し、法令に沿った雇用をする必要があります。
不法滞在の外国人を雇用しないための対策
企業は不法就労助長罪を防ぐために、外国人材を採用する時に入念な確認作業を実施しなければいけません。
特に、在留カードの確認とカード偽装への注意は徹底する必要があります。
不法滞在の外国人を雇用しないためにも、2つの対策を把握しましょう。
対策① 在留カードを確認する
在留カードの確認は、不法就労を防ぐための基本といえる対策です。
確認をおこなう際は在留カードの現物を用い、コピーでの確認を避けましょう。
具体的な確認ポイントは、以下の通りです。
|
在留カードには、外国人の身分事項や在留期限、就労制限の有無などが記載されています。
これらの情報を入念に確認し、不法滞在に該当しないか判断しましょう。
対策② 在留カードの偽装に気をつける
近年では、精巧な偽造在留カードが増加しています。
偽造カードに騙されないためにも、見分け方を把握しなければいけません。
在留カードには、偽造防止のための特殊な加工が施されています。
以下を参考にすると、真贋を確認できます。
|
また、出入国在留管理庁が提供する在留カード等番号失効情報照会システムを活用すれば、在留カード番号の有効性を確認できます。
不安がある場合は、出入国在留管理庁や行政書士に相談しましょう。
まとめ
不法就労助長罪を防ぐためには、在留資格の正しい知識を持ち、在留カードを慎重に確認する必要があります。
外国人材の採用を検討している企業は、4つのポイントに注意しましょう。
|
不法就労に関する問題を未然に防ぐためには、専門家のサポートが最適です。
万全の体制を築き、採用・雇用管理を徹底しましょう。