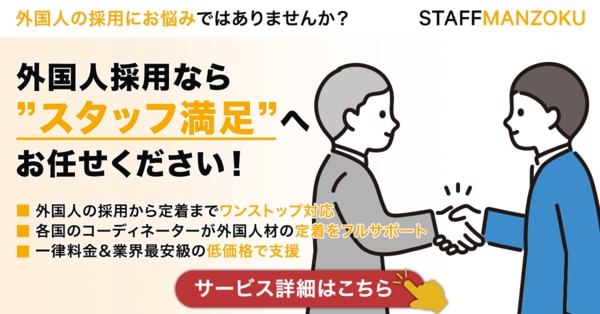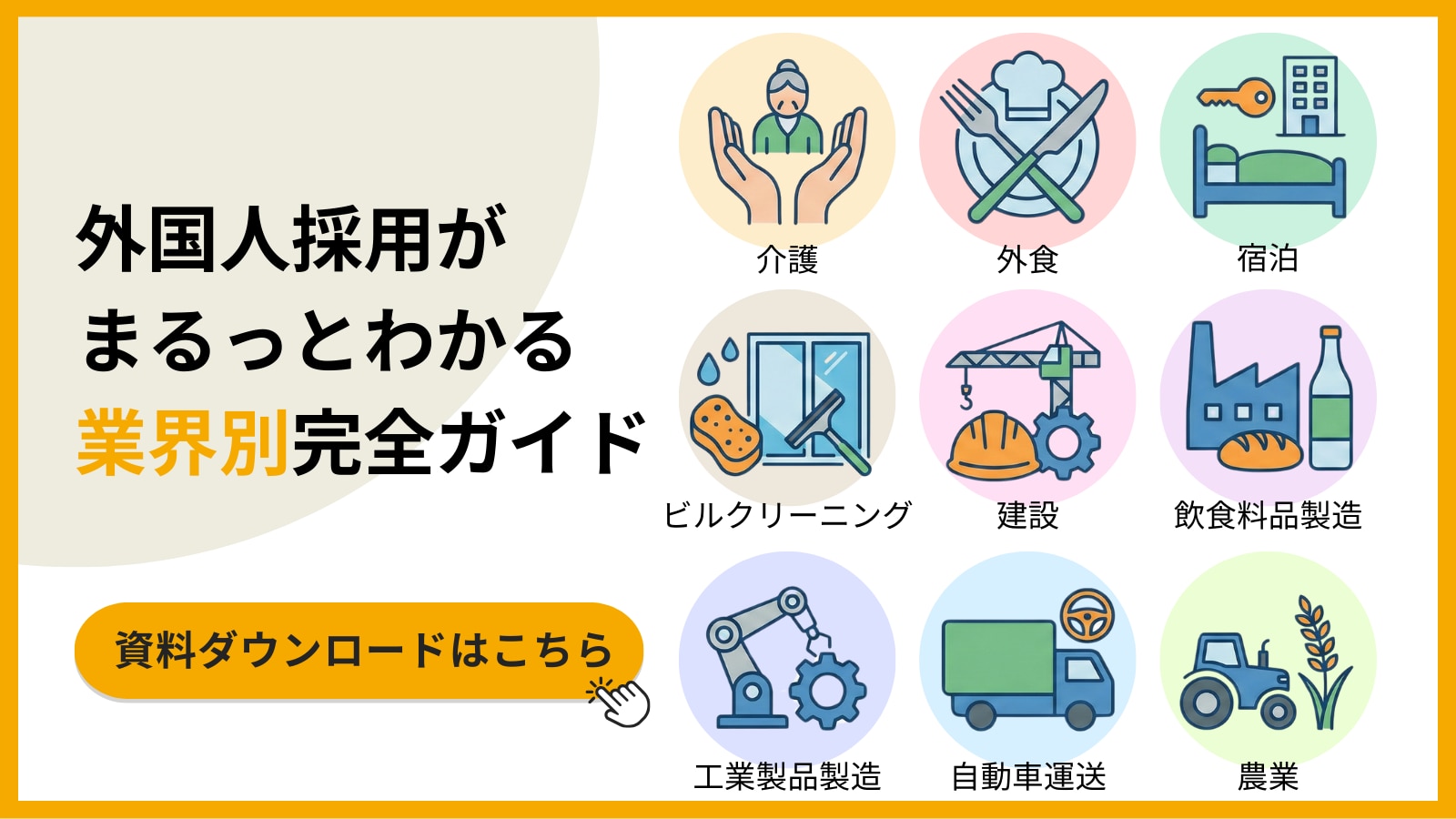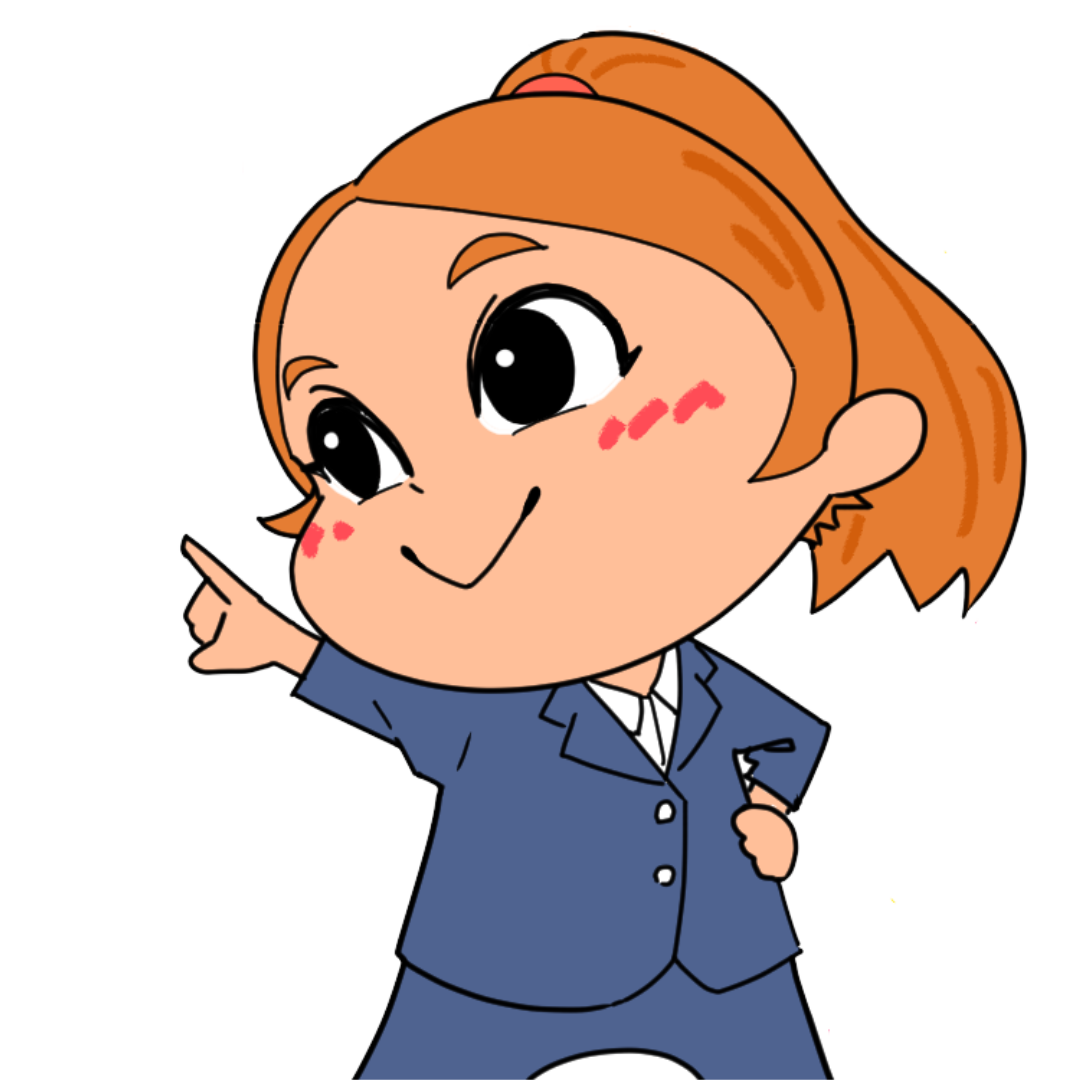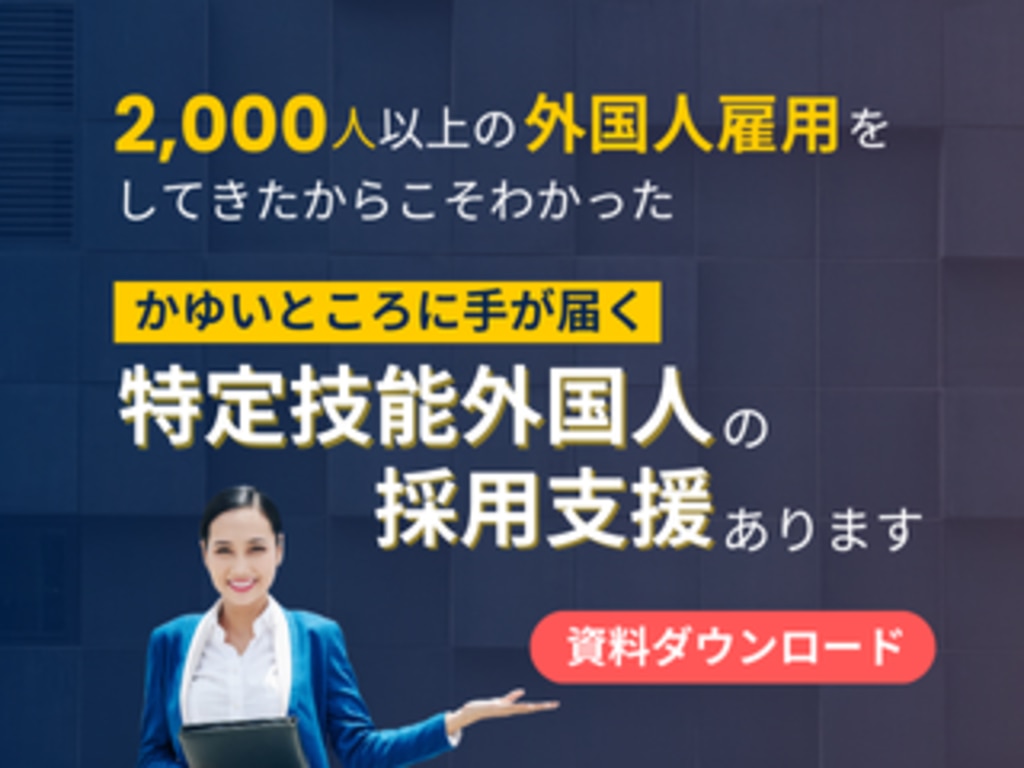高度人材にあたる外国人とは?条件とポイント制の概要を解説
高度人材は、日本の産業にイノベーションをもたらす専門知識や技術を持つ外国人材を指します。
少子高齢化による人手不足に直面している日本では、優秀な外国人材の受け入れを推進しているのが実情です。
しかし、高度人材の採用を検討する企業からは、どのような人材が高度人材に該当するのか、具体的な受け入れ要件は何かといった声が多く寄せられています。
本記事では、高度人材の定義やポイント制による優遇措置、採用時の注意点を詳しく解説します。
高度人材の受け入れは、企業の成長戦略に欠かせない選択肢です。
申請手続きの流れを理解し、自社に合った採用計画を立てましょう。
目次[非表示]
高度人材とは
高度人材とは、日本の産業の発展やイノベーションに貢献できる専門知識と技術を有する外国人材を指します。
該当する人材は、主に以下の3タイプです。
|
日本政府は、2012年5月から高度人材ポイント制を導入しました。
学歴や職歴、年収などの項目でポイントを付与し、合計が70点以上に達した外国人材を高度人材と認定しています。
認定された高度人材には、在留期間の延長や永住許可要件の緩和など、さまざまな優遇措置が与えられるのが特徴です。
また、彼らの受け入れは日本の労働市場の発展を促進し、経済の活性化にも寄与すると期待されています。
人材の国際的な獲得競争が激化するなか、日本は高度人材の受け入れを積極的に推進し、2020年末までに1万人、2022年末までに2万人の受け入れを目標として掲げています。
高度人材ポイント制の目的と概要
高度人材ポイント制は、優秀な外国人材の日本への定着を促進するための評価制度です。
外国人材の活動を3つに分類し、それぞれの特性に応じて評価をおこないます。
|
評価項目は学歴や職歴、年収などで構成され、それぞれに設定された基準に沿ってポイントが付与されます。
例えば、博士号取得者には30点(高度経営・管理分野の場合は20点)、年収1,000万円以上の場合は40点といった形です。
また、日本の大学を卒業している、高い日本語能力を有するなど、特別加算となるボーナスポイントも設けられています。
この制度により、日本が求める高度な能力を持つ外国人材を客観的な基準で評価し、戦略的な受け入れを実現しています。
さらに、ポイントが80点以上の場合は、永住許可申請に必要な在留期間が大幅に短縮されるなど、手厚い優遇措置が用意されている点も魅力です。
在留資格の「高度専門職」の分類
在留資格の高度専門職は、3つの区分で構成されています。
|
高度学術研究活動は大学教授や研究者など、研究活動や教育に携わる人材が対象です。
高度専門・技術活動は自然科学や人文科学の分野における専門知識や技術を活かした業務に従事する人材を指します。
高度経営・管理活動は企業経営や事業管理に従事する人材が対象です。
高度人材ポイントによる優遇措置の内容
高度人材ポイントによる優遇措置の内容は、高度専門職1号と2号で異なります。
それぞれの優遇措置の内容を詳しく解説します。
高度専門職1号
高度専門職1号の在留資格を取得すると、複数の優遇措置を受けられます。
通常の在留資格では1つの活動しか認められませんが、1号では複数の資格にまたがる活動が許可されるのが特徴です。
例えば、大学での研究活動と並行して関連事業も経営できるなどです。
また、在留期間は最長の5年が一律で付与されるほか、永住許可要件も緩和されます(高度人材として3年以上活動していれば申請が可能)。
ポイントが80点以上の場合は、1年間の在留で永住許可申請ができるのも特徴です。
さらには配偶者の就労も認められ、学歴や職歴などの要件を満たさなくても、教育や技術・人文知識・国際業務の活動を行えます。
加えて、一定の条件下では親や家事使用人の帯同も許可され、入国・在留手続きも優先的に処理されます。
高度専門職2号
高度専門職2号の在留資格は、広範な活動と安定した在留を可能にする制度です。
対象になるのは高度専門職1号で3年以上活動を行った人材で、1号で認められていた活動に加え、ほぼすべての就労資格における活動を行えます。
例えば、研究者として活動しながら、経営者として事業展開も可能です。
また、在留期間は無期限となるため、更新手続きを定期的に行う必要がありません。
配偶者の就労や親の帯同、家事使用人の帯同などの優遇措置も引き続き受けられます。
高度人材はこれらの優遇措置により、日本で長期的な活動を計画できます。
したがって、高度専門職2号の取得は、日本での安定的な生活基盤を築くうえで重要なステップといえるでしょう。
自分だけでなく家族を含めた生活環境の整備が容易になるほか、充実した活動を行える環境が整います。
高度人材を雇用するメリット
高度人材を雇用するメリットは、3つあります。
|
それぞれを把握すれば、高度人材への期待が膨らみ、具体的なビジョンが見えてくるでしょう。
メリット① ビジネスの拡大
海外市場への進出には言語力だけでなく、異文化への理解や国際的なビジネス感覚が欠かせません。
しかし、母国の商習慣や市場特性を熟知した高度人材を採用すれば、海外展開における戦略立案や現地とのコミュニケーションを有利に進められます。
例えば、製造業での海外取引では、専門知識と語学力を活かした商談ができるでしょう。
また、現地の規制や法制度への対応もスムーズになるため、リスクの軽減にもつながります。
JETROの調査によると、大企業が高度人材を採用したことで5つの効果があったと報告されています。
|
高度人材の採用は、企業の国際競争力を高める手段として注目されています。
メリット② 人手不足の解消
2023年に日本商工会議所がおこなった調査では、約70%の中小企業が人手不足を実感していると回答しています。
特に、IT技術者やエンジニアなど、専門スキルを持つ人材の確保が困難な状況です。
しかし、専門知識と技術力を有する高度人材を採用すれば、企業の中核を担う人材として期待できます。
例えば、AIやデータサイエンスなどの先端技術分野では、海外の大学や研究機関で高度な専門教育を受けた人材が活躍してくれるでしょう。
また、建築や医療などの高度な資格や経験が必要な分野でも、母国で培った専門性を活かした貢献が期待できます。
高度人材を雇用すると、質の高い人材を確保できると共に、企業の技術力や競争力を向上させられます。
メリット③ スキルや発想力の向上
異なる文化や教育環境で育った彼らは、日本人社員とは異なる視点や発想を持っているため、イノベーションを促進してくれるでしょう。
具体的には、研究開発における新しいアプローチの提案や、商品企画での斬新なアイデアの創出です。
実際に、精密部品メーカーの高砂電気工業では、インド人を中心とした高度人材の採用により、社内のコミュニケーションが活性化し、機械設計のディスカッションが多角的になったと報告されています。
また彼らとの協働は、日本人社員の語学力や異文化理解力が向上するため、組織全体の国際競争力強化にもつながるでしょう。
高度人材がもたらす多様な視点は、企業の成長に欠かせない推進力といえます。
ポイントの計算方法と特別加算条件
高度人材ポイント制では、活動類型ごとに定められた基準に従って点数が計算されます。
活動類型 | ポイントの加算条件 |
|---|---|
学歴 | 博士号取得で30点、修士号取得で20点が付与される |
職歴 | 実務経験の年数に応じて5点から25点が加算される |
年収 | 年齢によってポイントの配分が異なり、29歳以下で年収1,000万円の場合は40点、900万円なら35点が加算される(段階的に付与) |
研究実績 | 特許の取得や論文の発表数などが評価対象 |
これらの基本項目に加え、特別加算の条件も設けられています。
日本の大学を卒業している場合や、日本語能力試験N1を保持している場合は追加でポイントが付与される仕組みです。
また、地方での就労や成長分野での活動にも加算があります。
高度人材ポイント制のメリットは、合計が70点以上になると高度人材として認定、80点以上になると永住許可申請の要件が緩和されるなど、手厚い優遇措置を受けられる点です。
高度専門職の在留資格を申請する流れ
高度専門職の在留資格申請には、3つのケースがあります。
|
必要な手続きはそれぞれの立場で異なるため、事前に把握しておきましょう。
これから日本へ来る人の場合
これから日本へ入国する人は、5つの申請手続きが必要です。
|
まずは地方出入国在留管理局で、在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請書やポイント計算表、それらを立証する資料を提出しましょう。
入管での審査では、高度人材としての要件を満たしているかが判断されます。
許可が下りると、在留認定証明書が発行される流れです。
その後は申請者が自国の日本大使館で査証申請をおこない、パスポートに入国許可の証印が貼付されます。
最後に、日本の空港や港での上陸審査を経て、在留カードが交付されます。
すでに日本にいる人の場合
すでに日本に在留している人が高度専門職への在留資格変更を希望する場合は、3つの申請手続きが必要です。
|
現在の在留資格から高度専門職へ切り替える場合は、地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行います。
申請の際には、ポイント計算表とそれを証明する資料の提出が必要です。
入管での審査では、主に3つの項目がチェックされます。
|
審査に合格すると在留資格変更許可が下り、新しい在留カードが交付されます。
不許可となった場合でも、現在の在留資格の期限内であれば、更新手続きを行えます。
高度専門職の在留期間を更新する場合
高度専門職1号の在留期間を更新する場合は、3つの申請手続きが必要です。
|
まずは地方出入国在留管理局で、在留期間更新許可申請を行います。
申請時には、現時点での状況に基づいてポイントを計算し直し、それを証明する資料の提出が必要です。
審査ではポイントが70点以上を維持しているか、高度人材としての活動が適切に行われているかが確認されます。
審査に合格すると在留期間が更新され、新しい在留カードが発行されます。
高度専門職2号は在留期間が無期限のため、更新手続きは不要です。
高度専門職を雇用する際の注意点
高度専門職を雇用する際に注意したいのは、単純労働が命じられない点です。
さらに、在留カードの確認を怠らないことも重要といえます。
高度人材の雇用に失敗しないためにも、それぞれのポイントを把握しておきましょう。
注意点① 単純労働は命じられない
高度人材の雇用では、専門性や技術力を活かせる業務の提供が必須です。
主たる業務として、清掃作業や商品の仕分けなどの単純労働は命じられません。
例えば、ITエンジニアとして採用した高度人材に、データ入力作業だけをさせる行為はNGです。
採用時に提示した職務内容と、業務が大きく異なる場合も同様です。
業務内容が在留資格の要件を満たさない場合は、在留資格の取り消しにつながる可能性があります。
注意点② 在留カードを確認する
在留カードには在留資格や在留期間、資格外活動許可の有無などが記載されています。
まずは在留資格が高度専門職1号、または高度専門職2号か確認してください。
次に、在留期間の確認をおこない、更新時期を把握します。
就労可能な活動範囲も確認しつつ、予定している業務内容が認められた範囲内か確認しましょう。
在留カードの記載内容と実際の就労状況に齟齬が生じないよう、適切な管理体制を整えなければいけません。
まとめ
高度人材ポイント制は、専門知識や技術を持つ外国人材を戦略的に受け入れる制度です。
学歴や職歴、年収などの項目で70点以上を獲得すると認定され、さまざまな優遇措置を受けられます。
企業にとっては、グローバルビジネスの拡大や人手不足の解消できる点がメリットです。
外国人採用を検討する際は、制度の内容や申請手続きを理解したうえで、自社に適した受け入れ計画を立てましょう。