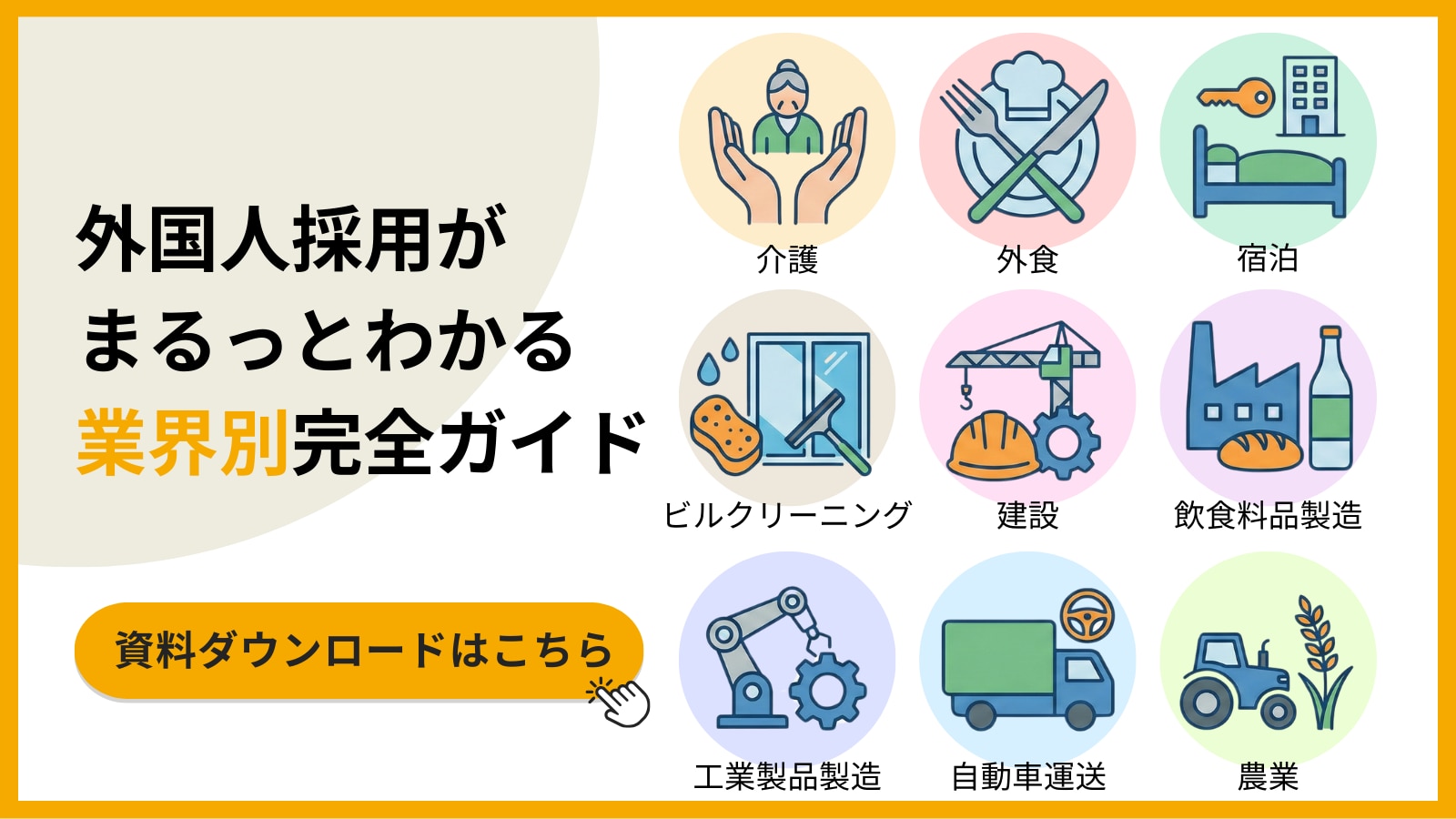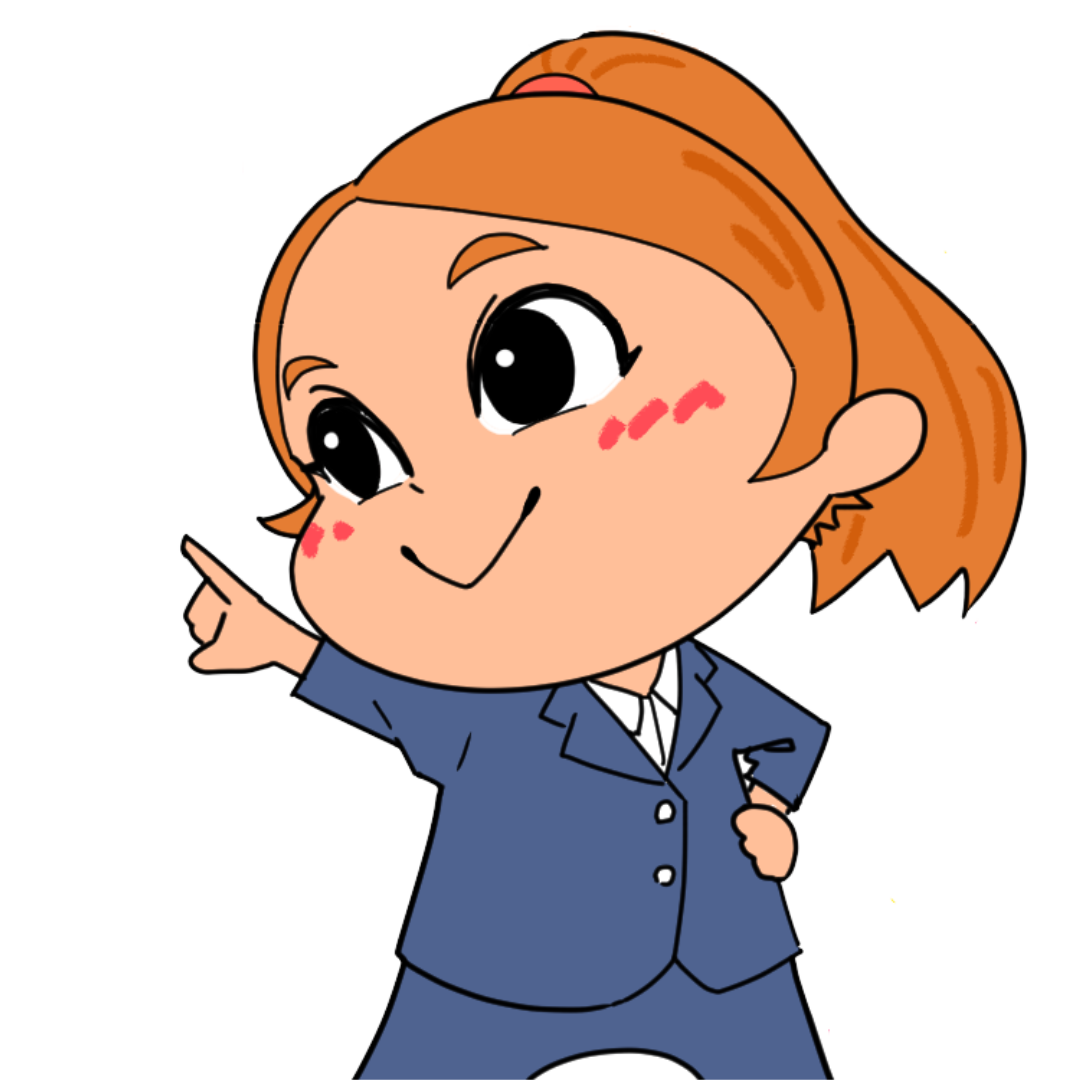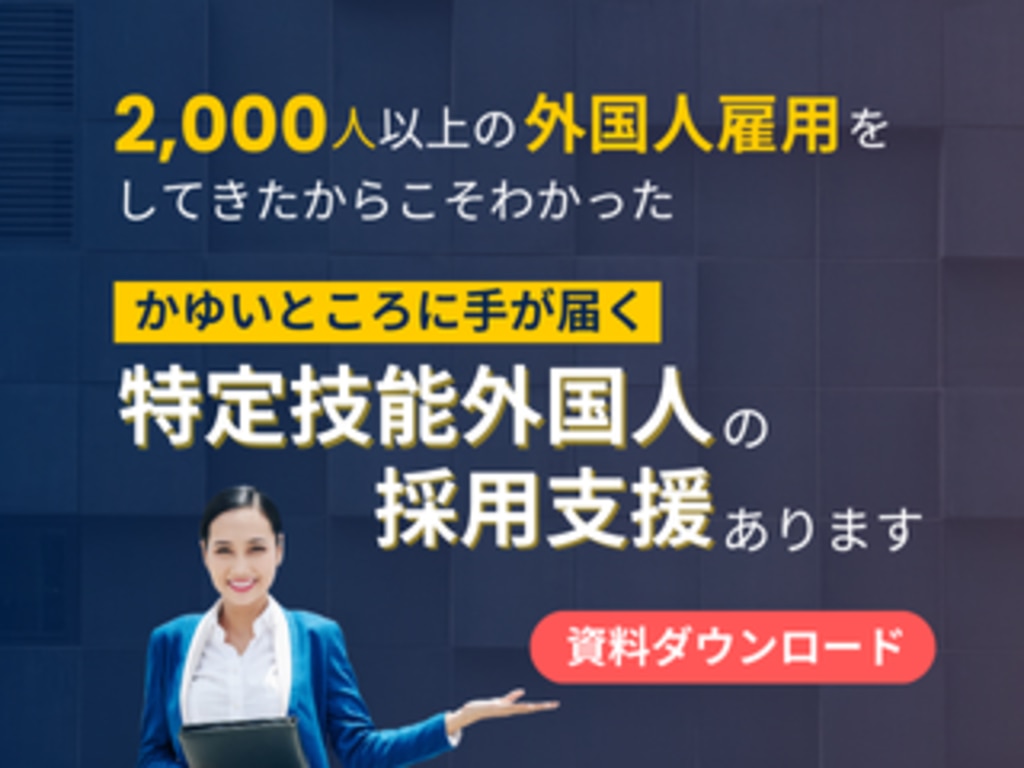不法就労助長罪とは?該当する3つのケースと企業が気をつけるポイント
外国人を雇用する際は、法令違反にならないためにも不法就労助長罪の把握が必要です。
近年は人手不足を背景に、外国人の採用を検討する企業が増える一方で、在留資格や就労条件の確認不足により予期せず違反になるケースが発生しています。
不法就労助長罪は2025年6月から罰則が強化され、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科せられます。
本記事では、不法就労助長罪の定義や具体的な事例、企業が取るべき対策を詳しく解説します。
外国人を適切に雇用し、コンプライアンスを確保するために必要な情報を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次[非表示]
- 1.不法就労とは
- 2.不法就労助長罪とは
- 2.1. ➀不法滞在の外国人を就労させたケース
- 2.2. ②就労不可の外国人を就労させたケース
- 2.3. ③在留資格の制限を超えて就労させたケース
- 3.不法就労助長罪の罰則
- 3.1.処罰の対象
- 4.外国人を雇用する企業が注意すること
- 4.1.身元確認を欠かさない
- 4.2.在留カードを必ず確認する
- 4.3.外国人人材紹介サービスを利用する
- 5.不法就労助長罪の事例
- 6.まとめ
不法就労とは
不法就労とは、日本国内で就労資格を持たない外国人が、収入を伴う活動をする行為を指します。
主なケースは以下の3つです。
|
例えば、ビザの期限切れ後も滞在を続け就労する場合が、不法就労にあたります。
また、観光ビザで入国した外国人がアルバイトをしたり、留学生が許可された時間を超えて働いたりするケースも同様です。
不法就労は現在、入国管理局による監視が強化されています。
就労資格を持たない本人だけでなく、雇用した企業側も罰則の対象となるため注意が必要です。
参照元:不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。
不法就労助長罪とは
不法就労助長罪は入管法第73条の2に規定される罪で、外国人を不法に雇用したり、不法就労を斡旋したりした者に対して法的措置を講じる制度です。
現在、不法就労助長罪の検挙件数は200件以上と、犯罪インフラに該当する事犯の中でも大きな割合を占めています。
罪になる基準は、企業側が外国人の就労資格を確認する義務を果たしていたかどうかです。
ここでは、不法就労助長罪に該当する3つのケースを詳しく解説します。
➀不法滞在の外国人を就労させたケース
不法就労助長罪の代表的なケースは、密入国者や在留期限を超過して滞在する外国人を雇用する行為です。
主なケースは3つあります。
|
企業は従業員の在留期限を把握し、更新手続きを適切に管理する責任があります。
在留期限の確認を怠ったがために不法就労を助長しないよう、在留カードの有効期限は必ず把握しておかなければなりません。
②就労不可の外国人を就労させたケース
日本に滞在するための資格は、2024年3月時点で29種類あります。
そのうち、就労が認められているのは19種類です。
観光などの短期滞在や文化活動の資格では、原則として就労が禁止されています。
留学生や家族滞在の資格を持つ外国人の場合は、資格外活動許可を取得すれば一定の条件下で就労が可能となりますが、週28時間が限界です。
企業側は採用する時に在留資格のほか、外国人の就労が許可されているか、また就労可能な範囲はどこまでなのかを正確に把握しなければなりません。
③在留資格の制限を超えて就労させたケース
不法就労助長罪は、外国人に対して在留資格で許可された活動の範囲を超えて働かせた場合も含まれます。
例えば、料理人として技能の滞在資格を取得している外国人を、まったく異なる業務に従事させるケースです。
特定技能の滞在資格では、認められた特定産業分野以外での就労は禁止されています。
また、留学生のアルバイトで週28時間の制限を超えて働かせた場合も違法です。
企業は採用時だけでなく、就労開始後も滞在資格で認められた活動範囲を超えていないか、継続的なチェックが求められます。
不法就労助長罪の罰則
不法就労助長罪の罰則は2025年6月から強化され、現行の3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金から、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金へと引き上げられます。
厳罰化の背景には、近年の人手不足を背景とした外国人雇用の増加に伴い、不法就労に関する問題が社会的な課題となっているためです。
罰則は罰金刑で済まない可能性もあり、状況によっては拘禁刑と罰金の両方が科されるケースもあります。
実際の判例では、不法就労と知りながら外国人を雇用した企業の経営者が実刑判決を受けたケースや、確認不足による過失があったとして罰金刑に処されたケースが報告されています。
企業はこれまで以上に、厳格な法令遵守を求められるでしょう。
参照元:不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。
処罰の対象
不法就労助長罪における処罰の対象は、雇用主に限らず広範囲に及びます。
直接雇用した企業をはじめ、不法就労者に仕事を斡旋した仲介業者や、職場を提供した事業主も罪に問われる対象です。
また、不法就労者に宿泊施設を提供・パスポートを預かった人物も罪に問われます。
不法就労と知らなかったという理由だけでは、免責されないため注意が必要です。
滞在資格の確認を適切に行わなかったなど、企業側に過失があると判断された場合も、処罰の対象です。
したがって、外国人を雇用する企業は、滞在資格の確認や就労条件の管理を徹底しておく必要があります。
外国人を雇用する企業が注意すること
外国人を雇用する際に企業がもっとも注意すべきポイントは、適切な身元確認と滞在資格の確認です。
入管法で定められた雇用管理の基準に従い、以下の3つを細かくチェックしましょう。
|
それぞれの注意点を詳しく解説します。
身元確認を欠かさない
外国人雇用の身元確認では、在留カードに記載された情報と本人が一致するか確認しなければなりません。
主に以下の記載内容をチェックします。
|
特に注意すべきポイントは、近年増加している偽造在留カードへの対応です。
不正な手段で入手した在留カードを使用するケースは数多く報告されているため、確認時は細心の注意を払いましょう。
また、確認した内容は雇用管理簿に記録し、保管する必要があります。
加えて、ハローワークへの届出も必要となるため、記録に漏れがないよう徹底しなければなりません。
在留カードを必ず確認する
在留カードの確認では、カードが本物か偽物かの判定をしなければなりません。
出入国在留管理庁が公開している偽造防止機能の確認ポイントを参考に、ホログラムの確認や色の変化などをチェックします。
また、在留カード等読取アプリケーションを利用すれば、ICチップ内の情報を読み取り、カードが真正なものか確認できます。
出入国在留管理庁のWebサイトでは、カード番号から失効情報を照会できるサービスも提供しているので活用するといいでしょう。
偽造カードの使用による不法就労を防ぐためにも、これらの確認手段は組み合わせて用いるべきです。
在留カードの確認は、外国人雇用の基本作業といっても過言ではありません。
外国人人材紹介サービスを利用する
外国人の雇用を適切に行うためには、専門的なサポートを受けられる人材紹介サービスの利用がおすすめです。
優良な紹介サービスでは、滞在資格の確認から各種申請手続き、就労開始後の従業員管理まで、一貫したサポートを提供しています。
初めて外国人材を採用する企業にとっては、法令遵守の観点からも心強い味方です。
また、人材紹介サービスを通じた採用では、滞在資格や就労条件などの確認が事前に完了しているため、不法就労のリスクを大幅に軽減できます。採用後のフォローアップ体制も整っており、在留期限の管理や更新手続きなども安心して任せられるでしょう。
不法就労助長罪の事例
警察庁の統計によると、2022年の不法就労助長罪の検挙件数は246件に上り、具体的な違反事例は数多く報告されています。
代表的な事例は、人材派遣会社の日本人社員らが技能実習の滞在資格を持つベトナム人を水産加工会社に派遣し、就労させたケースです。
この事案では、複数の関係者が不法就労助長罪で逮捕され、仲介したベトナム人も不法就労斡旋の罪に問われました。
また、大手飲食チェーンでは、留学生の就労時間制限である週28時間を超えて働かせたとして、経営者や労務担当者らが書類送検されています。
食品メーカーの事例では、通訳などの滞在資格で来日した外国人を工場での単純作業に従事させ、資格の活動範囲を超えた就労をさせたとして不法就労助長罪に問われました。
これらの事例から見えてくるのは、企業による法令理解の不足や確認作業の甘さです。
意図的な違反だけでなく、知識不足や確認不足による過失であっても、厳しい処罰の対象となる重みを理解する必要があります。
参照元:令和5年における組織犯罪の情勢(警察庁)/SNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況(警察庁)/デジタル空間における情報流通の健全性に関する基本理念(総務省)
まとめ
不法就労助長罪は、企業の確認不足や認識の甘さから発生するケースが多く見られます。
企業は2025年6月からの罰則強化により、慎重かつ的確な対応が必要です。
採用時の滞在資格確認をはじめ、就労開始後も在留期限や就労条件の管理を徹底しなければなりません。
特に注意したいのが、在留カードが本物かどうかの確認です。
偽造カードが増加している現状では、出入国在留管理庁が提供する各種確認手段を活用する必要があります。
不安がある場合は、人材紹介サービスの利用を検討しましょう。
外国人材の採用は企業の成長に不可欠ですが、コンプライアンス違反は企業の存続にも関わる重大な問題になるため注意が必要です。