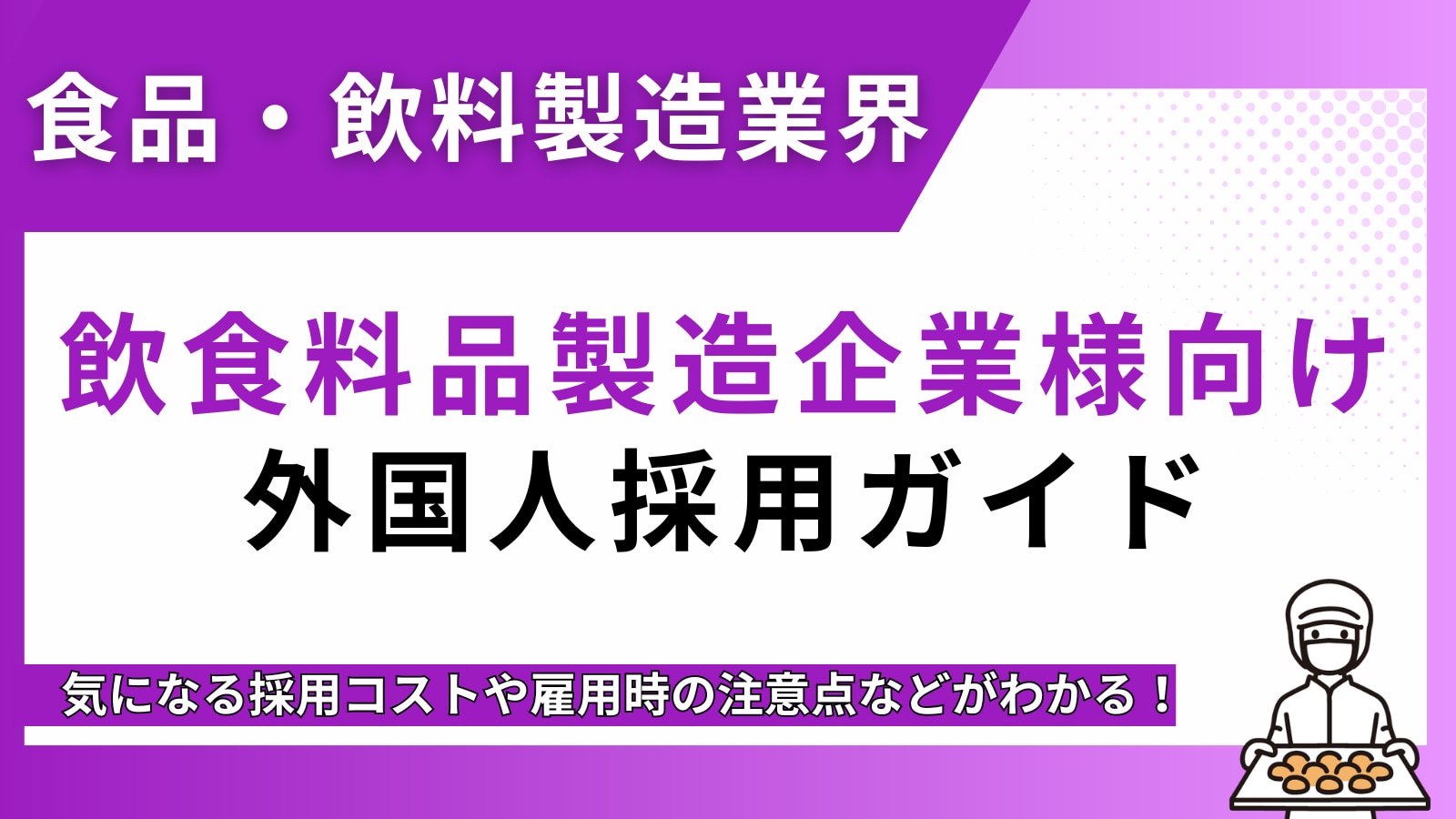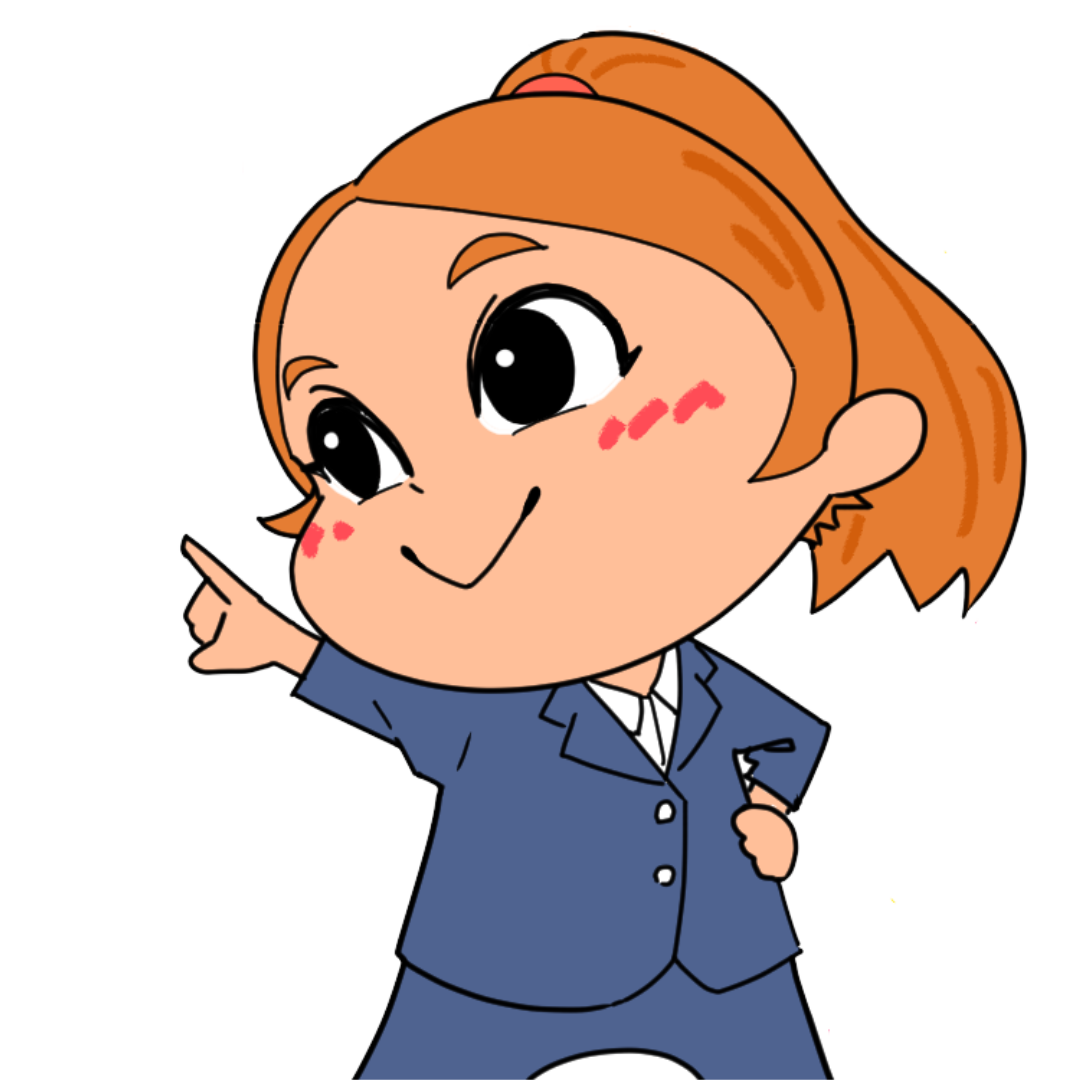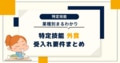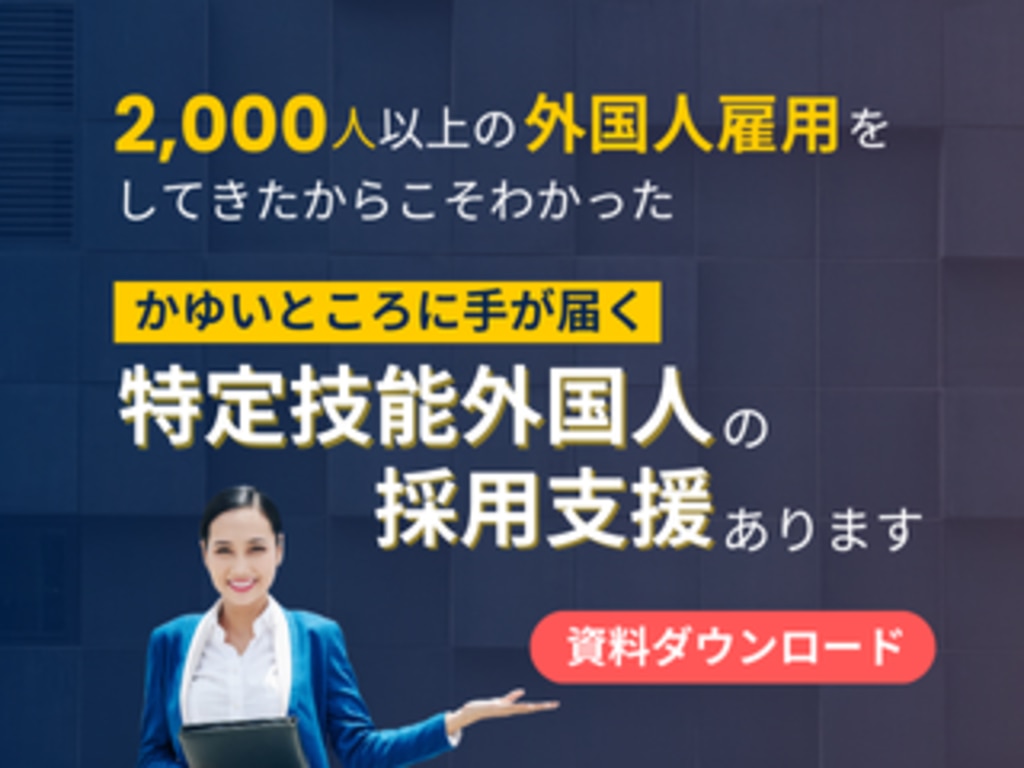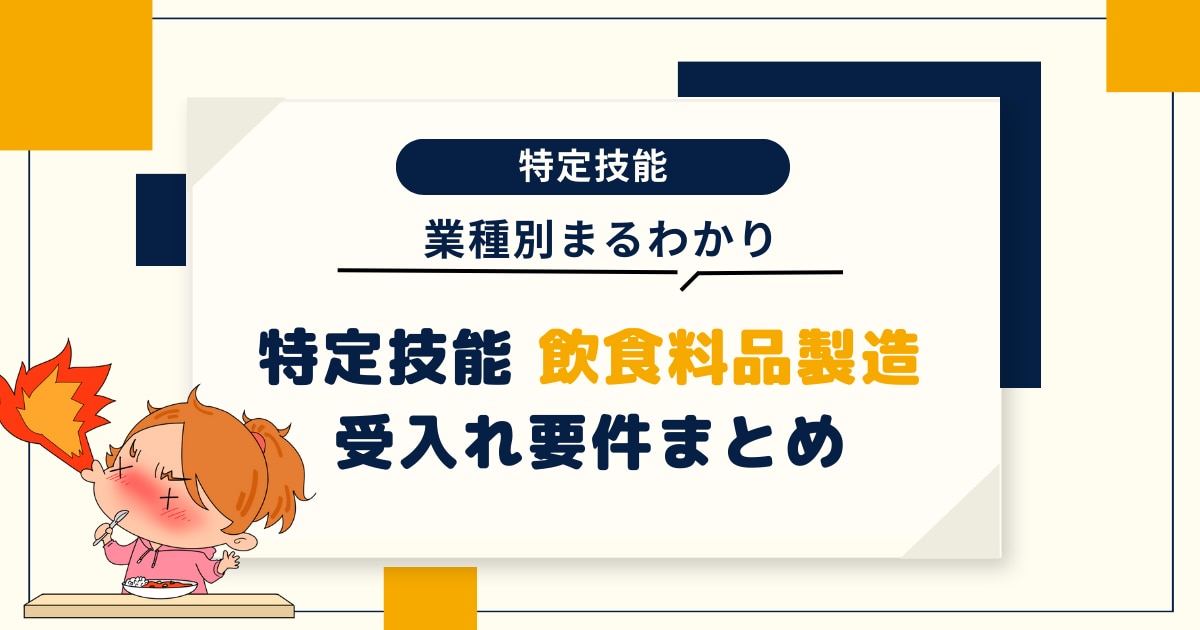
特定技能「飲食料品製造業」とは?受け入れ要件や採用の流れを解説
特定技能は、日本の深刻な人手不足を補うために生まれた在留資格です。
2019年4月からスタートしており、介護・外食業・宿泊・飲食料品製造業・ビルクリーニングなど全16分野が対象です。
本記事では、そのなかから「飲食料品製造業」に絞って、基礎知識から必要なサポート体制まで、わかりやすく解説します。
特定技能外国人の採用を検討している企業の担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。
| 【飲食料品製造業向け】 外国人採用 完全ガイド 飲食料品生産業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。意欲をもって真面目にはたらく特定技能外国人が安定した労働力を提供します。 |
目次[非表示]
- 1.特定技能について
- 2.特定技能「飲食料品製造業」とは
- 3.特定技能「飲食料品製造業」の需要が増えている理由
- 4.特定技能「飲食料品製造業」の対象となる業種
- 5.特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を受け入れる事業者の条件
- 5.1.農林水産省が定める受入れ要件を満たしている
- 5.2.支援体制が整っている
- 6.特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を受け入れる際に押さえておきたいポイント
- 6.1.ポイント①日本人と同等の給与や福利厚生を提供する
- 6.2. ポイント②住居を用意する
- 6.3.ポイント③求人広告を他社と差別化する
- 6.4.ポイント④異文化を受け入れる体制を整える
- 6.5.ポイント⑤同じ国籍の人材を複数名採用する
- 6.6.ポイント⑥人材派遣会社と協力して採用活動を行う
- 6.7. ポイント⑦面接や内定を早めに行う
- 7.特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を採用する流れ
- 8.特定技能1号「飲食料品製造業」を取得できる要件
- 8.1.飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格している
- 8.2.日本語能力を測る試験に合格している
- 8.3.技能実習2号または3号を良好に修了する
- 8.4.HACCP(ハサップ)を含む衛生管理の知識がある
- 9.特定技能2号「飲食料品製造業」を取得できる要件
- 10.特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を受け入れるには、農林水産省の要件をクリアする必要がある
特定技能について

特定技能とは、在留資格の一つです。特定技能1号、2号の2種類があります。
1号は特定の産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要としている技能を有する業務に従事する外国人に向けた資格です。
2号は、特定の産業分野に属する熟した技能を有している外国人向けの在留資格となります。
資格を取得するためには、日本語試験と技能試験を受けて合格しなければなりません。
そのため、特定技能を有している外国人を採用する場合、日本語が話せることに加えある程度各分野に関する知識を持った人材の作用が可能です。
特定技能は、日本人の雇用だけだと不足してしまう労働力を補うために活用可能です。
同じく、外国人向けの在留資格である技能実習は受け入れ人数の制限がありますが、特定技能の場合、建設と介護分野を除いて人数制限がありません。
また、直接雇用が可能なのも特徴です。
関連記事:特定技能1号と2号のビザの違いは?採用前に知りたい注意点を解説
関連記事:特定技能外国人を採用する流れ
特定技能「飲食料品製造業」とは
特定技能「飲食料品製造業」は、酒類を除く飲食料品の製造・加工・安全衛生など、飲食料品の製造全般に従事できる在留資格です。
労働力不足が深刻な飲食料品製造業界において、戦力となる外国人材を受け入れるために設けられました。
飲食料品製造業をはじめとする特定技能には、以下の2種類があります。
特定技能の種類
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
可能な業務 | 特定産業分野に属する、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務 | 特定産業分野に属する、熟練した技能を要する業務 |
在留期間 | 1年、6か月、または4か月ごとの更新(通算で上限5年まで) | 3年、1年または6か月ごとの更新(上限なし) |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に不可 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関または登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
特定技能2号は、特定技能1号と比べてよりレベルの高い技能が求められます。
2023年には受入れ分野が「介護」以外のすべての特定産業分野に拡大され、従来は特定技能1号のみだった飲食料品製造業も対象となりました。
参照元:法務省:特定技能ガイドブック
特定技能「飲食料品製造業」の需要が増えている理由
特定技能「飲食料品製造業」の需要は、近年急増中です。
有資格者の受入れ人数は、2022年6月の29,617人から、2023年6月には53,282人、2024年6月には70,202人と、去年までの2年間で2倍以上になっています。
さらに2024年4月からの5年間では、13万9,000人の受入れが見込まれており、この分野において特定技能外国人がまだまだ求められていることがわかります。
この需要増加の背景には、以下の要因があります。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」
6次産業化
まず考えられる背景としては、飲食料品製造業の6次産業化が挙げられます。
6次産業化とは、1次産業の農林漁業、2次産業の製造業、3次産業の小売業を融合させ、それぞれの事業を一体的に推進する取り組みのことです。
これにより、これまで農林漁業のみを行ってきた事業者が、単なる生産だけでなく、加工や販売を行うケースが増加しました。
しかし、加工や販売の業務が増えるにつれ、従来の農林漁業者だけではすべての業務をカバーしきれなくなり、人手不足への対策が急務となったのです。
こうした事情から、多様な業務に対応できる人材が求められ、特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を持つ外国人材が活用されるようになりました。
日本での技能の習得を目的とする“技能実習生”が、細分化された特定の業務しか担当できないのに対し、特定技能外国人はより幅広い業務に対応できます。
その点が評価され、特定技能「飲食料品製造業」の有資格者は、6次産業化を推進する事業者にとって重要な労働力となっています。
技能実習からの移行
技能実習制度で日本に滞在していた外国人材が、特定技能へ移行するケースが増えていることも理由の一つです。
技能実習2号を良好に修了すると、特定技能評価試験と日本語試験が免除された状態で、在留資格を特定技能1号に移行できます。
外国人材からすると特定技能1号に移行すると転職が可能となり、雇用拡大のチャンスが広がる点は大きな魅力です。
受入れ企業側としても、技能実習生はすでに日本語や日本の職場環境に慣れているため、教育コストを抑えて、実務経験のある人材を確保することが叶います。
このように、外国人材と受入れ企業は、技能実習から特定技能への移行を望んでいる点で思惑が一致しているのです。
なお、技能実習制度は2027年に廃止され、新たに育成就労制度が施行されることが決定しています。
特定技能「飲食料品製造業」の対象となる業種
特定技能「飲食料品製造業」の有資格者が従事できるのは、以下の9つの業種です。
特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を雇用できる業種
- 食料品製造業
- 清涼飲料製造業
- 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 製氷業
- 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る)
- 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る)
- 菓子小売業(製造小売)
- パン小売業(製造小売)
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)
このうち食料品製造業は、さらに以下の9つに分類されます。
食料品製造業の種類
- 畜産食料品製造業
- 水産食料品製造業
- 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
- 調味料製造業
- 糖類製造業
- 精穀・製粉業
- パン・菓子製造業
- 動植物油脂製造業
- その他の食料品製造業
このように、特定技能「飲食料品製造業」の対象となるのは、飲食料品の製造に関わるほとんどの業務です。
ただし、酒類や塩、香料、ペットフードなど、一部の製品の製造に関しては、対象外となっています。
参照元:「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を受け入れる事業者の条件
特定技能外国人は、飲食料品製造業を営む事業者にとって大きな戦力といえますが、受け入れるためには、所定の条件を満たす必要があります。
どのような条件が課せられているのかを確認しておきましょう。
農林水産省が定める受入れ要件を満たしている
特定技能外国人と直接雇用計画を結ぶ企業を、“特定技能所属機関”といいます。
この特定技能所属機関になるためには、農林水産省が定める次の要件をクリアすることを求められます。
引用元:出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」
上に挙げた通り、特定技能所属機関は農林水産省などで構成される“食品産業特定技能協議会”の構成員でなければなりません。
食品産業特定技能協議会の構成員になると、状況調査などの協力に応じる義務が生じます。
支援体制が整っている
特定技能外国人を受け入れる際は、農林水産省の定める要件が満たされていることに加えて、支援体制の整備も求められます。
人材の採用にあたって企業には、入国前のガイダンスや出入国時の送迎、日本での生活オリエンテーションなど、多岐にわたる支援義務が生じます。
さらに、受入れ後も苦情への対応や定期的な面談、転職時のサポートなど、継続的な支援を続けなければなりません。
これらの支援は自社で行うことも可能ですが、ノウハウがない場合や過去2年以内に外国人材の受入れ実績がない場合は、登録支援機関に委託する必要があります。
登録支援機関は、特定技能外国人の支援を専門に行う機関で、企業がスムーズに受入れを進められるようサポートしてくれます。
| 【飲食料品製造業向け】 外国人採用 完全ガイド 飲食料品生産業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。意欲をもって真面目にはたらく特定技能外国人が安定した労働力を提供します。 |
特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を受け入れる際に押さえておきたいポイント

特定技能「飲食料品製造業」は、日本で働きたい外国人に人気がある資格の一つで、在留資格を持つ求職者は大勢います。
その一方で、特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を募集する企業も多いため、優秀な人材の獲得には、採用戦略の見直しが必要です。
ここからは、特定技能「飲食料品製造業」を持つ外国人材を受け入れる企業が押さえておきたい7つのポイントを解説します。
ポイント①日本人と同等の給与や福利厚生を提供する
特定技能の外国人材を採用する際、賃金や福利厚生の待遇は日本人の従業員と同等以上にする必要があります。
これは、出入国在留管理局の審査基準にも含まれており、適正な給与が設定されていなければ在留資格の取得が認められません。
また、給与が低ければその分、求職者から選ばれにくくなるので、良い人材の確保に動くなら、業界水準以上の給与の提示が望ましいでしょう。
くわえて、ボーナスや昇給制度、有給休暇の付与、社会保険の整備など、日本人の従業員と同じ条件を提供することで、長期的な定着を促せます。
ポイント②住居を用意する
外国人材は、日本での住居の確保に苦労する場面が少なくありません。
特に単身で来日する場合、保証人の問題や言語の壁が原因で、住まいが見つからないことが往々にしてあります。
そのため、外国人材を受け入れる企業が寮や社宅を提供できると、採用競争力を高める大きなポイントになります。
寮を用意できない場合でも、契約の際に企業が同席したり、保証人代行サービスを利用したりして、住居の確保を支援することが重要です。
住環境が整っていれば、外国人材の定着率も目に見えて向上するでしょう。
ポイント③求人広告を他社と差別化する
求職者は、応募する企業を検討する際、求人広告の内容を参考にします。
ひと目見ただけで魅力を感じる求人を作成するためには、他社との差別化を意識することが必要です。
たとえば、以下のような工夫が効果的です。
求人広告を他社と差別化する工夫
- 給与面で競争力を持たせる
- すでに外国人材が在籍していることをアピールする
- 研修制度やキャリアアップ支援を明記する
また、応募者が理解しやすいような、求人情報の多言語対応もポイントになります。
ポイント④異文化を受け入れる体制を整える
外国人材が安心して働ける環境を作るためには、企業側が異文化を受け入れる姿勢を持たなければなりません。
日本のビジネスマナーや習慣に慣れていない外国人は多いため、企業も文化の違いを理解し、双方で歩み寄る努力が求められます。
外国人向けのオリエンテーションを実施したり、社内に多文化共生のためのサポート体制を整えたりすることが有効です。
また、日本語学校の紹介や地域コミュニティと交流する機会を設ければ、外国人材が日本での生活に適応しやすくなります。
ポイント⑤同じ国籍の人材を複数名採用する
言語の壁が原因で外国人材が孤立し、離職へとつながるケースは珍しくありません。
これを防ぐには、同じ国籍の人材を複数名採用するのがおすすめです。
同国出身の同僚がいれば、仕事の悩みや生活の不安を相談し合うことを通じ、精神的な負担を軽減できます。
また、すでに働いている同国の外国人材がいる場合は、その方に新しい外国人材のフォローを担当してもらうことで、定着率の向上が期待できるでしょう。
ポイント⑥人材派遣会社と協力して採用活動を行う
特定技能外国人を受け入れる際は、人材派遣会社や登録支援機関の協力によって、スムーズな採用が可能になります。
人材派遣会社は豊富な採用ノウハウを持っており、適切な候補者とのマッチングをサポートしてくれるため、採用の成功率を高めることができます。
また、求職者の紹介だけでなく、就業後のフォローアップも行ってくれるため、企業側の負担が軽減されるはずです。
ポイント⑦面接や内定を早めに行う
優秀な特定技能外国人材を確保したい場合、迅速な面接や内定が重要です。
特に、国内在住の外国人を採用する場合は、他社と競争になることが多いため、対応の遅れが採用の機会損失につながるとも考えられます。
また、ビザの取得手続きには一定の時間を要するので、内定を出したらすぐに申請準備を進めなければなりません。
採用プロセスの各フェーズで素早い対応を心がけることで、優秀な人材を確保しやすくなります。
在留資格を持つ外国人材を採用する具体的な流れは、次項で詳しく解説します。
特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を採用する流れ
それでは、特定技能外国人を受け入れる際の一連の流れを見ていきましょう。
国内に在留中の場合と、海外に居住している場合の2つのケースに分けて紹介します。
日本国内に在留中の外国人を受け入れる場合
すでに日本にいる外国人を採用する場合は、以下の流れになります。
日本人の採用とは異なる部分があるので、しっかりとご確認ください。
日本国内に在留中の外国人を受け入れる場合
- 外国人が特定技能試験に合格または技能実習2号を良好に修了
- 採用活動(人材の募集や面接など)
- 雇用契約の締結
- 1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
- 地方出入国在留管理局(入管)に在留資格変更許可を申請
- 在留資格の変更許可
- 就労開始
在留期限までに、特定技能1号への在留資格変更許可を申請することが難しいときは“特定活動(特定技能移行準備)”という特例措置が認められる場合があります。
参照元:出入国在留管理庁「受入れ機関の方」
海外に居住する外国人を受け入れる場合
続いて、特定技能の在留資格を持って、海外から新たに来日する場合を紹介します。
海外に居住する外国人を受け入れる場合
- 外国人が特定技能試験に合格または技能実習2号を良好に修了
- 採用活動(人材の募集や面接など)
- 雇用契約の締結
- 1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
- 地方出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書交付を申請
- 在留資格証明書の受領
- ビザを申請
- ビザを受領
- 入国
- 就労開始
入国時に空港でパスポートやビザ、在留資格認定証明書が必要となるため、漏れなく揃えておきましょう。
なお、ビザの申請は、外国人が居住している国の在外公館で行います。
参照元:出入国在留管理庁「受入れ機関の方」
| 【飲食料品製造業向け】 外国人採用 完全ガイド 飲食料品生産業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。意欲をもって真面目にはたらく特定技能外国人が安定した労働力を提供します。 |
特定技能1号「飲食料品製造業」を取得できる要件
先述の通り、現在特定技能「飲食料品製造業」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類の在留資格があります。
このうち特定技能1号に関しては、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格に加えて、一定の日本語能力の証明が求められます。
特定技能1号「飲食料品製造業」の合格基準
技能水準 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 |
日本語能力 | “国際交流基金日本語基礎テスト”または“日本語能力試験(N4以上)” |
なお、技能実習2号または3号を良好に修了している場合は、この限りではありません。
それぞれの詳しい試験内容や要件については、以下で掘り下げていきます。
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格している
外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施している“飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験”は、飲食料品製造業に必要な技能水準を確認するテストです。
学科試験のほかに、図や計算式を用いて解答する実技試験もあります。
受験資格 | 在留資格を有しており、以下両方を満たす者 |
試験時間 | 70分 |
実施方法 | ペーパーテスト方式(マークシート) |
合格基準 | 65%以上 |
受験料 | 国内試験:8,000円 |
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験は、日本国外での受験も可能です。
受験資格や受験料が異なる場合があるので、公式サイトで最新の情報をご確認ください。
参照元:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
日本語能力を測る試験に合格している
特定技能外国人としての日本語能力を認められるためには、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験に合格しなければなりません。
日本語能力を測る試験
国際交流基金日本語基礎テスト | 日本語能力試験 | |
形式 | CBT方式 | マークシート方式 |
内容 | ・文字と語彙 | ・言語知識 |
受験料 | 7,000円 | 7,500円 |
開催頻度 | 年6回 | 年2回(国外受験の場合は、年1回の場合がある) |
レベルの目安 | 「A2」以上:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力 | 「N4」以上:基本的な日本語を理解できる程度の能力 |
国際交流基金日本語基礎テストは、得点に応じてA1~C2の6段階で判定されます。
このうち、特定技能ではA2以上の評価が必要です。
日本語能力試験の場合は、試験がN1〜N5の5段階に分かれており、特定技能ではN4以上の4つの試験いずれかに合格することが求められます。
| 【動画でわかる】 外国人の日本語レベル JLPT(日本語能力試験)N1~N5レベルの外国人が、日本語を話している動画をまとめました。 「外国人採用を検討する予定がある」「募集条件の設定が必要」など、外国人の日本語レベルが分からない場合に活用いただける資料です。 |
技能実習2号または3号を良好に修了する
技能実習2号または3号を良好に修了している場合、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験や日本語能力を測る試験が免除されます。
ただし、修了した技能実習の内容がこれから従事する予定の業務と関連性があると認められる必要があり、技能実習であればどの分野でも働けるというわけではありません。
特定技能1号への移行が可能であるかどうかは、外国人技能実習機構の公式サイトにある移行対象職種情報で確認できます。
HACCP(ハサップ)を含む衛生管理の知識がある
食品衛生法改正により、2021年6月から、飲食料品製造業の事業者は“HACCP”に沿った衛生管理に取り組むことが義務づけられました。
HACCPとは、飲食料品の安全性を確保するための衛生管理手法であり、製造工程を分析し、危害要因の除去・低減を目的としています。
HACCPに沿った衛生管理に関する基準
基準 | 概要 |
危害要因の分析 | 食品または添加物の製造、加工、調理、運搬、貯蔵または販売の工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させうる要因(危害要因)の一覧表を作成し、これら危害要因を管理するための措置(管理措置)を定めること |
重要管理点の決定 | ①で特定された危害要因の発生の防止、排除または許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが不可欠な工程を重要管理点として特定すること |
管理基準の決定 | 個々の重要管理点において、危害要因の発生の防止、排除または許容できる水準にまで低減するための基準(管理基準)を設定すること |
モニタリング方法の設定 | 重要管理点の管理の実施状況について、連続的または相当な頻度の確認(モニタリング)をするための方法を設定すること |
改善措置の設定 | 個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定すること |
検証方法の設定 | ①~⑤に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること |
記録の作成 | 営業の規模や業態に応じて、①~⑥に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成すること |
小規模営業者等への弾力的運用 | 小規模な営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省で確認した手引書に基づいて対応することが可能 |
先ほど紹介した飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験では、HACCPによる衛生管理の知識も出題範囲に含まれます。
参照元:厚生労働省「HACCP(ハサップ)」
特定技能2号「飲食料品製造業」を取得できる要件
特定技能2号は、配偶者と子の帯同が認められ、永住権の取得要件をも満たしうることから、特定技能1号と比べて厳しい基準が設けられています。
技能水準に関しては、特定技能1号の場合と同様に、試験に合格することで証明しなければなりません。
特定技能2号「飲食料品製造業」の合格基準
技能水準 | 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験 |
実務経験 | 飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験 |
飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験では、飲食料品の製造・加工および安全衛生管理に関する高度な技能を有し、自らの判断で適切に業務を遂行できる能力が問われます。
なお、現時点では企業からの申し込みに限られており、外国人個人での受験はできないため、企業のサポートが必須となります。
さらに、この在留資格を得るには試験に合格するだけでなく、実際に職場で工程管理を行い、複数の従業員を指導・管理した経験が2年以上必要です。
ここでいう“複数の従業員を指導・管理した経験”とは、技能実習生やアルバイト、特定技能外国人を監督する、班長やライン長といった役職に就いていたことを指します。
特定技能「飲食料品製造業」の有資格者を受け入れるには、農林水産省の要件をクリアする必要がある
本記事では、特定技能「飲食料品製造業」の概要や、有資格者を受け入れる際に押さえておきたいポイントを解説しました。
特定技能外国人を直接雇用する“特定技能所属機関”になるためには、農林水産省が定める要件を満たしている必要があります。
また、特定技能外国人の住居探しのフォローや求人広告の工夫も、選ばれる企業になるうえで意識したい点です。
採用活動は人材派遣会社と協力して実施すると、企業は大きな恩恵を得られます。
スタッフ満足では、特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を持つ外国人材の就労をサポートしています。外国人材の採用から定着、育成までを徹底的にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
| 【飲食料品製造業向け】 外国人採用 完全ガイド 飲食料品生産業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。意欲をもって真面目にはたらく特定技能外国人が安定した労働力を提供します。 |