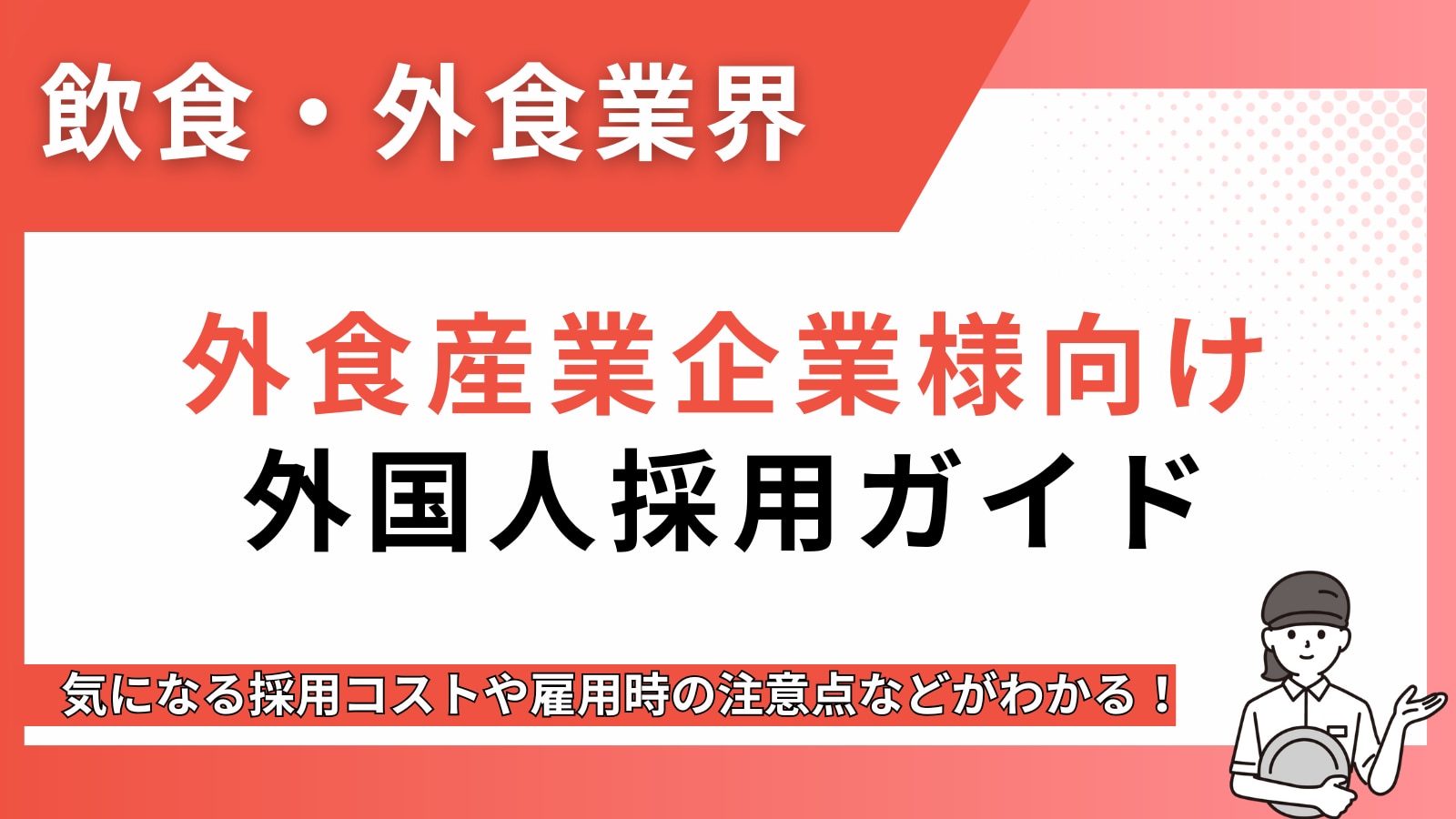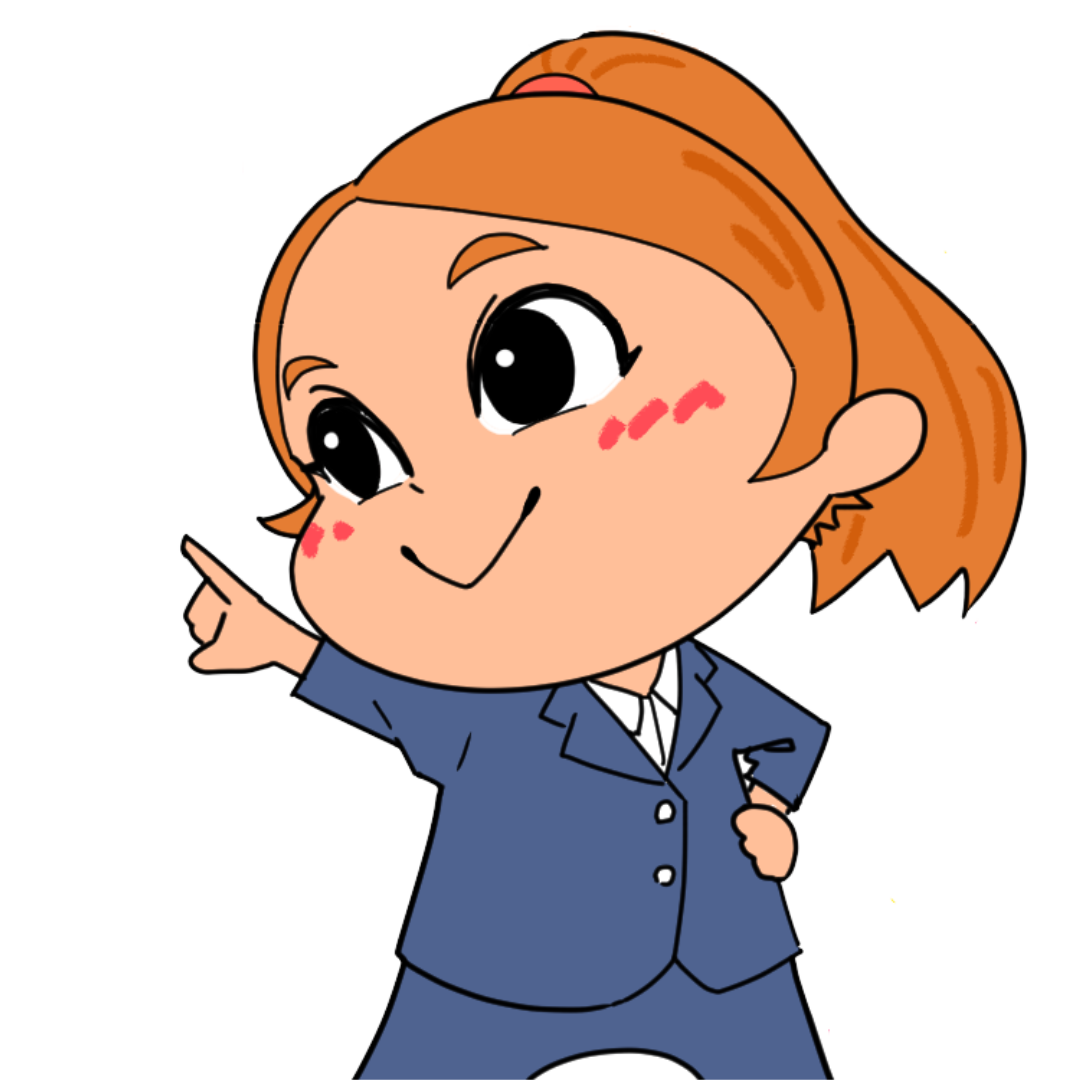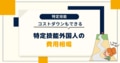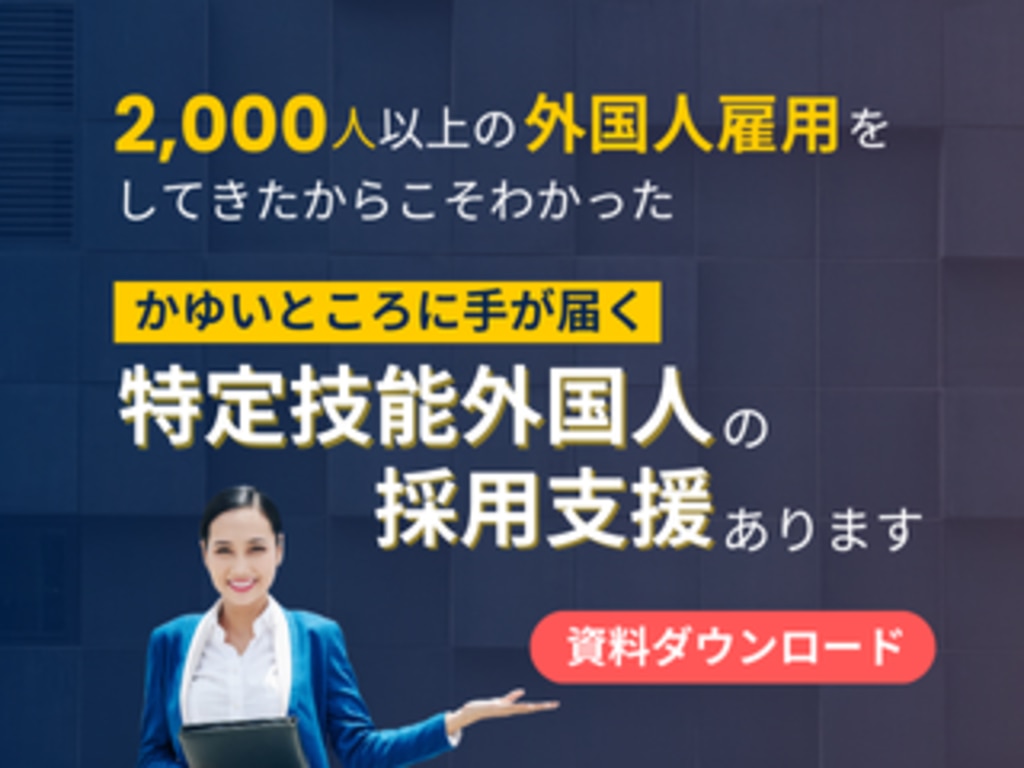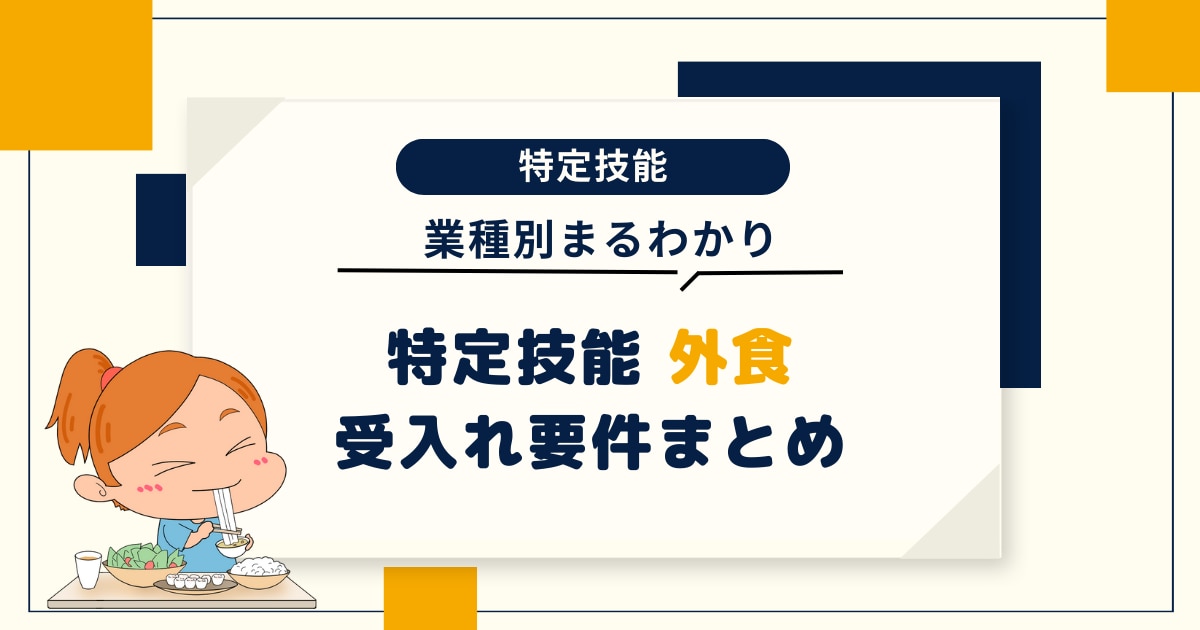
特定技能「外食業」とは?受け入れ企業の要件と飲食店での採用方法を解説
特定技能とは、人手不足が深刻化している分野で、外国人労働者を雇用するために創設された在留資格のことです。
対象となるのは、介護・外食業・宿泊・飲食料品製造業・ビルクリーニングなどを含む全16分野です。
本記事では、このなかから特定技能「外食業」を取り上げ、概要や要件、受入れまでの流れを解説します。
外国人労働者の雇用を検討している担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。
| 【飲食店&外食産業向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 即戦力として働ける特定技能外国人が、店舗運営をしっかりサポートします。 飲食業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |
目次[非表示]
特定技能「外食業」とは
特定技能「外食業」は、日本国内の飲食業において、一定の専門性や技能を持つ外国人労働者を受け入れるための在留資格です。
食堂やレストラン、持ち帰り専門店など、幅広い業態でこの資格を持つ外国人労働者の就労が認められています。
以下の表にある制度の詳細を確認していきましょう。
雇用形態 | 直接雇用に限定 |
報酬要件 | 日本人と同程度 |
受入れ見込み数 | 今後5年間で最大5万3,000人 |
特定技能「外食業」における外国人労働者の雇用形態は、直接雇用に限られ、派遣による雇用は認められていません。
報酬に関しては、外国人労働者にも日本人と同等の待遇を保証することが求められます。
これは、日本人労働者との賃金差別を禁止して、公正な労働環境を確保するための措置です。
外国人か日本人かといった国籍にかかわらず、能力に応じて支払う賃金を決めなければなりません。
特定技能の受入れ人数に制限はありませんが、国は人材不足の見込み数と受入れ人数を比較して、過大ではないことを証明するために受入れ見込み数を示しています。
それによると、外食業分野における受入れ見込み数は、令和6年から令和10年までの5年間で最大5万3,000人と想定されています。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度の受入れ見込み数の再設定」
関連記事:特定技能とは?
飲食業界の課題
特定技能「外食業」が誕生したのには、どのような背景があったのでしょうか?
以下で外食業を含む飲食業界の課題を確認し、その理由をひも解いていきましょう。
人手不足
特定技能「外食業」が創設された最大の理由として、飲食業界の慢性的な人手不足が挙げられます。
厚生労働省によると、宿泊業、飲食サービス業における令和5年の欠員率(人手不足の深刻度を表す指標)は、全産業のなかでもっとも高いことが判明しました。
翌年の令和6年には全産業中3番目にまで下がりましたが、依然として高い欠員率で推移しています。
このような飲食業界の人手不足の原因の一つとして、国内産業が共通して抱える少子高齢化問題が考えられます。
とりわけ飲食業界では立ち仕事が多く、身体的な負担が大きいため、若年層の働き手が求められますが、その層の人材が少ないのが現状です。
こうした状況下で、もはや日本人のみでは業務に必要な人員確保の見通しが立たなくなり、特定技能による外国人労働者の採用が進められたのです。
参照元:厚生労働省「令和6年上半期雇用動向調査結果の概況」
関連記事:飲食店の人手不足問題の原因とは?人材確保のための効果的な対策
労働環境の悪さ
労働環境の悪さも、特定技能「外食業」が創設された理由といえます。
飲食業界の賃金は、決して高い水準にあるとはいえません。
令和6年に行われた厚生労働省の調査によると、宿泊業、飲食サービス業の平均賃金は月収で26万9,500円と、全業界のなかでもっとも低い結果となりました。
そのうえ、飲食業界では、書き入れ時にあたる土日祝日や年末年始に休むことがなかなかできません。
人手が足りていない職場では、残業が求められるケースもあり、拘束時間が長くなりがちです。
こうした劣悪な労働環境では、従業員のモチベーションを保つことが難しく、人材が定着しません。
そこで「新しい土地で頑張ろう」と意欲の高い、外国人労働者の活躍が期待されているわけです。
参照元:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
特定技能「外食業」の対象となる業種・業務
特定技能「外食業」で外国人労働者を受け入れられる業種は、以下の通りです。
特定技能「外食業」の対象となる業種
業種 | 概要 | 例 |
飲食店 | 客の注文に応じ調理した飲食料品をその場で飲食させる | ・食堂 |
持ち帰り飲食サービス業 | 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する | ・持ち帰り専門店 |
配達飲食サービス業 | 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける | ・仕出し料理 ・弁当屋 |
給食事業等の飲食サービス業 | 客の求める場所で調理し、飲食料品の提供を行う | ・給食事業所 |
特定技能「外食業」を取得した外国人労働者は、飲食店や持ち帰り専門店のほか、病院や学校の給食施設といった、幅広い業種で雇用することができます。
業務内容としては、衛生管理・調理・接客など飲食業に関する業務全般に従事してもらうことができるため、人手不足に悩まされる企業にとって大きな助けとなるでしょう。
ただし、特定技能「外食業」の資格では、従事できないケースもいくつかあります。
たとえば、配達飲食サービス業で、調理も接客もさせず、デリバリー業務のみに従事させることは禁じられています。
また、ホテル内のレストランでの雇用は可能なものの、フロントやベッドメイキングなどそのほかのホテル業務を依頼することはできません。
特定技能「外食業」で雇用できるのはあくまで飲食業に関する業務に限定されるため、この点は遵守するように注意が必要です。
参照元:農林水産省「外食業分野における 特定技能外国人制度について」
| 【飲食店&外食産業向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 即戦力として働ける特定技能外国人が、店舗運営をしっかりサポートします。 飲食業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |
受入れ企業の要件
受入れ企業側も外国人労働者を雇用するにあたって、いくつかの要件を満たす必要があります。
以下でその要件を確認し、外国人労働者が安心して働ける環境づくりを心がけましょう。
条件
受入れ企業の要件における“条件”とは、外国人労働者を雇用するために、事前に整備しておかなければならない項目のことです。
この条件に準じて環境を整備しなければ、外国人労働者の受入れは認められません。
受入れ企業が外国人労働者を雇用するための条件には、以下の4つが挙げられます。
受入れ企業の条件
- 雇用契約が適切である
- 労働・社会保険および租税に関する法令を遵守している
- 外国人労働者を支援する体制がある
- 外国人労働者を支援する計画が適切である
冒頭でも確認したように「外食業」を含む特定技能では、外国人労働者と直接雇用契約を結ばなければなりません。
その際の契約内容は、報酬額や所定労働時間などの、規定された条件を取り漏らすことなく、かつ法令を遵守したかたちで定める必要があります。
また、外国人労働者を支援する体制・計画を整えることも不可欠です。
たとえば、“体制”としては、外国人労働者が十分理解できる言語で支援を実施することが条件に定められています。
“計画”では、出入国の際の送迎手順や住居・口座の確保方法、および日本語学習の支援内容などをあらかじめ決めておくことが求められます。
なお、上記で紹介したのは、4項目に大別した条件のうちの一部です。
より詳細な内容を知りたい場合には、出入国在留管理庁が提供している資料を確認する、もしくは同庁にお問い合わせください。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
義務
受入れ企業には、外国人労働者を雇用したあとにも、守らなければならない3つの“義務”が生じます。
受入れ企業に生じる義務
- 雇用契約を確実に履行する
- 外国人労働者への支援を適切に実施する
- 出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出を行う
受入れ企業は、事前に定めた雇用契約、ないし支援の体制・計画のもと外国人労働者の雇用を進めていかなければなりません。
また、これらの受入れ後の状況に関する届出を、出入国在留管理庁およびハローワークに対して定期的に行うことも求められます。
もし、この届出を適切に行わなかったことが発覚した場合は、指導・罰則の対象となり、引き続き特定技能による受入れができなくなります。
このように特定技能による受入れを実施するうえでは事前準備も大切ですが、その後の管理にも十分に気を配る必要があるわけです。
なお、外国人労働者への支援については、出入国在留管理庁から認定を受けた“登録支援機関”に委託することも可能です。
支援に関する業務をすべて委託すれば、受入れのハードルも下がるので、選択肢に入れておくことをおすすめします。
協議会への入会
上記に挙げた条件や義務は特定技能の全分野に該当する要件でしたが、このほかに分野別に設けられた協議会への加入も求められます。
協議会は、外国人労働者を適切な環境で受け入れられるように、構成員の連携強化・制度や情報の周知・法令順守の啓発を行う組織です。
特定技能「外食業」の場合は、“食品産業特定技能協議会”に加入する必要があります。
特定技能「外食業」の有資格者の受入れを実施する際の流れ
ここからは、実際に特定技能「外食業」の有資格者の受入れを行う際の流れを紹介していきます。
特定技能「外食業」の有資格者の受入れを実施する際の流れ
- 特定技能「外食業」による雇用が実現可能か確認する
- 人材募集・面接を実施する
- 雇用契約を結ぶ
- 支援計画書を策定する
- 協議会に入会する
- 在留資格申請を行う
- 外国人労働者の就労が始まる
これまでに見てきた内容が、どのタイミングで関わってくるのかも踏まえて確認していきましょう。
ステップ①特定技能「外食業」による雇用が実現可能か確認する
特定技能「外食業」に基づいて外国人労働者を雇用するための第一歩として、そもそも自社の業務で制度が利用可能かどうかを確認する必要があります。
特定技能「外食業」は、飲食業界にあるどのような仕事でも外国人労働者に任せられるという資格ではありません。
前述したように、配達飲食サービス業ではデリバリー業務にのみ従事させることやホテルのレストランスタッフとして雇用して、その他業務に就かせることは禁じられています。
このほかにも、外国人労働者に接待を行わせることも、特定技能の趣旨に反するとして認められていません。
具体的には顧客との飲食やカラオケでの同席などが挙げられます。
これらの事項に抵触する可能性がある場合には、出入国在留管理庁に事前に問い合わせ、特定技能の対象となる業種・業務なのか判断してもらうのが賢明です。
ステップ②人材募集・面接を実施する
自社が特定技能「外食業」の対象となることが確認できたら、外国人労働者の採用に向けて人材募集を始めましょう。
人材募集を実施する際には、日本人の採用活動と同じように求人票を作成します。
ただし、一般的な求人票とは異なる部分があり、特定技能「外食業」により外国人労働者を雇用するための条件を満たした内容になるように記載しなければなりません。
また、詳しくは後述しますが、企業だけでなく外国人労働者自身にも、特定技能の資格を証明するための要件が設けられています。
書類選考や面接のときには、この要件をクリアしているのか否かを判別するために、証明書の提出を求めたり、書類を偽装していないかを確認したりする必要があります。
ステップ③雇用契約を結ぶ
採用したい人材が見つかったら、その外国人労働者とのあいだに雇用契約を締結します。
この雇用契約書の内容は、出入国在留管理庁によって定められているひな型に基づいた適切なものでなければなりません。
また、その表記は日本語とともに、内定者にとって理解できる言語で書かれていることも大切なポイントです。
というのも作成された雇用契約書は、のちの在留資格の申請時に使用するためです。
不備があった場合には在留許可が下りないおそれがあるので、外国人労働者にきちんと内容をわかってもらえるように作成しましょう。
ステップ④支援計画書を策定する
在留資格の申請に向けて、支援計画書を作成していきます。
ここで、具体的な支援計画書の内容を確認してみましょう。
支援計画書に記載する必要がある支援の内容
- 事前のガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保、日常生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きなどへの同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談や苦情などの対応
- 日本人との交流機会の促進
- 企業側の都合による転職の際の支援
- 定期的な面談の実施
このように、受入れ企業には外国人労働者が安心して働けるよう、実務面だけにとどまらず全面的な支援を行うための支援計画書の作成・実行が求められます。
「自社のみの力でこうした環境の整備を行うのは難しい……」と思われたら、登録支援機関への委託も視野に入れておきたいところです。
ステップ⑤協議会に入会する
支援計画書が策定できたら、在留資格申請前の最終段階として、協議会に加入する必要があります。
以前は特定技能「外食業」により、外国人労働者を初めて雇用する際には、受入れから4か月以内に協議会へ加入すれば問題ありませんでした。
しかし、2024年6月15日以降、在留資格の申請前に加入することが義務づけられたのです。
協議会に加入する際には申請後に審査が設けられているため、結果が出るまでに1~2か月程度要します。
そのあいだに、在留資格の申請に必要な書類を集めておきましょう。
ステップ⑥在留資格申請を行う
協議会への加入が済んだら、いよいよ在留資格の申請に移ります。
在留資格を申請する際に必要な書類は多岐にわたりますが、その内容は“外国人労働者本人の書類”“受入れ企業の書類”“分野の書類”に大別可能です。
それぞれ必要な書類の詳細を、以下で表にまとめました。
在留資格の申請時に必要な書類
外国人労働者本人の書類 | ・在留資格認定証明書交付申請書 |
受入れ企業の書類 | ・特定技能所属機関概要書 |
分野の書類 | ・外食業特定技能1号技能測定試験の合格証の写し |
このように在留資格の申請には、膨大な書類の準備が必要になります。
ただし、こちらの申請作業も、支援計画書の策定と同様に委託することができます。
ステップ⑦外国人労働者の就労が始まる
在留資格の取得が無事完了したら、外国人労働者の就労がスタートします。
就労を始めるにあたって、必要であれば引っ越しや住居の手配のサポートを行いましょう。
また、雇用契約書で締結した内容を遵守することはもちろん、出入国在留管理庁やハローワークへの届出も忘れずに実施するように気をつけてください。
| 【飲食店&外食産業向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 即戦力として働ける特定技能外国人が、店舗運営をしっかりサポートします。 飲食業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |
特定技能「外食業」を取得する要件
受入れ企業は、雇用する外国人労働者を探すにあたり、特定技能「外食業」の要件を満たす人材かどうかをきちんと判別する必要があります。
そこで、当該外国人労働者が特定技能「外食業」の資格を取得するための要件も事前に確認しておきましょう。
特定技能「外食業」により、日本での就労を目指す外国人労働者は、以下の要件を満たさなければなりません。
特定技能「外食業」を取得する要件
- 18歳以上である
- 日本語能力試験(JLPT)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格している
- 外食業特定技能1号技能測定試験に合格している
合格が必要な2種類の試験について、概要を解説します。
日本語能力試験(JLPT)・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
外国人労働者は自身の語学力を証明するために、日本語能力試験(JLPT)、もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のいずれかの試験に合格しなければなりません。
それぞれの概要を以下にまとめました。
日本語能力試験と国際交流基金日本語基礎テストの概要
日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト | |
実施団体 | 国外:独立行政法人国際交流基金 国内:日本国際教育支援協会 | 独立行政法人国際交流基金 |
実施方式 | マークシート方式 | CBT方式 |
実施回数 | 年2回(7月・12月) | 複数回 |
日本語能力試験では、点数に応じて日本語の能力が5段階で表されます。
外国人労働者が特定技能「外食業」を取得するためには、2番目に高い基準である“N4(基本的な日本語を理解することができる)”に認定される必要があります。
一方の、国際交流基金日本語基礎テストは、その得点によって合否が決まる試験です。
総合得点が250点中200点以上であれば、合格となり、特定技能の要件を満たすことができます。
| 【動画でわかる】 外国人の日本語レベル JLPT(日本語能力試験)N1~N5レベルの外国人が、日本語を話している動画をまとめました。 「外国人採用を検討する予定がある」「募集条件の設定が必要」など、外国人の日本語レベルが分からない場合に活用いただける資料です。 |
外食業特定技能1号技能測定試験
外国人労働者の実務面の知識と技能を測るのが、外食業特定技能1号技能測定試験です。
外食業特定技能1号技能測定試験は、日本国内のほかに以下のアジア各国で実施されます。
外食業特定技能1号技能測定試験が実施される国
- フィリピン
- インドネシア
- ネパール
- ミャンマー
- カンボジア
- タイ
- スリランカ
1年を通して1月・6月・10月ごろの計3回開催されますが、国外の試験会場においては海外情勢の影響を受けて一部中止になる可能性があります。
語学力のテストは国際交流基金日本語基礎テストにより、比較的柔軟に受験できますが、外食業特定技能1号技能測定試験はいつでも受けられるわけではありません。
そのため外国人労働者は、合格に向けて計画的な学習が必要です。
以下で試験の内容についても、確認しておきましょう。
試験の内容
外食業特定技能1号技能測定試験の内容を、次の表にまとめました。
外食業特定技能1号技能測定試験
試験内容 | 詳細 |
学科 | 衛生管理: |
実技 | 判断する試験: |
同試験は、学科と実技の2つで構成されており、外食業に就労するうえで必要な知識全般を評価されます。
合格するには、学科と実技の合計で、満点の65%以上の点数をとる必要があります。
特定技能「外食業」による外国人労働者の雇用で人手不足を解消しよう
本記事では、特定技能「外食業」の概要や受入れ企業の要件を解説しました。
特定技能「外食業」は、日本国内の飲食業において、一定の専門性や技能を持つ外国人労働者を受け入れるための在留資格です。
食堂やレストラン、持ち帰り専門店など、幅広い業態での雇用が認められています。
受入れ企業は外国人労働者を雇用するために、支援の体制や計画を事前に整備し、雇用後はそれに従って日本での生活をサポートすることが求められます。
「支援環境をきちんと準備できるか不安」という担当者様は、スタッフ満足をご利用ください。
各国の言語・文化に精通したコーディネーターが、外国人労働者の受入れから定着までを徹底的にサポートいたします。
| 【飲食店&外食産業向け】 外国人採用 完全ガイド 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 即戦力として働ける特定技能外国人が、店舗運営をしっかりサポートします。 飲食業界に特化した採用方法・費用感がわかる資料をご案内しています。 |