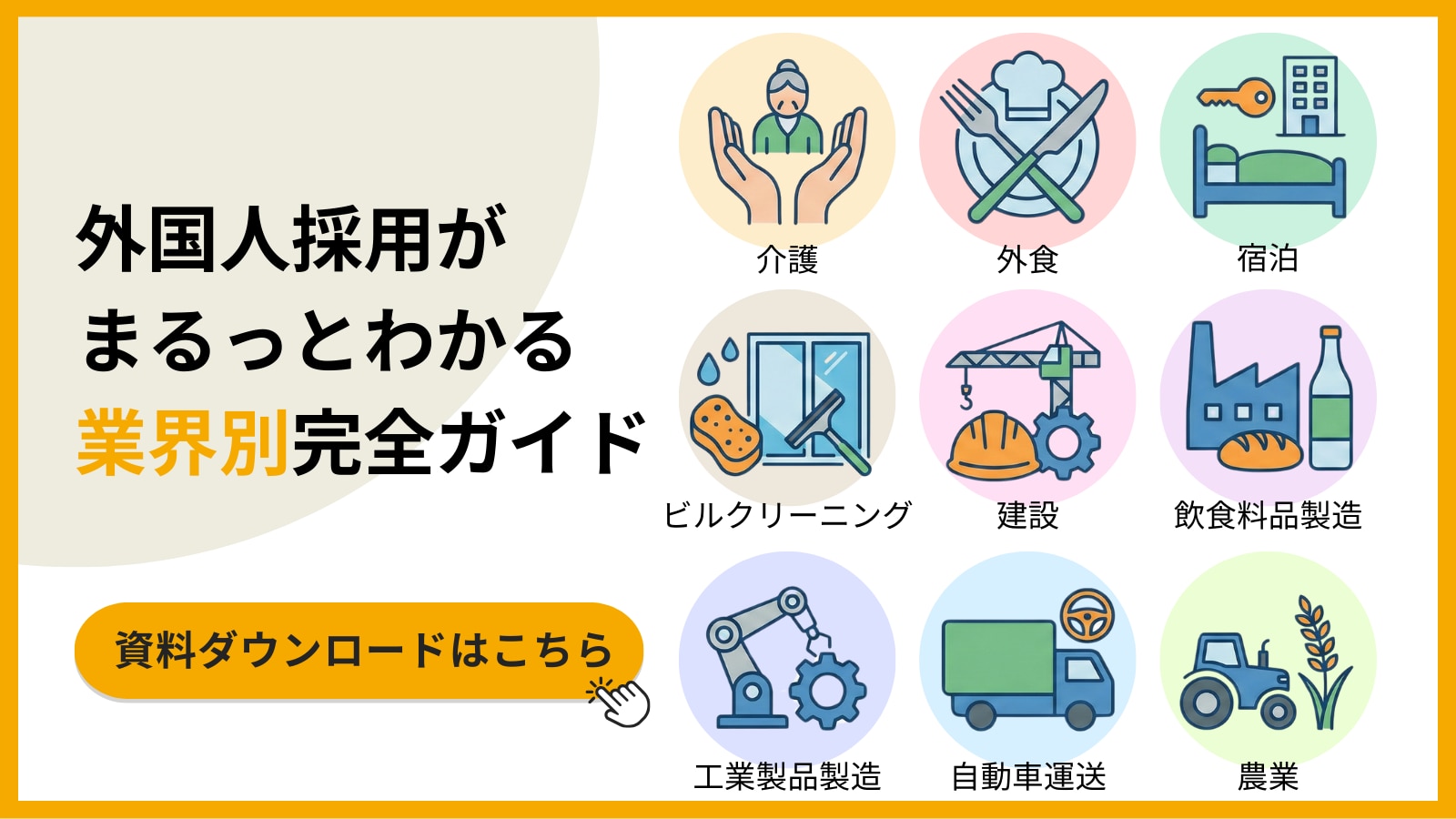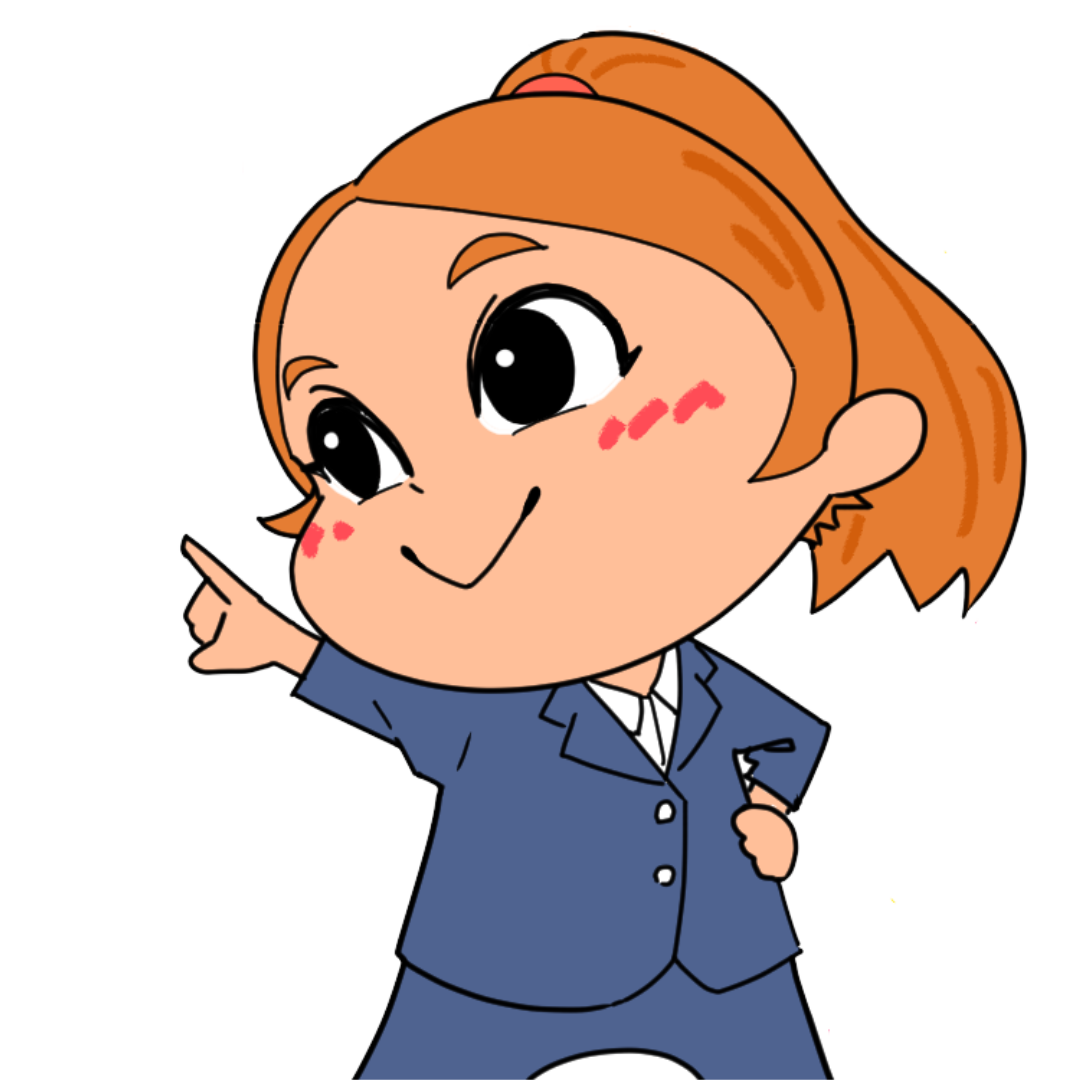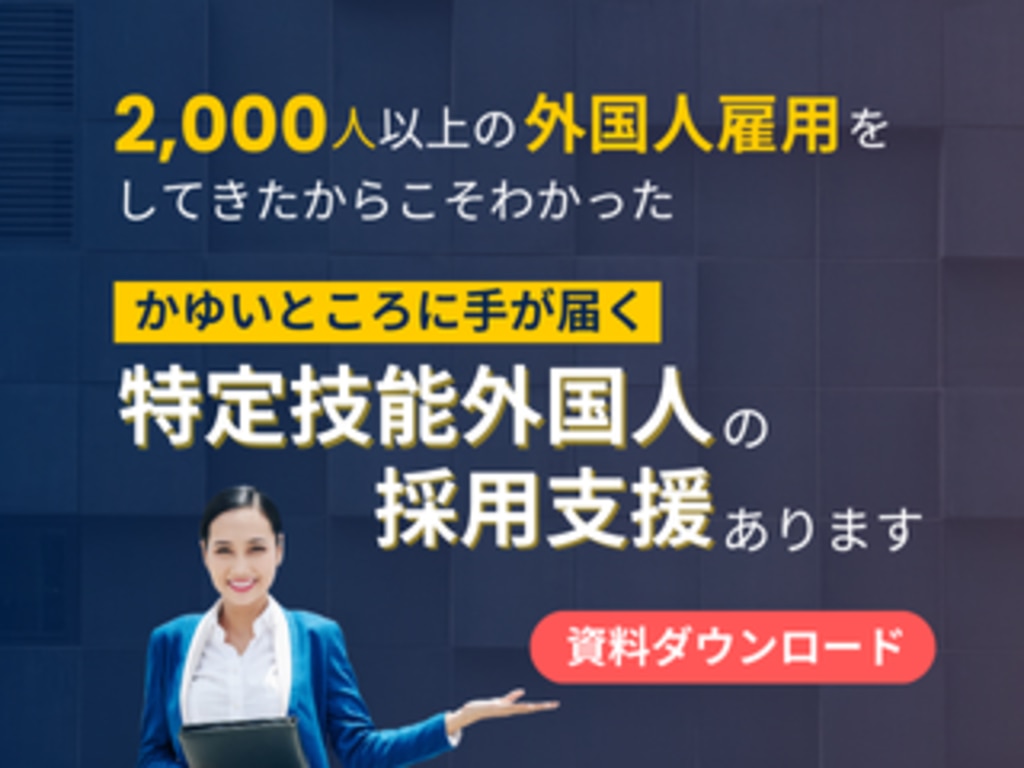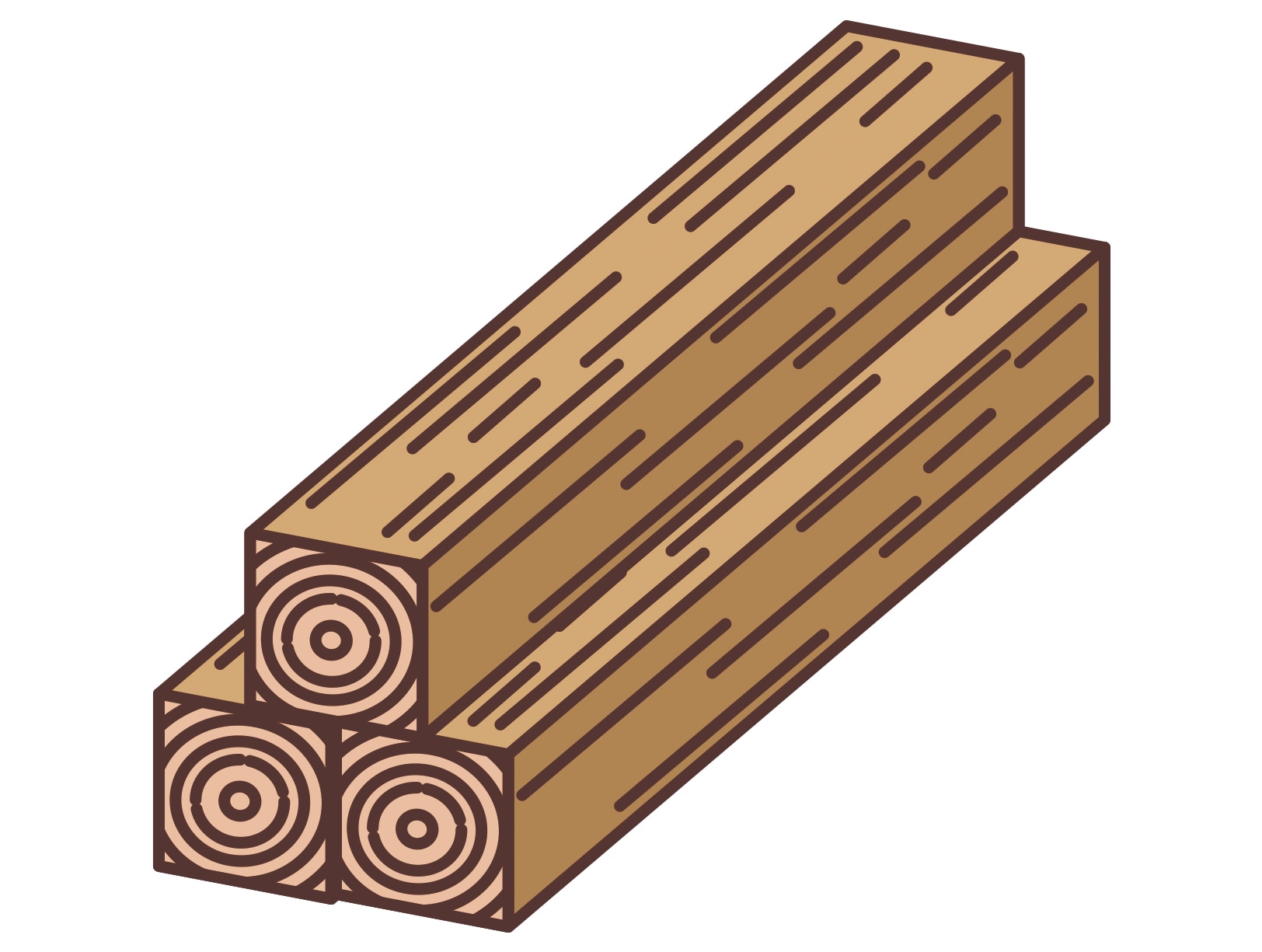
特定技能「木材産業」とは?雇用する場合の注意点とともに解説
特定技能とは、国内産業の人手不足を解消するため、一定の専門性・技能を保有する外国人を受け入れる制度のことです。
特定技能はさまざまな分野にも適用されていますが、今回は「木材産業」について紹介します。
有資格者を企業が受け入れるための要件や、外国人人材を雇用する際の注意点までを取り上げています。
木材産業分野で外国人を受け入れようと検討中の企業さまは、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
特定技能「木材産業」とは
特定技能「木材産業」とは、2024年3月に木材産業の人手不足解消に向けて追加された特定技能制度の領域の一つです。
特定技能は計16分野、1号・2号と分かれています。
1号に認定された人材は、日本語力と技術を磨いて2号を取得するのが一般的です。
しかし、特定技能「木材産業」ではまだ1号しか適用されないため、通算で最大5年しか雇えません。
特定技能1号で担当可能な業務は、製材業、合板製造業に係る木材の加工などです。
これに加えて、原材料の運搬・受け入れ、検査に関わる作業・清掃といった付随業務も任せられます。
木材産業の現状
法務省の「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」によると、木材産業の現状は次のようになっています。
【木製品製造業(家具を除く)の就業者数】
木製品製造業の就業者数は、平成22年の12万3,000人から令和2年には10万3,000人と、この10年間で約16%減少。
【35歳未満の就業者割合】
令和2年における35歳未満の就業者割合は、全産業で22.8%。
木材・木製品製造業(家具を除く)では17.6%。
木材産業業界の人手不足は、令和6年度から5年間で5万7,000人だと予測されています。
そのうち、外国人の受け入れ見込み数は5,000人が上限です。
木材産業は他の業種に比べて、労働災害の発生率が高い傾向にあります。
そのことから、就業者数が年々減少しているのです。
近年では、労働者の安全確保・業務量を軽減させるために以下の対策をしています。
|
誰でも働きやすい環境を整えることで、外国人人材の活躍が期待できます。
外国人人材を迎え入れることで「森林・林業基本計画」「花粉症対策の全体像」といったプロジェクトも円滑に進んでいくでしょう。
特定技能「木材産業」の受け入れ企業側の条件
特定技能「木材産業」を企業側が受け入れる際に必要な条件は5つあります。
|
引用元:法務省「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」 また、特定技能外国人の雇用形態は直接雇用のみとなっています。 これらの条件を満たしていなければ、違法雇用とみなされ処罰の対象になるおそれがあります。
特定技能「木材産業」の取得における要件
外国人人材が特定技能「木材産業」を取得するためには、2つの要件をクリアしなければいけません。
|
それぞれ詳しく解説します。
木材産業特定技能1号測定試験に合格する
木材産業特定技能1号測定試験とは、外国人人材が、木材産業分野に必要な知識・技能を保有していることを証明する試験です。
農林水産省が選定した機関で試験を実施します。
試験の詳細は後述しているため、ご確認ください。
日本語能力テストに合格する
特定技能「木材産業」を取得するには、外国人人材が生活に支障がない程度の日本語能力を保有している必要があります。
日本語能力を客観的に証明できる「日本語能力試験」「国際交流基金日本語基礎テスト」を受けましょう。
【日本語能力テストの詳細】
試験名 | 日本語能力試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト |
必要なレベル | N4以上 | A2相当のレベル |
レベルの詳細 | 基本的な日本語を理解できる | ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を保有している |
特定技能を取得するには、日本語能力試験ではN4以上、国際交流基金日本語基礎テストならA2相当のレベルが必要です。
技能実習2号を良好に修了している場合、木材産業特定技能1号測定試験・日本語能力テストを免除されるケースがあります。
特定技能「木材産業」の試験概要
特定技能「木材産業」を取得するには、木材産業特定技能1号測定試験を受ける必要があります。
【木材産業特定技能1号測定試験の詳細】
技能水準 | 木材加工、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また各種作業について、安全の確保を図りつつ一定時間内に正しい手順で的確にできるレベルであること |
言語 | 日本語(ひらがな、カタカナ、漢字ふりがな付き) |
問題数 | 35問(学科試験:32問、実技試験:3問) |
試験時間 | 60分 |
合格基準 | 学科・実技試験の合計得点の65%以上 |
実施方法 | CBT方式、ペーパーテスト方式 |
引用元:農林水産省「木材産業特定技能1号測定試験実施要領」
次回の試験開催日は以下のとおりです。
|
2024年12月時点で国外試験の開催日程は林野庁のホームページをご確認ください。
特定技能外国人を受け入れるまでの流れ
特定技能外国人を受け入れるまでには、次のような手順が必要です。
|
外国人人材を募集する際は、国内か国外かによって必要な手続きが異なります。
では、それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ① 受け入れ要件を確認する
給与や支給時期、各種手当・福利厚生など、求人を募集する前に外国人人材の受け入れ要件を決定しましょう。
また特定技能外国人が日本で快適に過ごせるようなサポートも必要です。
例えば日本語教育支援や、日本人スタッフが外国文化を把握していると円滑に受け入れられるでしょう。
ステップ② 人材募集・面接を実施する
特定技能外国人を募集する際の方法はさまざまです。
ですが、初めて外国人人材を募集する場合は人材紹介会社、または現地の機関を利用するのがおすすめです。
外国人人材の雇用に関するノウハウを保有しているため、スムーズに手続きが進むでしょう。
外国人人材から応募があれば面接を実施します。
面接の際はシンプルな日本語を活用したり、通訳を利用したりすることでお互いのミスマッチを避けられるでしょう。
ステップ③ 雇用契約を締結する
面接を経て雇用すると決定したら、特定技能雇用契約書を作成し、雇用契約を締結しましょう。
契約書を作成する際には、日本語だけでなく外国人人材の母国語で記載するのが一般的です。
また待遇面や一時帰国する際の有休消化の扱いをどうするかなどの項目も記載しなければいけません。
記載事項が多いため、抜け漏れがないか確認することが大切です。
ステップ④ 在留資格の申請をする
国内在住の外国人人材を雇用する場合は「ビザ変更申請」、海外在住の人材を雇用する場合は「ビザ認定申請」が必要です。
国内在住の外国人人材が保有するビザが、技能実習生や留学の場合は「在留資格変更証明書交付申請」を行います。
海外に住んでおり、日本の在留資格を保有していない外国人人材は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
特定技能「木材産業」の必要書類は2024年12月時点で詳細が決まっておらず、今後、必要書類が増える可能性があります。
特定技能「木材産業」の外国人を雇用する場合の注意点
特定技能「木材産業」の外国人を雇用する場合の注意点は5つあります。
|
それぞれ解説します。
木材産業特定技能競技会に加入する
特定技能「木材産業」の外国人を雇用予定なら、受け入れ企業は「木材産業特定技能競技会」に加入する必要があります。
木材産業特定技能競技会とは、農林水産省が外国人人材の適切な受け入れ・保護を目的として設立した機関です。
構成員になった後は以下のような協力が求められます。
|
雇用できる形態は正社員のみに限られる
前述でも記載したとおり、特定技能「木材産業」の人材は正社員雇用のみに限られます。
外国人人材を国内で雇用する際の条件・待遇は、日本人スタッフと同様でなければいけません。
労働基準法が適用されるためです。
法律を遵守し、外国人人材が働きやすい環境を整えましょう。
定められた範囲内での業務に従事させる
特定技能外国人の対応可能な業務には以下のとおり、限りがあります。
|
この業務以外を外国人人材に対応させると、実施させた企業が処罰の対象となるので気をつけましょう。
業務に円滑に取り組めるようにサポートする
外国人人材が業務を円滑に進められるよう、次のようなサポートが必要です。
|
これらの支援をすることで、外国人人材がスムーズに作業できるでしょう。
労働面と生活面のサポート体制を整える
旅行で日本を訪れたことはあるけれど、日本に住んだことがある外国人人材は少ないでしょう。
日本の文化・暮らしに慣れるために生活面でのサポートが必要です。
特に、以下の生活に関するサポートは企業の義務です。
|
リソースがないなどの理由で、自社で上記の支援が難しい場合は「登録支援機関」に委託すると良いでしょう。
登録支援機関とは、外国人人材の雇用に必要な手続き・サポート業務を代行する機関のことです。
スタッフ満足では、住居確保を始めとする生活支援から行政への定期報告まで対応可能です。
ご興味がある企業さまは、ぜひお問い合わせください。
まとめ
外国人人材を雇用するまでにさまざまな手続きが必要です。
外国人雇用に関するノウハウがなければ、特定技能外国人を受け入れ、業務を任せるまでに時間がかかるでしょう。
外国人人材の生活支援などの手続きは、登録支援機関に委託できます。
スタッフ満足では人材紹介から、手間のかかる手続きや採用後の特定技能外国人への対応まで、採用に関わる業務を一気通貫で引き受けることができます。
特定技能外国人の採用をご検討の企業さまは、お気軽にお問い合わせください。