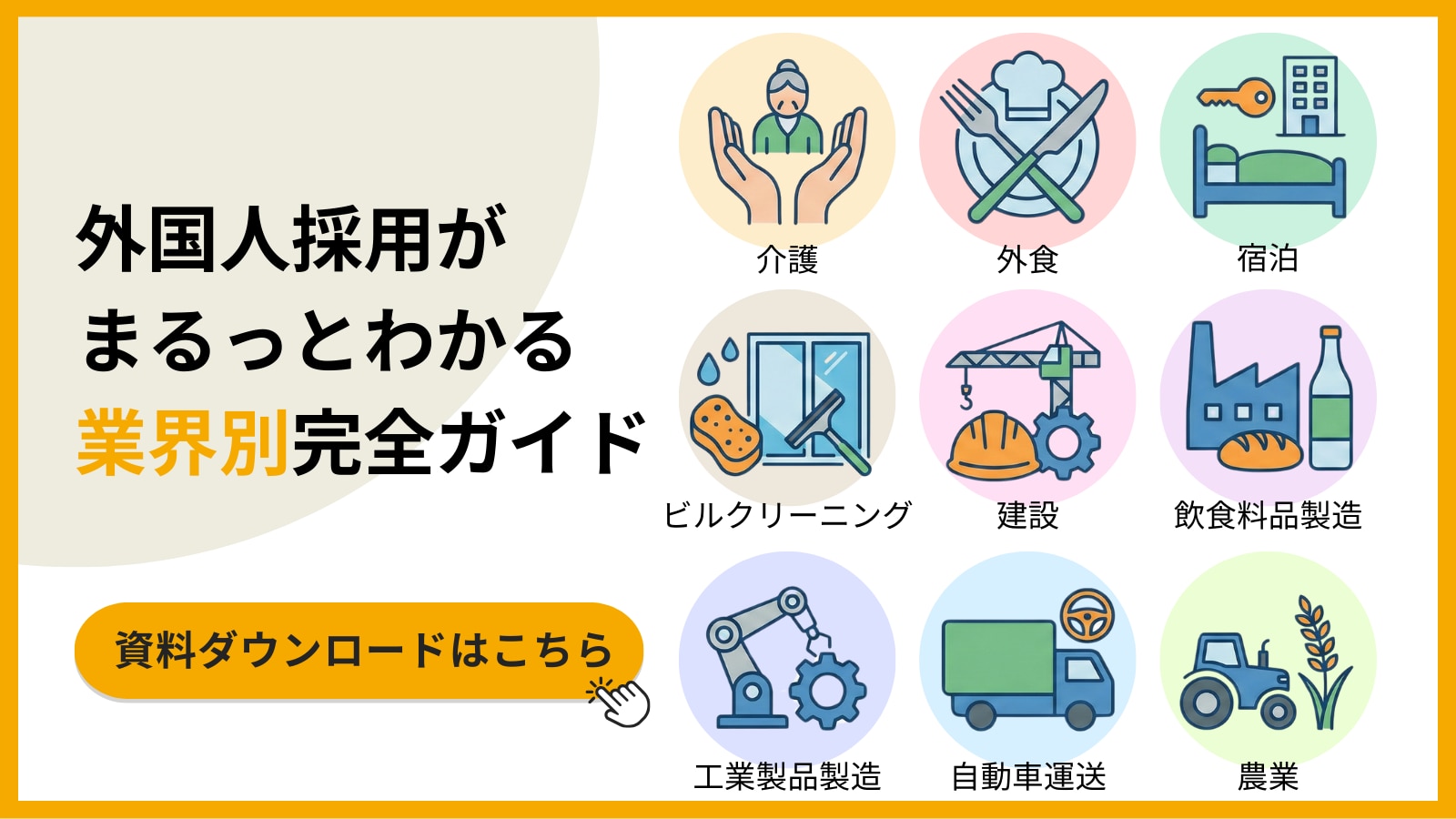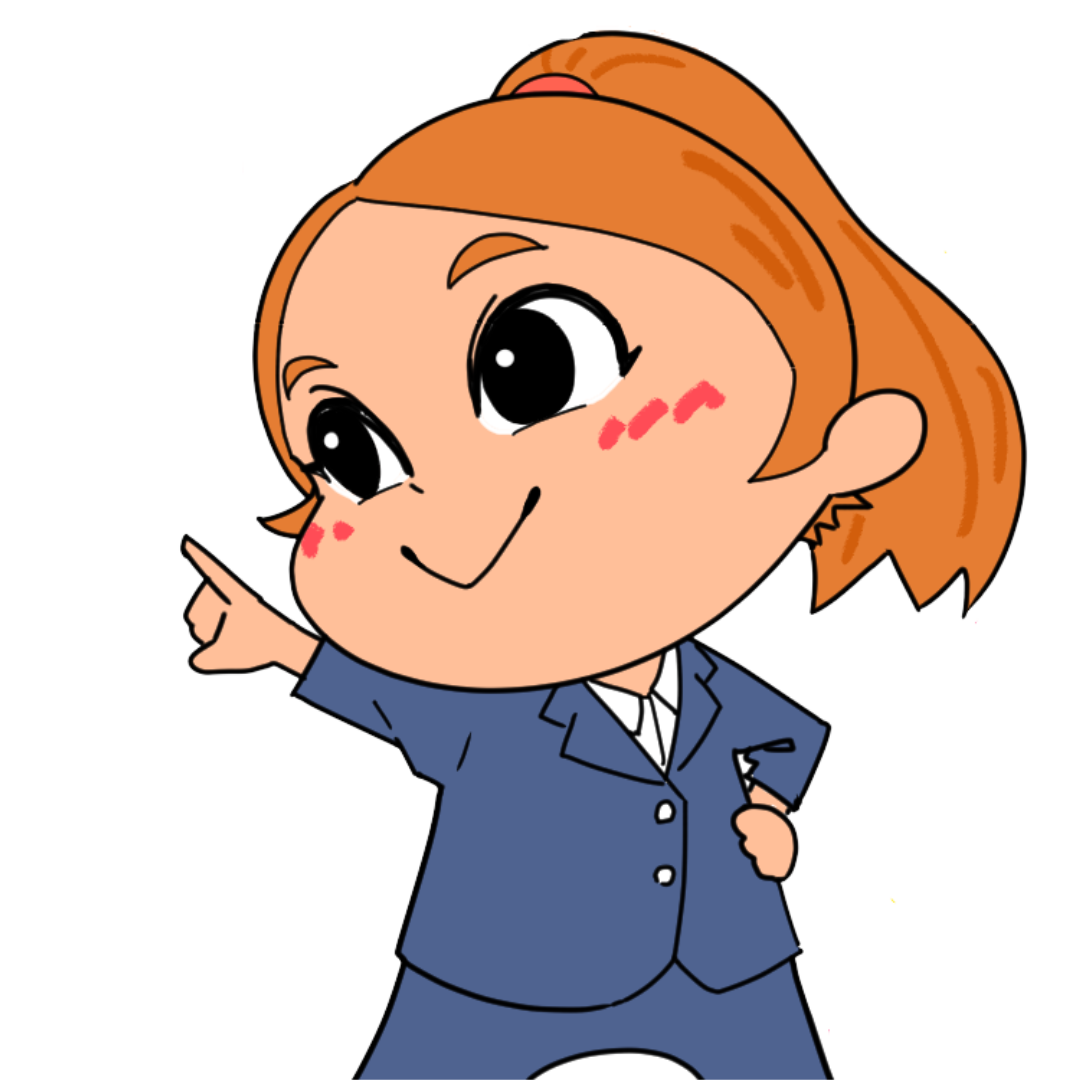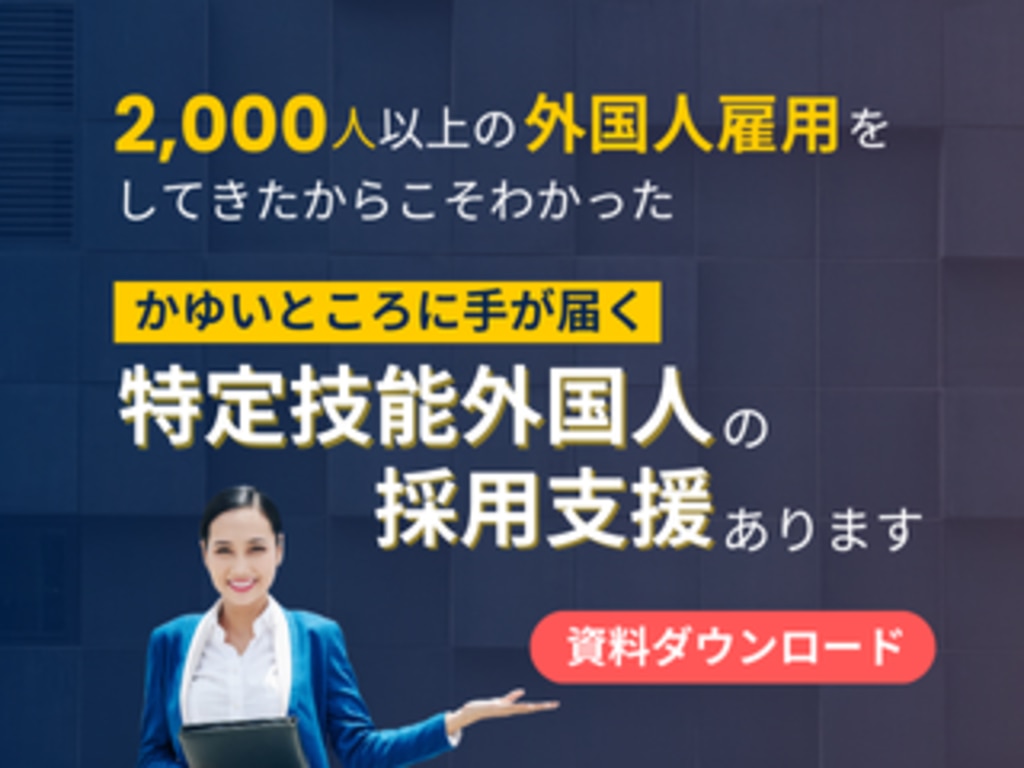在留資格の「技術・人文知識・国際業務 」とは?要件を解説
外国人材の採用を検討する企業が増える中、在留資格の技術・人文知識・国際業務に注目が集まっています。
しかし、要件や申請手続きに関する知識がなく、在留資格の選択に悩む企業は珍しくありません。
技術・人文知識・国際業務は、高度な専門性を持つ外国人材の受け入れに適した在留資格です。
とはいえ、業務内容や学歴との関連性など、細かな規定があります。
採用を成功させるためには、対象人材の条件や従事可能な業務内容を正しく理解しなければいけません。
本記事では、在留資格の技術・人文知識・国際業務の基本から申請要件、具体的な職種、申請手続きの方法までを詳しく解説します。
外国人材の採用を確実に進めたい人事担当者は、ぜひ最後までお読みください。
|
【完全ガイド】 就労ビザに関する内容をまとめた資料です。 日本で働くことができる在留資格の概要をまとめておりますので、外国人雇用を検討する際の確認資料としてお使いいただけます。 |
目次[非表示]
- 1.在留資格の「技術・人文知識・国際業務」とは
- 2.「技術・人文知識・国際業務」で就労できる業務
- 3.「技術・人文知識・国際業務」で就労可能な職種一覧
- 4.「技術・人文知識・国際業務」を申請するための要件
- 4.1.学歴(職歴)と業務内容の関連性
- 4.2.学歴
- 4.3.受け入れ企業の経営状態
- 4.4.給与水準
- 5.「技術・人文知識・国際業務」の申請方法
- 5.1.海外で採用して日本に招く場合
- 5.2.日本にいる外国人を採用する場合
- 5.3.日本で働いていた外国人を採用する場合
- 6.「技術・人文知識・国際業務」の外国人を採用する際の注意点
- 6.1.注意点①資格外活動許可が必要なケースがある
- 6.2.注意点②業務内容が在留資格に合っているか確認する
- 6.3.注意点③在留期間の更新時期に気をつける
- 6.4.注意点④単純労働はさせられない
- 6.5.注意点⑤学歴(職歴)と業務内容の関連性は必須である
- 7.まとめ
在留資格の「技術・人文知識・国際業務」とは
在留資格の技術・人文知識・国際業務は、高度な専門性を持つ外国人材が日本国内で就労するために必要な資格です。
2021年10月時点で存在する29種類の在留資格のひとつで、一般的には技人国と略して呼ばれています。
主な目的は、外国人が母国で培った専門知識や技術を日本企業で活かすことです。
対象となる分野は幅広く、大きく分けると3つに集約できます。
|
在留資格の特徴は、職務内容や生活状況の変化に応じて他の資格への切り替えができる点です。
例えば、日本語学校で学ぶ留学生が卒業後に日本企業に就職する際や、技能実習生が高度な業務に従事する場合にも活用できます。
また、一定の要件を満たせば家族の帯同も認められるため、長期的なキャリア形成を視野に入れた外国人材にとっては魅力的な資格です。
「技術・人文知識・国際業務」で就労できる業務
在留資格の技術・人文知識・国際業務では、専門知識や技術を必要とする業務のみ、就労が許可されています。
具体的には、以下のような業務です。
|
在留資格の下で働く外国人は、企業との雇用契約に基づいた活動が前提です。
単純作業や反復的な業務は、認められません。
例えば、工場でのライン作業や飲食店での一般的な接客などは、従事できない業務です。
また、高度な技術に見える業務でも、訓練で習得可能な業務は対象外となる可能性があります。
従事できる業務の判断基準は、外国人の学歴や職歴と業務内容に関連性があり、専門知識を活かせる職務かどうかです。
企業側は、採用する時に業務内容が在留資格の要件と合致しているか慎重に確認する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」で就労可能な職種一覧
技術・人文知識・国際業務で就労可能な職種は、それぞれ多岐にわたります。
採用にあたっては、各職種で必要とされる専門性の水準や、業務内容の詳細を把握しておきましょう。
技術
技術分野での就労は、自然科学に基づく専門知識と技術が求められます。
主にIT・機械・電気電子・建築などの領域で活躍できる人材が対象です。
就労可能な職種の例は以下のとおりです。
|
近年はデジタルトランスフォーメーションの進展に伴い、IT関連の技術者需要が高まっています。
採用する際は、大学や専門学校での専攻内容と実際の業務内容の関連性に注目しましょう。
また、技術の進歩が速い分野のため、学習の継続や技術の更新も求められます。
企業側は外国人材の技術力を正確に評価し、適切な配置を検討しなければいけません。
人文知識
人文知識の分野は、社会科学的な専門知識を活用する3つの業界が中心です。
|
この分野での就労には、体系的な専門教育を受けている必要があります。
一般的には、大学の専攻との直接的な関連性が注目すべきポイントです。
人文知識分野で認められる主な職種は、10種類あります。
|
特に期待されているのは、企業の管理部門や専門的なコンサルティング業務です。
近年ではグローバルビジネスの展開に伴い、国際的な知識や経験を持つ人材の需要も増加しています。
国際業務
国際業務の分野では、外国の文化や言語に関する理解と専門知識を活かした職種が対象です。
母国の文化や言語を活用しながら、日本企業のグローバル展開をサポートできる人材が求められています。
就労可能な職種は、以下の通りです。
|
主に海外との取引やインバウンド需要への対応に欠かせない役割を果たします。
また、異文化コミュニケーションのスキルや、両国の商習慣に関する理解も重視されるのが特徴です。
企業側は外国人の言語能力だけでなく、ビジネスにおける実践的なコミュニケーション能力も評価する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」を申請するための要件
技術・人文知識・国際業務を申請するための要件は、4つあります。
|
これらの要件の目的は外国人材の安定した就労環境を確保と、専門的な能力の適切な活用です。
学歴(職歴)と業務内容の関連性
申請する際は外国人材の学歴または職歴と、従事予定の業務内容との間に明確な関連性がなければいけません。
例えば、情報工学を専攻した人がシステムエンジニアとして働く場合や、経済学を学んだ人が財務部門で働く場合です。
学歴(職歴)と業務内容の関連性は、大学や専門学校での専攻科目と業務内容を照らし合わせて判断されます。
直接的な関連性がない場合でも、十分な実務経験と証明があれば、要件を満たせます。
また、関連性の判断が難しい場合は、業務内容の詳細や必要とされる専門知識に関する具体的な資料の提出が必要です。
審査では資料に基づき、総合的な判断が行われます。
学歴
学歴要件は日本もしくは母国の大学を卒業、または日本の専門学校を卒業していることです。
海外の大学を卒業している場合は、学歴が日本の大学卒業と同等以上か証明する必要があります。
ただし、学歴要件を満たさない場合でも、技術・人文知識分野では10年以上、国際業務分野では3年以上の実務経験があれば申請できます。
また、2024年2月末からの新制度により、特別な認定を受けた専門学校の卒業生に関しては、業務内容との関連性について柔軟な判断が行われるようになりました。
これにより、従来よりも幅広い分野で就労できる機会が開かれています。
受け入れ企業の経営状態
受け入れ企業の経営状態は、外国人材の安定した雇用を保証する観点から重要な審査項目です。
企業には適切な事業実績と健全な財務状況が求められ、債務超過の有無が重視されます。
審査では、決算書類や事業計画書などの提出が必要です。
収支状況や今後の事業見通しが、チェックされます。
また、企業の規模に応じた適切な雇用体制が整っているかも判断材料です。
例えば、売上高や従業員数に対して適正な人数の外国人材を雇用しているか、適切な労働環境が整備されているかなどが審査されます。
業績が不振な場合では、改善に向けた具体的な計画の有無と、それが実現可能かどうかが判断されます。
特に問題がなければ、申請は認められるでしょう。
新規設立の企業の場合は、事業計画や資金計画の提出が求められます。
審査で重視されるのは、事業の継続性や安定性です。
給与水準
給与水準に関する要件は、日本人従業員と同等以上の待遇の確保です。
外国人労働者の権利を保護し、適正な労働条件を確保するために設けられた基準です。
具体的には、同じ職務に従事する日本人従業員の給与水準と比較して、同等またはそれ以上の給与を支払う必要があります。
基本給だけでなく、各種手当や賞与なども含めた総支給額で判断しなければいけません。
また、採用時の給与水準だけでなく、昇給や昇格の機会も、日本人従業員と同等の条件が求められます。
新卒採用の場合は、同期入社の日本人従業員との給与比較が厳密に行われるのが一般的です。
給与水準が基準を下回る場合は、理由を合理的に説明する必要があります。
説明が不十分だと、申請が下りない可能性が高まるでしょう。
「技術・人文知識・国際業務」の申請方法
技術・人文知識・国際業務の申請方法は、状況によって異なります。
|
該当する申請の流れを把握して、スムーズな就労を実現させましょう。
海外で採用して日本に招く場合
|
海外から外国人材を直接採用する場合は、まず在留資格認定証明書の取得から始める必要があります。
証明書は、外国人が在留資格の要件を満たしている証明を行う重要書類です。
申請は原則として受け入れ企業が行い、必要書類の準備から申請手続きまでを担当します。
準備する書類は、以下の6点です。
|
審査期間は通常1〜2ヶ月程度ですが、書類の不備がある場合はさらに時間がかかる可能性があります。
証明書が交付されたら外国人本人に送付し、本人が自国の日本大使館でビザを申請する流れです。
日本にいる外国人を採用する場合
|
日本国内にいる外国人(留学生も含む)を採用する場合は、在留資格変更許可申請を済ませる必要があります。
この手続きは、現在の在留資格から技術・人文知識・国際業務への切り替えが目的です。
申請は原則として外国人本人が行いますが、企業側も必要な書類の準備や手続きのサポートが求められます。
提出が必要になる主な書類は、4点です。
|
留学生の場合は、上記に加えて成績証明書や出席率などの資料も必要です。
また、アルバイト経験のある場合は、資格外活動許可の範囲内で働いていた証明も必要になるでしょう。
審査では、学業成績や就学態度なども考慮されるため、留学中の学習状況が申請の可否に影響を与える可能性があります。
日本で働いていた外国人を採用する場合
|
すでに日本国内で就労している外国人を採用する場合は、現在の在留資格や業務内容によって必要な手続きが異なります。
基本的には就労資格証明書の交付申請から始まりますが、在留資格の変更が必要になる可能性も考慮しておくべきでしょう。
申請の際は新たな雇用契約書に加えて、前職での在留カードや就労証明書が必要です。
また、これまでの在留期間中の活動実績や、新しい業務との関連性を示す資料も求められます。
注意すべきポイントは、前職と新しい職場での業務内容の整合性です。
大きく異なる業務に変更する場合は、妥当性について的確に説明する必要があります。
転職に伴う在留期間の更新時期が近い場合は、更新手続きと併せて検討すべきです。
企業側は、一連の手続きがスムーズに進むよう、情報提供や書類準備のサポートを行いましょう。
「技術・人文知識・国際業務」の外国人を採用する際の注意点
技術・人文知識・国際業務の外国人を採用する際の注意点は、5つあります。
|
スムーズな採用を実現するために、それぞれの注意点を把握しておきましょう。
注意点①資格外活動許可が必要なケースがある
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人は、副業やアルバイトを行う可能性があります。
ケースによっては、資格外活動許可の取得が必要になるでしょう。
許可申請は本人が入国管理局で行い、副業の具体的な内容や労働時間を明示しなければいけません。
また、単純労働は資格外活動として認められないため、本来の業務に支障をきたさない範囲で許可されます。
企業側は外国人社員の副業状況を適切に把握し、管理する必要があります。
注意点②業務内容が在留資格に合っているか確認する
採用時や人事異動の際は、業務内容が在留資格の要件と合致しているかの確認が必要です。
特に、データ入力などの定型業務や、専門知識を必要としない作業が主体となる配置転換は避けなければなりません。
業務内容の変更を検討する際は、外国人材の専門性が活かせる職務を提供しましょう。
不明な点がある場合は、事前に入国管理局に相談すべきです。
注意点③在留期間の更新時期に気をつける
在留期間の更新手続きは、期限切れの3ヶ月前から申請できます。
更新申請を行う際は、これまでの業務実績や今後の就労計画などの資料が必要です。
更新時期を見過ごすと不法滞在となるほか、企業も処罰の対象となる可能性があります。
したがって、期限管理は徹底しましょう。
特に、更新時期が人事異動や契約更新と重なる場合は、余裕を持った対応が求められます。
注意点④単純労働はさせられない
技術・人文知識・国際業務の在留資格では、単純作業や反復的な業務への従事は認められません。
例えば、工場でのライン作業や一般的な接客業務、データ入力などの定型業務は対象外です。
新入社員研修などで一時的に現場作業を経験する場合も、事前に入国管理局への確認が必要です。
単純労働が必要な場合は、特定技能など別の在留資格の検討が望ましいでしょう。
注意点⑤学歴(職歴)と業務内容の関連性は必須である
在留資格を申請を行う上で重要なのは、外国人材の学歴または職歴と、従事予定の業務内容との関連性です。
例えば、情報工学専攻者がシステムエンジニアとして働く場合のように、専門分野と業務が明確に結びつく必要があります。
関連性が認められないと、申請が不許可となる可能性が高いです。
したがって、採用段階では十分な確認を行う必要があります。
まとめ
在留資格の技術・人文知識・国際業務は、専門知識や技術を持つ外国人材の受け入れに適した資格です。
申請では学歴と業務の関連性、企業の受入体制、給与水準などの要件を満たす必要があります。
単純労働との区別や更新時期の管理などには、十分に注意しましょう。
申請手続きは、海外からの採用か国内採用かによって異なりますが、いずれの場合も必要書類の準備と期限管理が欠かせません。
また、採用後も在留期間の更新や業務内容の変更時には、在留資格の要件との整合性を確認する必要があります。
外国人材の採用を検討する企業は、これらの要件や手続きについて十分な理解を持ち、計画的な対応を心がけましょう。
不明な点がある場合は入国管理局や専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるべきです。
要件を満たした適切な採用と適切な管理を実現できれば、外国人材の能力を最大限に活かせます。
|
【完全ガイド】 就労ビザに関する内容をまとめた資料です。 日本で働くことができる在留資格の概要をまとめておりますので、外国人雇用を検討する際の確認資料としてお使いいただけます。 |