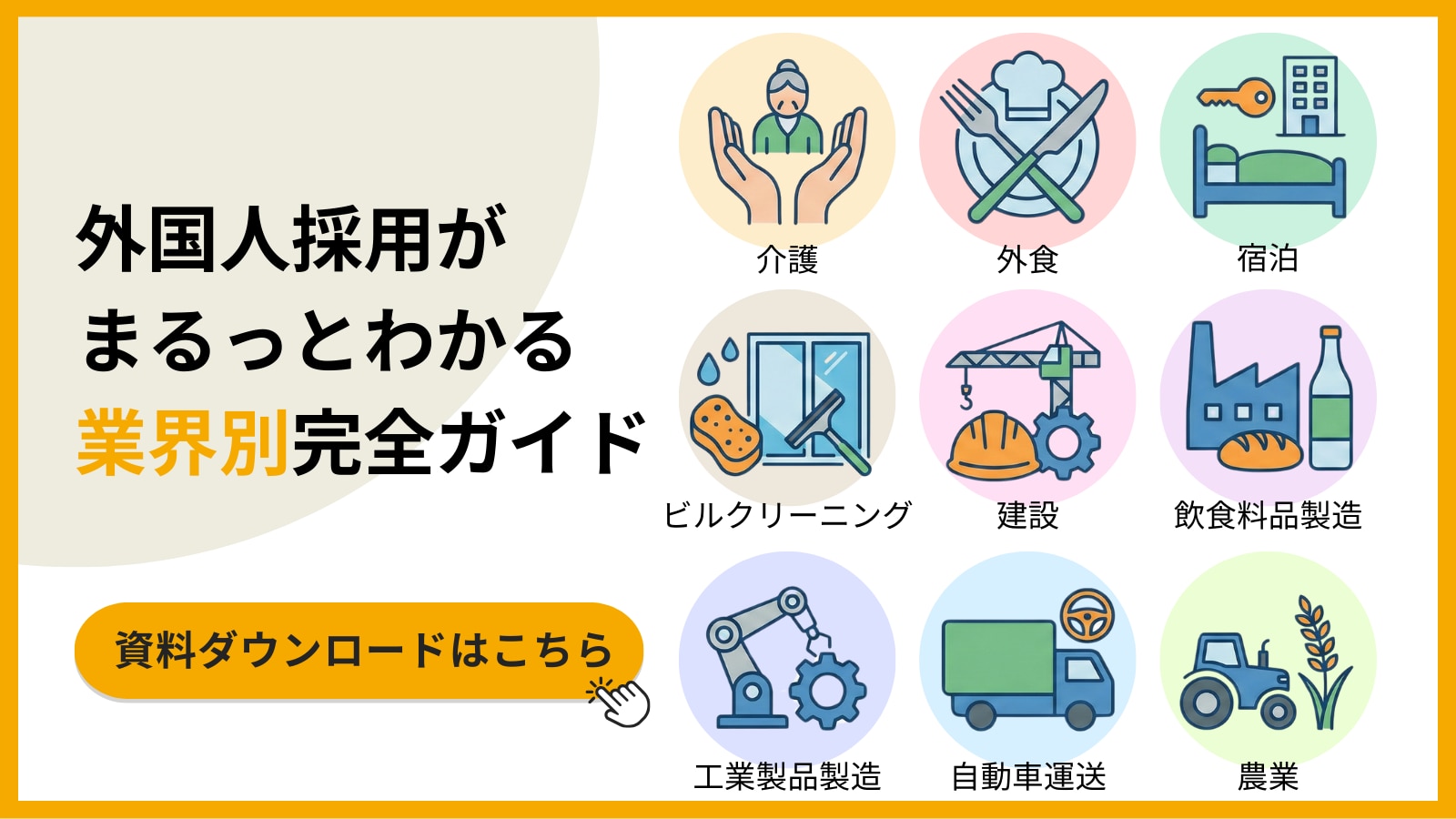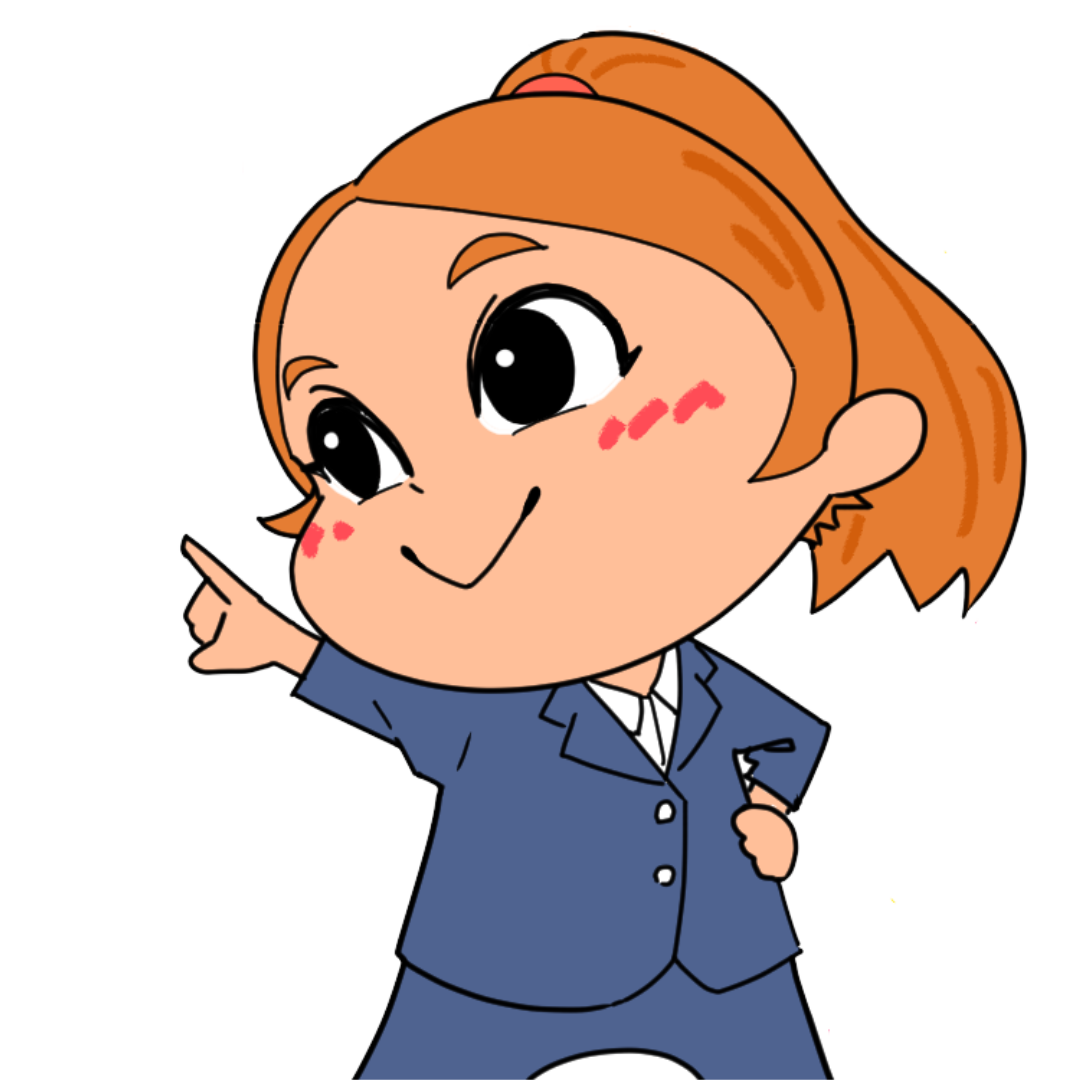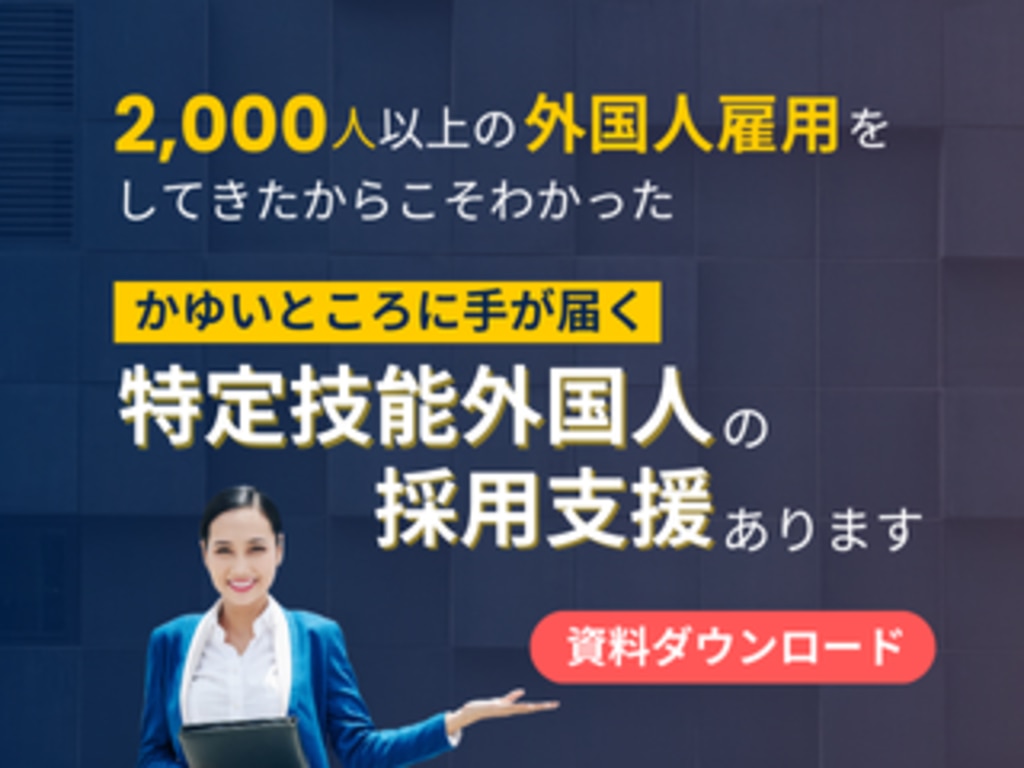特定技能を取得するための試験とは?試験内容を詳しく解説
厳しい人手不足を解消するため、外国人の採用を検討することもあるでしょう。
特に、専門的な知識や技術を要する分野では、特定技能を取得した外国人を採用する必要があります。
特定技能の試験に合格すれば、彼らの技能を把握できますが、どのような試験を受けているかご存じでしょうか?
そこで本記事では、特定技能の試験内容について解説します。
外国人の長期雇用を考えており、情報収集されている方は、ぜひご覧ください。
目次[非表示]
特定技能とは?
特定技能とは、特に人材不足が深刻な日本の産業分野において、外国人の採用が認められている在留資格のことです。
2019年に新設され、原則、正社員として雇用するのが条件です。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれ就労できる職種の数が異なります。
特定技能1号を有している場合は、「特定産業分野」に位置づけられている12分野での就労が可能です。
特定技能1号の12分野は、以下の通りです。
【外国人の受け入れが可能な12分野】
|
一方で、特定技能2号の対象は、2023年に2分野から11分野まで拡大され、上記のうち「介護」を除くすべての分野で就労が認められています。
対象分野の拡大を受け、今後は2号を取るために、まずは1号を取得して働きたいという外国人が増加するかもしれません。
また、2号は在留期間に上限がなく、条件を満たせば永住権の獲得や、家族帯同が認められる可能性があります。
そのため、人手不足に悩む企業にとっては、特定技能外国人を獲得するチャンスが広がるものの、分野によっては採用競争が激しくなることも予想されます。
関連記事:特定技能とは?採用方法や企業にとってのメリットを解説
特定技能取得に関する試験

特定技能を取得するには、「特定技能評価試験」の合格が必要です。
外国人が日本で働くにあたって、不可欠なスキルの有無を判定するために行いますが、彼らが実際にどのような試験を受けるのか、ご存じない方が多いかもしれません。
そこで、まず「特定技能1号」の試験内容を解説します。
なお、特定技能2号の試験内容については後述します。
日本語能力
特定技能1号評価試験には、日本語能力を測る「日本語能力試験(JLPT)」と「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」の2種類があります。
特定技能1号の取得にあたっては、このどちらかの試験に合格すればよいとされています。
なお、特定技能2号の取得要件には、日本語能力試験(JLPT)はありません。
日本での生活や業務では、日本語が欠かせませんから、この試験は外国人にとって重要な試験なのです。
それでは、日本語能力試験(JLPT)と、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)について詳しく見ていきましょう。
日本語能力試験(JLPT)
日本語能力試験(JLPT) とは、日本語を母国語としない外国人を対象に、日本語のレベルを測定・認定する語学検定試験のことです。
主催しているのは、国際交流基金と財団法人日本国際教育支援協会です。
試験では、日本語でコミュニケーションを取るために必要な「言語知識」「読解力」「聴解力」の3つが、どの程度備わっているのか総合的に判定されます。
認定レベルはN1~N5の5段階に分けられており、数字が小さいほど日本語の理解度が高いと見なされます。
以下の表に、日本語能力試験(JLPT)の認定の目安をまとめました。
【日本語能力試験(JLPT)の認定目安】
認定レベル | レベルの目安 |
N1 | 幅広い分野で使われる日本語を理解することができる |
N2 | 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる |
N3 | 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる |
N4 | 基本的な日本語を理解することができる |
N5 | 基本的な日本語をある程度理解することができる |
特定技能では、最低でもN4の認定が必要です。
仕事において、話す機会や難しい言葉を扱うことが多いケースや、自然かつ円滑なコミュニケーションを取る必要がある場合は、N1~N3の認定が求められます。
なお、日本語能力試験(JLPT)は、毎年7月上旬と12月上旬に行われます。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)
国際交流基金日本語能力基礎テスト(JFT)は、日本での生活に必要なコミュニケーション能力が備わっているかを測定する試験です。
試験は、「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4つで構成されています。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT )の認定レベルは、A1、A2、B1、B2、C1、C2の6段階です。
それぞれ「日本語で何ができるレベルか」が具体的に決められており、そのなかでも日本語でコミュニケーションが取れる方の目安は、大きく3段階に分けられています。
【国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)における認定レベル】
認定レベル | 日本語能力を有する方の目安 |
A1・A2 | 基礎段階の言語使用者 |
B1・B2 | 自立した言語使用者 |
C1・C2 | 熟達した言語使用者 |
参照元:レベルの目安(JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト-Japan Foundation)
特定技能1号を取得するには、A2以上のレベルが求められます。
A2は、日本の生活においてよく使われる文や表現の理解や、簡潔な言葉で説明できる程度の日本語能力を有しているレベルです。
また、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)のA2は、日本語能力試験(JLPT)のN4と同等のレベルだとされています。
技能試験
技能試験とは、各分野で就労するうえで欠かせない専門的な知識や、経験を調べるための試験のことです。
たとえば、宿泊業における技能試験では、実際の日本の旅館やホテルを想定した対応能力を判定するため、実務に即した業務が出題範囲です。
具体的には、「フロント」「レストラン」「接客」「広報・企画」「安全衛生その他の基本知識」の5つの業務に関する知識や技術を、学科・実技の2つの試験をもとに判定されます。
なお、特定技能1号の技能試験は、学科はペーパーテスト方式がほとんどですが、実技はペーパーテストや口頭試問、作業試験など、分野ごとに異なる方式で行われます。
技能試験は、分野や開催国によって異なりますが、11月に開催されることがほとんどです。
技能試験
一般社団法人 宿泊技能試験センター
受験資格
日本国内で特定技能の試験を受けられるのは、試験日において「満17歳以上」かつ「在留資格を有している」方です。
日本に滞在する期間に関わらず、在留資格をもっていれば受験できます。
また、技能実習2号を取得した場合は、特定技能の試験が免除されます。
技能実習2号とは、外国人ご自身の出身国での学習が困難な技術の習得や、熟達を図るための実習を日本で2年間行い、修了した際に得られる在留資格のことです。
この資格をもっていれば試験を受けずに、特定技能1号への移行が可能です。
ただし、特定技能の試験免除は、技能実習を良好に修了し、特定技能1号の分野と関連のある実習を行った場合のみとされています。
特定技能2号も試験が必要?

特定技能2号の取得には、該当の2号技能試験に合格することが必要です。
さらに、2号技能試験もしくは、技能検定の合格にくわえて、2~3年以上の実務経験も欠かせません。
特定技能2号の取得は、もともと特定技能1号取得者が2号試験に合格して移行することが条件でしたが、2023年秋からはそのほかの在留資格からでも移行が可能となりました。
ただし、1号から移行するあるいは、そのほかの在留資格をおもちの場合のいずれも、これまで通り試験の合格が必須です。
2号技能試験の内容は、ペーパーテスト方式ではない実技試験のみで行われます。
航空業を例に挙げると、特定技能2号の取得には、3年以上の実務経験と「航空分野特定技能2号評価試験」または「航空従事者技能検定」に合格することが条件です。
また、航空分野特定技能2号評価試験には、空港グランドハンドリング業務と、航空機整備業務の試験区分があり、試験内容も変わります。
このうち、「航空従事者技能検定」で特定技能2号を取得できるのは、航空機整備業務の試験のみです。
このように、特定技能2号の試験は、業務を極めるための技能試験が必須ですが、試験内容は分野ごとに異なります。
特定技能1号の取得には日本語能力と技能試験の両方の合格が必要!2号も技能試験の合格が必須
今回は、特定技能の試験内容について解説しました。
特定技能1号の取得には、日本語能力試験と技能試験の双方に合格することが必要です。
2号では、より熟練した技術が求められる技能試験の合格が不可欠です。
特定技能の1号と2号では、試験内容や習熟度などが異なるものの、資格を有した外国人を採用すれば、業務での活躍が期待できるでしょう。
スタッフ満足は、特定技能を取得した外国人の採用から定着までお手伝いする人材紹介サービスです。
累計1,000名以上の外国人の採用実績を活かしたサポートで、人材不足の解消を実現いたします。
試験内容についても不明点があればお答えしますので、ぜひ一度ご相談ください。