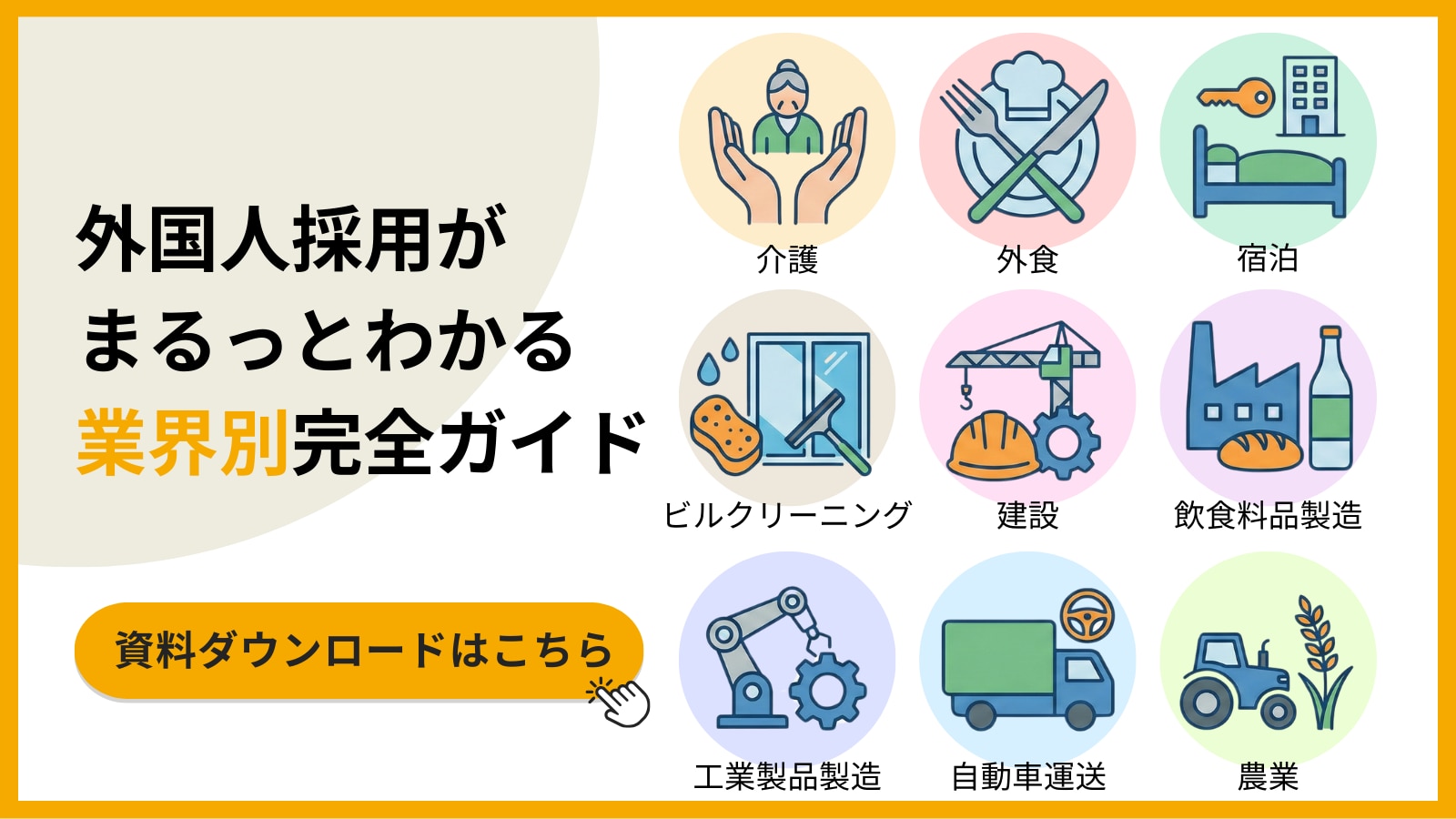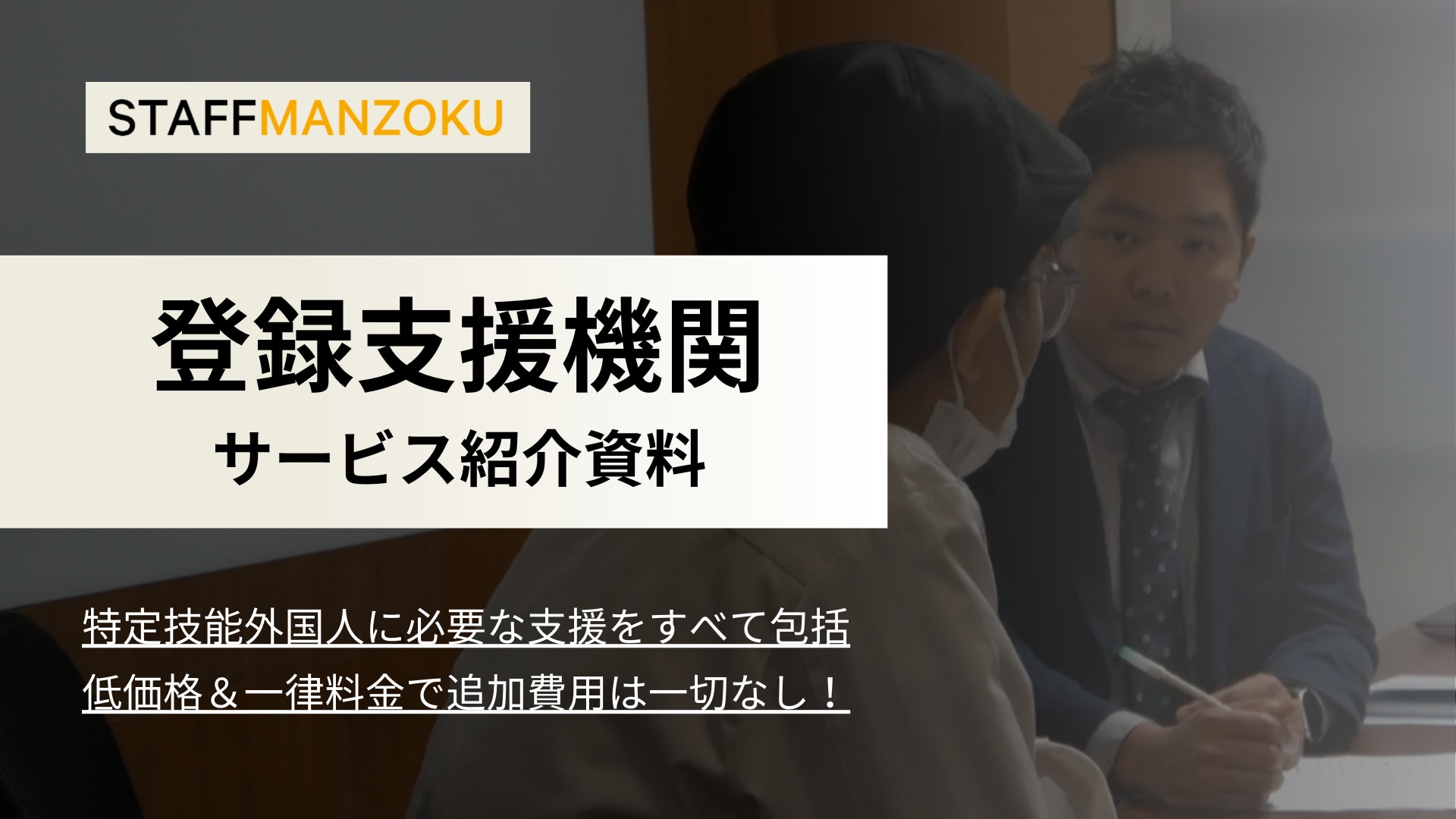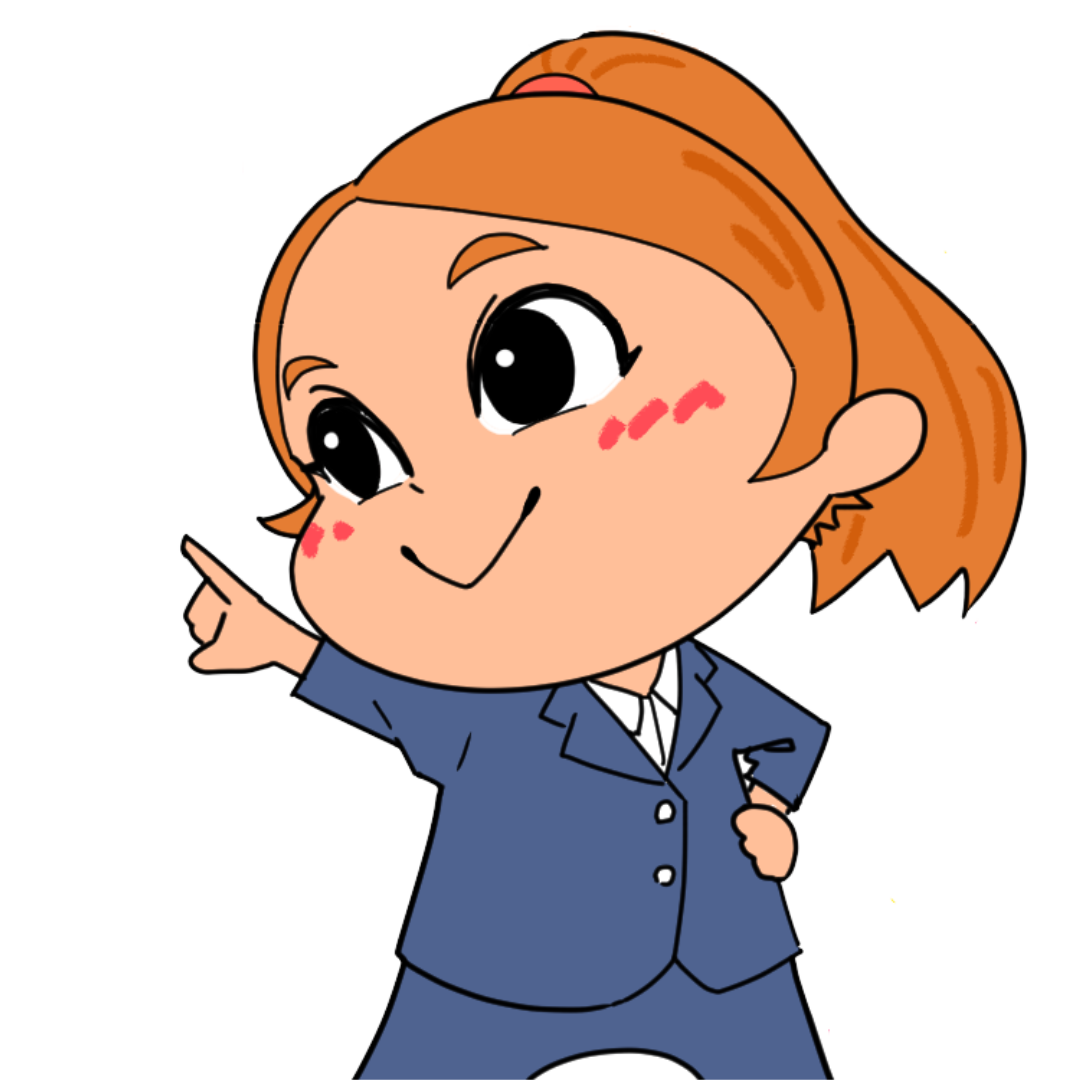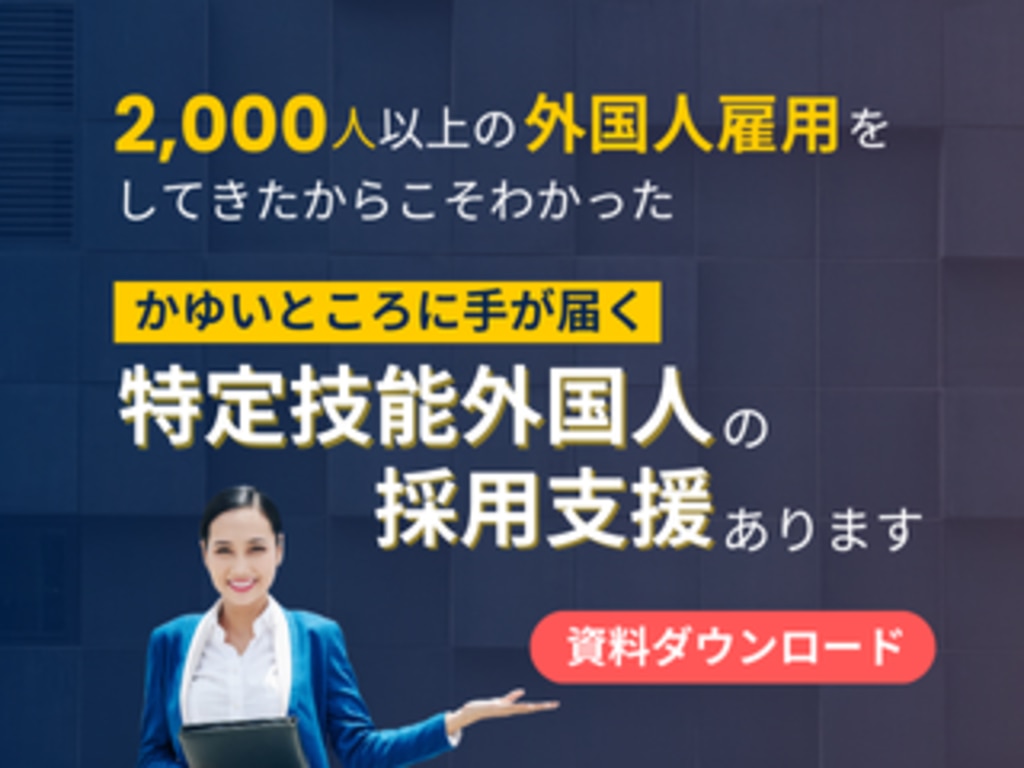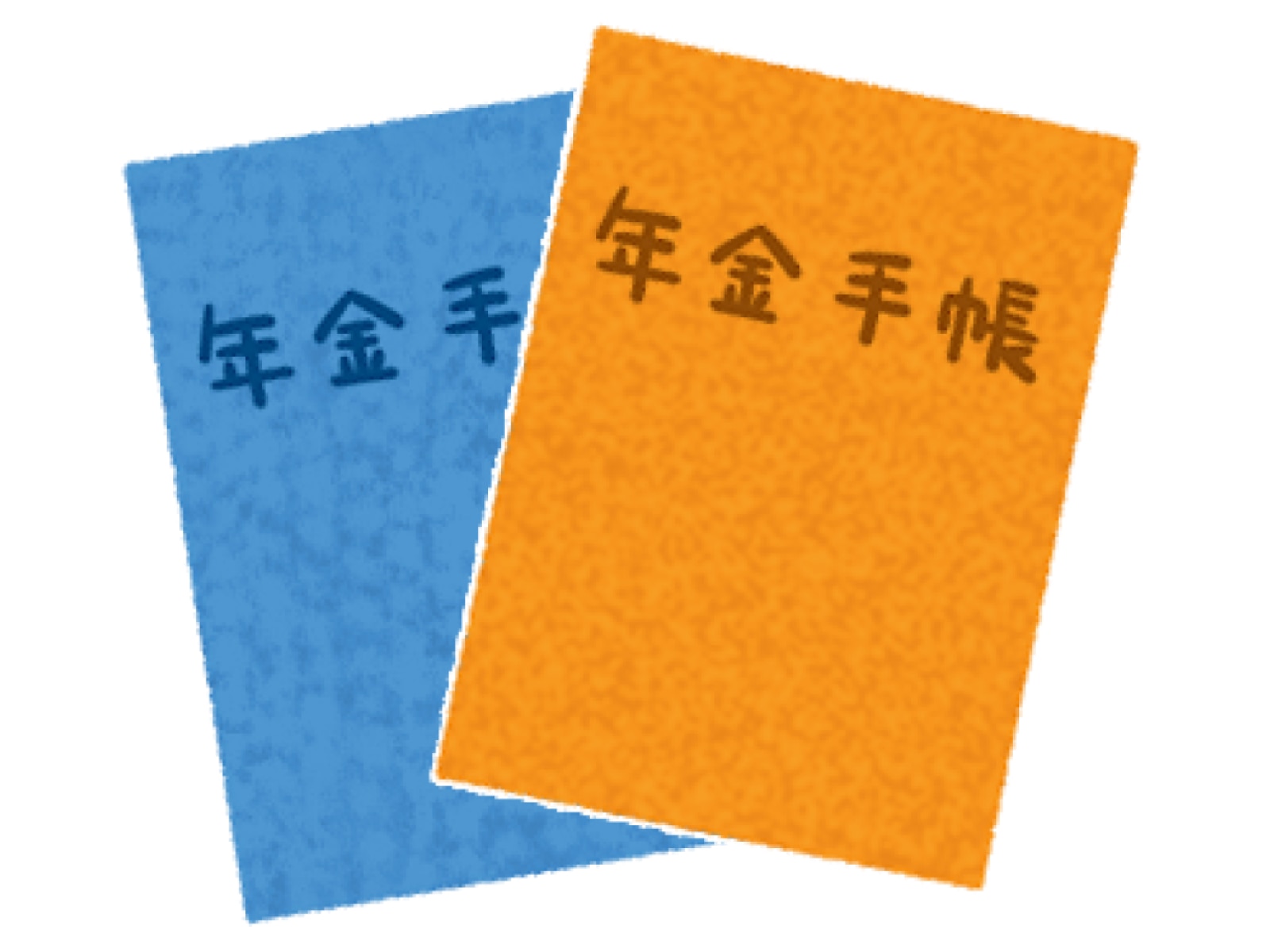
外国人労働者に対する社会保険への加入について解説!
外国人労働者を雇用する際、社会保険の加入で悩んでいる方は少なくないでしょう。
日本人と同じ扱いなのか、どの保険に加入すべきかなど、さまざまな疑問が生じるかと思います。
一定の条件を満たした外国人労働者は、社会保険への加入が義務付けられています。
本記事では、外国人労働者の社会保険加入に関する基本や手続きの流れ、注意点を詳しく解説します。
外国人労働者の雇用を検討している企業の人事担当者や経営者の方は、ぜひ最後までお読みください。
目次[非表示]
外国人労働者も社会保険への加入が必要?
外国人労働者は、日本人労働者と同様に4つの社会保険への加入が必要です。
|
これらの保険は労働者の国籍に関わらず、一定の条件を満たす場合に加入義務が生じます。
労災保険は業務上の事故や通勤中の事故に対する補償を、雇用保険は失業時の生活保障や再就職支援を提供します。
健康保険は病気やけがの際の医療費を補助し、年金保険は将来の老後の生活を支える役割を果たします。
外国人労働者を雇用する企業は、社会保険の加入手続きを適切に行わなければいけません。
労働時間や給与額などの条件によっては、加入すべき保険が異なる場合もあります。
したがって、個々の状況に合わせた対応が必要です。
外国人労働者を雇う際の社会保険の手続き
外国人労働者を雇う際の社会保険の手続きは、4つあります。
|
それぞれの手続きを把握し、スムーズな採用を心がけましょう。
健康保険・介護保険に加入する
外国人労働者を雇用する際は、健康保険と介護保険への加入手続きが必要です。
健康保険の適用対象者は、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、月額賃金が8.8万円以上の労働者です。
ただし、学生や短期滞在者などは適用除外になる場合があります。
介護保険は、40歳以上65歳未満の健康保険加入者が対象です。
手続きは、事業主が日本年金機構に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出します。
なお、健康保険の被扶養者は国内に居住していることが条件です。
海外に住む外国人労働者の家族は、原則として被扶養者にはなりません。
ただし、一時的な海外居住の場合など、例外的に認められるケースもあります。
したがって、状況に応じて確認が必要です。
海外に住む外国人労働者の家族は不要対象になる?
海外に住む外国人労働者の家族は、原則として健康保険の被扶養者にはなりません。
日本の健康保険制度では、国内に居住する被保険者とその家族を対象としているためです。
ただし、例外的に認められるケースもあります。
外国人労働者の配偶者や子どもが一時的に海外に滞在している、留学のために海外に居住している場合などは、被扶養者として認められる可能性があります。
該当する場合は、状況を健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に相談し、判断を仰ぎましょう。
また、海外に居住する家族の医療費は、日本の健康保険が適用されません。
別途、海外旅行保険などへの加入を検討すべきです。
厚生年金保険に加入する
外国人労働者を雇用する際は、厚生年金保険への加入が必要です。
厚生年金保険は、健康保険と同様の加入条件が適用されます。
週の所定労働時間が20時間以上で、月額賃金が8.8万円以上の労働者が対象です。
加入手続きは、日本年金機構に健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出します(健康保険と同時にできる)。
厚生年金保険は、将来の老後の生活を支える制度です。
外国人労働者でも、日本での就労期間に応じて年金受給権が発生する可能性があります。
短期間の就労で帰国する場合は、脱退一時金の制度も検討しましょう。
また、日本と社会保障協定を結んでいる国の出身者の場合は、年金加入期間の通算などの取り扱いになる可能性があります。
雇用保険に加入する
外国人労働者を雇用する際は、雇用保険への加入も欠かせません。
雇用保険は、失業時の生活保障や再就職支援を行う制度です。
加入条件は、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者です。
加入手続きは、事業主が労働者を雇用した翌日から10日以内に、ハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
ただし、一部の在留資格(外交、公用、短期滞在など)を持つ外国人労働者は、雇用保険の適用対象外です。
また、留学生のアルバイトなど、週の所定労働時間が20時間未満の場合も同様です。
雇用保険は失業時の給付金だけでなく、在職中の教育訓練給付金なども利用できる制度です。
そのため、外国人労働者には欠かせない保証です。
雇用保険への加入が適用されない場合
雇用保険への加入が適用されないケースは、在留資格が外交・公用・短期滞在の場合です。
また、週の所定労働時間が20時間未満の場合も適用されません。
さらに、季節的に雇用される者で、4か月以内の期間を定めて雇用される場合も適用除外です。
ただし、条件に該当しても、1年以上の雇用が見込まれる場合は被保険者になる可能性があります。
派遣労働者の場合は、派遣元の事業所で雇用保険に加入するのが一般的です。
保険の適用は個々の雇用状況に応じて判断されるため、不明な点がある場合はハローワークに相談しましょう。
外国人労働者が雇用保険に加入しない場合に必要な手続き
雇用保険に加入しない場合でも、必要な手続きがあります。
まず雇用保険の適用除外となる理由を明確にし、根拠となる資料を保管しなければいけません。
在留資格が適用除外に該当する場合は、在留カードのコピーを保管します。
また、週20時間未満の就労の場合は、労働条件通知書や雇用契約書のコピーを保管する必要があります。
さらに、雇用保険被保険者資格取得届の代わりに、雇用保険被保険者資格取得届出不要確認書を作成し、保管しておくべきです。
確認書には、主に以下の情報を記載します。
|
これらの手続きは、労働基準監督署や入国管理局からの問い合わせに備えるためのものです。
適切な手続きを行えば、法令遵守の姿勢を示せます。
労災保険が適用される
労災保険は、労働者が業務上の事故や通勤中の事故によって負傷・疾病にかかった場合に、必要な保険給付を行う制度です。
労働者を1人でも雇用している事業主は加入義務があります。
対象は雇用形態や在留資格に関係なく、すべての労働者です。
したがって、パートタイムやアルバイト、短期雇用の外国人労働者も対象になります。
労災保険料は全額が事業主負担となり、労働者の給与から天引きできません。
主な給付内容は、3つあります。
|
外国人労働者が業務上の事故や疾病に遭った場合は、速やかに労災保険の請求手続きを行いましょう。
脱退一時金とは
脱退一時金は、日本の年金制度に加入していた外国人が帰国する際に、一定の条件を満たせば受け取りが可能になる制度です。
短期間の就労で、年金受給権が発生しない外国人労働者のために設けられています。
一時金を受け取るには、4つの条件を満たさなければいけません。
|
脱退一時金の請求は、日本を出国後2年以内に行う必要があります。
請求額は、保険料納付済期間に応じて計算されます。
ただし、一時金を受け取ると、その期間の年金加入期間がなくなるため注意が必要です。
社会保障協定とは
社会保障協定は国際間の年金制度の重複加入を防ぎ、年金加入期間を通算して年金受給権を確保するための二国間の取り決めです。
日本は現在、多くの国と社会保障協定を締結しています。
外国人労働者は協定により、日本で働く際の社会保険の取り扱いが明確です。
派遣元国の年金制度に加入している場合は、日本の年金制度への加入が一定期間免除される可能性があります。
また、日本と協定国での年金加入期間を通算して、それぞれの国の年金受給資格を得られる可能性もあります。
ただし、協定内容は国によって異なるため、個別の状況に応じて確認が必要です。
社会保障協定は外国人労働者の年金権を保護し、国際的な人材移動を促進する役割を果たしています。
企業は、外国人労働者の出身国と日本との社会保障協定の有無を確認し、適切な対応を取らねばいけません。
企業内転勤の場合の保険に扱い
企業内転勤で来日する外国人労働者の社会保険の扱いには、特別な配慮が必要です。
健康保険と厚生年金保険では、原則として日本の制度に加入しなければいけません。
ただし、協定国からの転勤者の場合は、一定期間(通常5年程度)に限り、派遣元国の年金制度に継続加入し、日本の年金制度への加入が免除される可能性があります。
この場合、派遣元国の社会保険制度の適用証明書を取得し、日本の年金事務所への提出が必要です。
雇用保険は、日本国内の事業所に雇用される形態なら通常加入が必要です。
労災保険は日本国内で就労する以上、必ず適用されます。
企業内転勤の場合は、本人の給与体系や福利厚生の継続性を考慮しつつ、日本の法令に則った適切な保険加入を行うべきです。
外国人労働者を雇用している際に注意すべきこと
外孤高人労働者を雇用している際は、賃金設定と在留資格の更新に注意が必要です。
怠ると、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
外国人労働者の賃金設定
外国人労働者の賃金設定は、日本人労働者と同様に最低賃金法を遵守する必要があります。
最低賃金は地域や業種によって異なるため、事業所の所在地の最低賃金を確認し、下回らないようにしなければいけません。
また、労働基準法第3条により、国籍を理由とした賃金の差別的取り扱いは禁止されています。
外国人労働者に対しても、日本人労働者と同等以上の賃金の提供が必要です。
最低賃金未満の賃金を合意に基づいて支払ったとしても、法律上は無効とみなされます。
在留資格の更新
在留資格の更新は、外国人労働者の雇用を継続する上で欠かせない手続きです。
雇用主は、外国人労働者の在留期限を把握し、更新手続きを適切に行うようサポートする必要があります。
更新申請は、在留期限の3ヶ月前から可能です。
手続きには、雇用契約書や給与明細などの書類が必要になるため、事前に用意しておきましょう。
また、外国人労働者が退職後3ヶ月以上にわたり、再就職や就職活動をしない場合は、在留資格が取り消される可能性があります。
在留資格の更新は、忘れないよう明確にしておくべきです。
外国人労働者が退職または解雇した際の社会保険の手続き
外国人労働者を退職または解雇した際の社会保険の手続きは、日本人と同様です。
必要に応じて、特有の手続きを済ませる必要があります。
日本人と同じ手続き
外国人労働者が退職する際は、日本人労働者と同様の手続きが必要です。
手続き | 内容 |
|---|---|
雇用保険の離職票の交付 | 失業給付受給のために必要 |
源泉徴収票の交付 | 退職年の所得税確定申告に必要 |
健康保険の被保険者証の回収 | 退職後の不正使用防止のため |
住民税の手続き | 支払うべき残高がある場合の処理 |
労働保険・社会保険の資格喪失手続き | 退職に伴う保険資格の喪失処理 |
各手続きは外国人労働者の権利を保護し、適切な社会保障を確保するために欠かせません。
外国人労働者特有の手続き
外国人労働者特有の手続きは、主に4つです。
|
必要な条件と場所を理解し、適切な情報提供を行いましょう。
退職証明書の作成・交付
外国人労働者から請求があった場合は、退職証明書を作成・交付する必要があります。
証明書には、以下の事由を記載しなければいけません。
|
ただし、労働者が請求しない事項の記入は禁止されています。
外国人雇用状況の届出の提出
外国人労働者が退職した場合は、ハローワークへ外国人雇用状況の届出を提出する必要があります。
届出に記載する情報は、以下のとおりです。
|
この手続きは、雇用保険の被保険者になっていない外国人労働者の場合も必要です。
届出を怠ると罰則の対象になる可能性があります。
在留カード番号記載様式を提出する
事業主は外国人労働者の退職に伴い、在留カード番号記載様式を管轄の地方出入国在留管理局に提出しなければいけません。
様式の提出は、外国人雇用状況の適切な管理と、不法就労の防止を目的としています。
記載する主な情報は、以下のとおりです。
|
手続きを行うと、外国人労働者の在留状況の変更を適切に報告できるほか、関係機関との情報共有を図れます。
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する
雇用保険の被保険者だった外国人労働者が退職した場合は、事業主がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。
届出は、退職日の翌日から10日以内に行わなければいけません。
記載する主な情報は、以下のとおりです。
|
手続きが完了すると、外国人労働者は失業給付の資格を得られます。
ただし、提出を怠ると、後日の給付申請に支障をきたす可能性があるため、注意が必要です。
外国人労働者へのサポートならスタッフ満足へお任せください
スタッフ満足は、外国人労働者の採用から定着までトータルサポートを提供する専門サービスです。
10年以上の経験を活かし、特定技能外国人の人材採用支援から入国後のサポートまで一貫したサービスを展開しています。
特徴は以下のとおりです。
|
特に、特定技能外国人の人材・採用支援と、採用後の定着支援が強みです。
特定技能外国人の人材・採用支援
スタッフ満足は、特定技能外国人の人材採用から定着までをトータルサポートする専門サービスを提供しています。
10年以上の経験を活かし、国内および海外主要6ヶ国(ベトナム、フィリピン、ミャンマー、ネパール、インドネシア、スリランカ)から安定的に人材を紹介しています。
特徴は、大きく分けると5つです。
|
さらに、外国人スタッフの育成ノウハウや、即戦力となるためのサポート体制が整えられています。
これにより、外国人採用が初めての企業でも、安心して採用活動を推進できます。
| 特定技能外国人 人材紹介サービス資料 外国人の豊富な育成経験をもとに支援内容をつくりあげました。 特定技能外国人に必要な支援を網羅し、離職防止につながる面談や学習支援を提供いたします。 |
採用後の定着支援なら「登録支援機関」サービスの活用もおすすめ
スタッフ満足の登録支援機関サービスは、特定技能外国人の採用後の定着を支援するプログラムです。
政府が定める10項目の義務的支援を一律料金で提供し、必要な業務に加え、eラーニングを活用した日本語学習、資格取得支援(介護福祉士含む)まですべてカバーします。
|
サービスを利用すれば、採用担当者の負担が軽減されるほか、外国人材に必要なサポートが確実に提供されます。
スタッフ満足は各国に対応できる人材コーディネーターが在籍しているため、言語の壁を越えた細やかなサポートが可能です。
外国人材の定着率向上を目指したい企業は、ぜひ検討してみてください。
関連資料>>月額1.6万円の登録支援機関サービスの支援内容を見る
| 【月額1.6万円】 登録支援機関 サービス紹介資料 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 外国人コーディネーターの母国語対応、eラーニングによる日本語学習・特定技能2号試験、介護福祉士の学習と試験対策など、幅広い支援を提供いたします。 |
まとめ
外国人労働者の雇用には、日本人労働者と同様の手続きに加え、特有の手続きが必要です。
また、賃金設定では最低賃金法の遵守が不可欠なほか、在留資格の更新にも注意しなければいけません。
退職時には、通常の社会保険手続きに加え、外国人特有の手続きを適切に行う必要があります。
法令遵守と外国人労働者の権利保護の実現に向け、管理を徹底しましょう。
外国人労働者の雇用に関する複雑な手続きや支援に関しては、専門サービスを利用すると、スムーズな雇用管理が可能です。