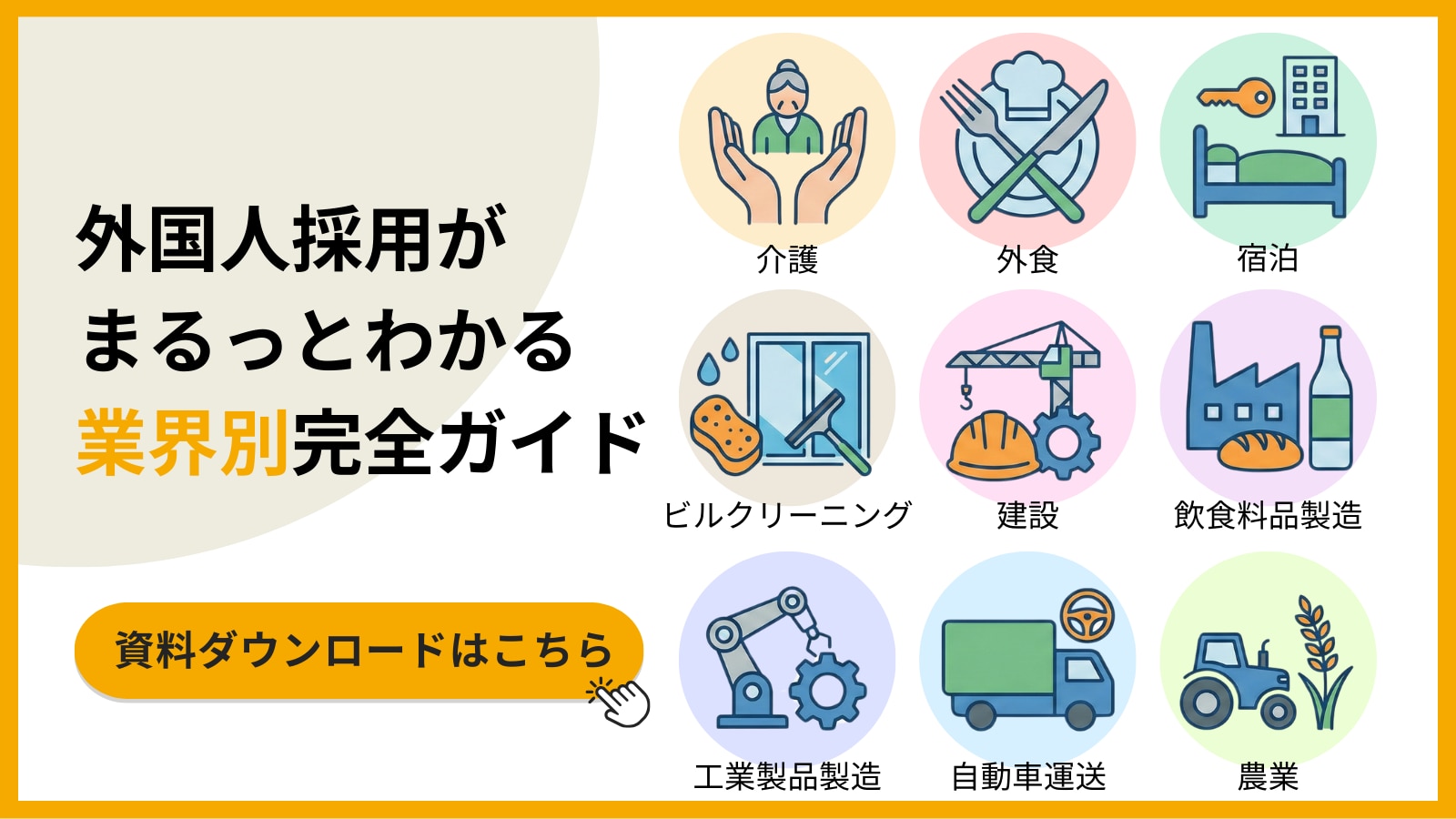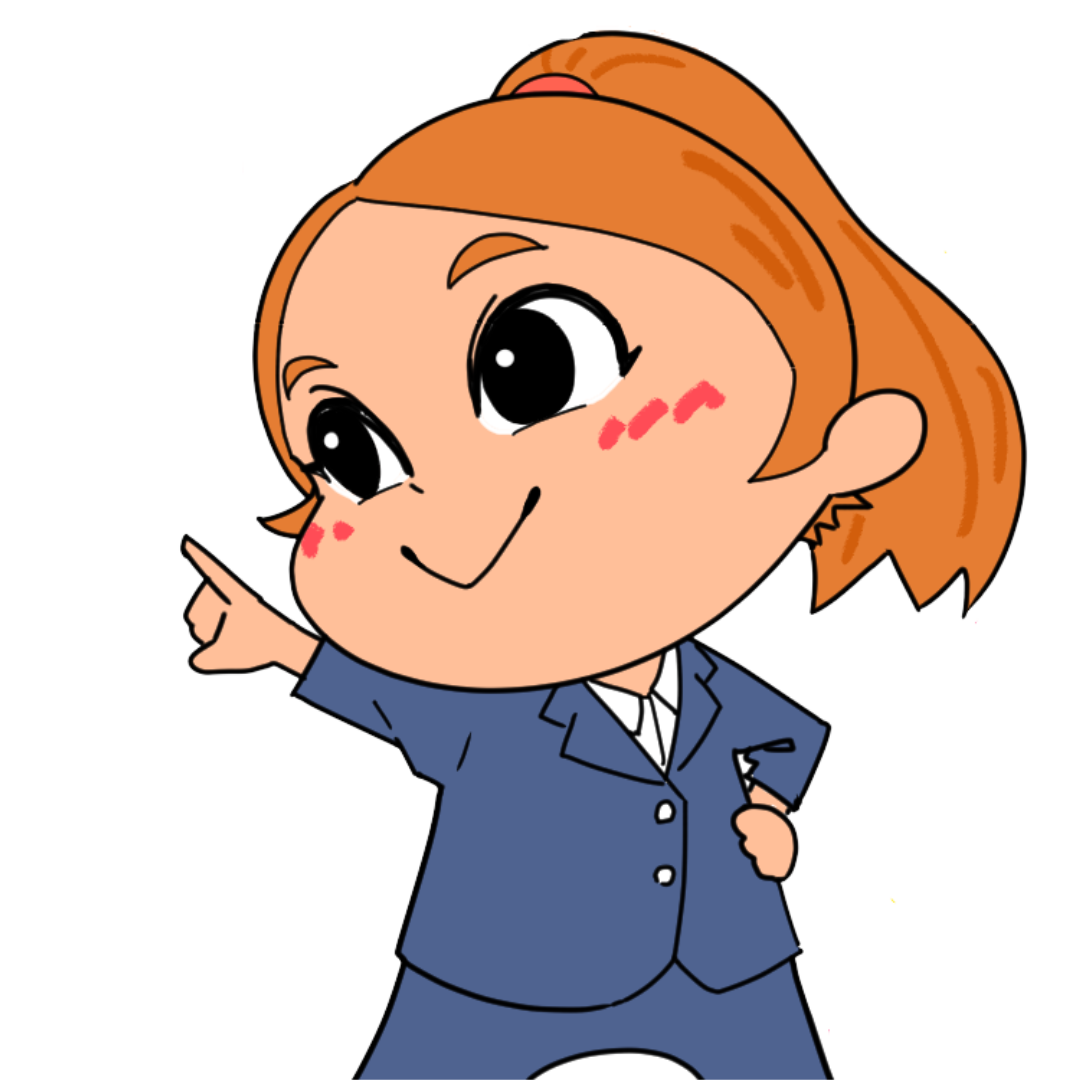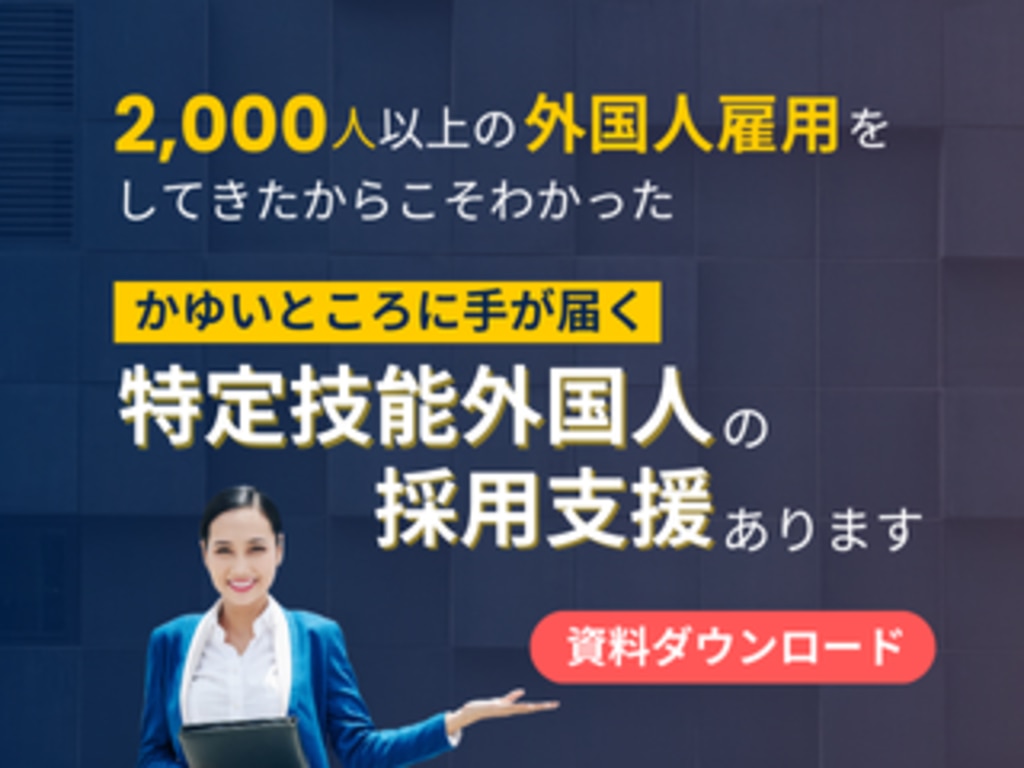外国人が退職する際の手続きとは?企業側と本人に分けて紹介
外国人従業員の退職は、日本人従業員と同様の手続きと、在留資格に関する手続きが必要です。
さらに、企業側と本人が分担して進めなければいけません。
本記事では、外国人従業員が退職する際に必要な手続きを、企業側と本人に分けて詳しく解説します。
スムーズに退職手続きを進めたい方、トラブルを未然に防ぎたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次[非表示]
外国人が退職する際の手続き
外国人が退職する際の手続きは、企業側と本人で異なります。
各項目を理解し、スムーズな手続きを実現させましょう。
企業側が行う手続き
外国人従業員が退職する際、企業側は下記の手続きが必要です。
|
各手続きの詳細を把握し、漏れがないよう明確なスケジュールを立てましょう。
雇用保険の離職票の交付
雇用保険の離職票は、退職する外国人従業員が失業給付を受けるために必要な書類です。
企業は退職日から10日以内に、管轄のハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を提出し、交付を受けなければいけません。
離職票は、2枚セットで発行されます。
1枚は企業が保管し、もう1枚は従業員に渡します。
票には在職中の賃金や勤務状況などが記載されているため、失業給付の算定基礎に欠かせません。
源泉徴収票の交付
源泉徴収票は、1年間の給与総額と源泉徴収された所得税額を記載した書類です。
退職する外国人従業員に対しても、退職時に交付する必要があります。
源泉徴収票は従業員が確定申告を行う際や、次の就職先での年末調整に必要です。
また、退職日の翌日から1ヶ月以内の交付が法律で定められています。
交付する際は正確な給与情報と税額を記載し、遅滞がないよう細心の注意を払いましょう。
健康保険の被保険者証の回収
外国人従業員が退職する際は、健康保険の被保険者証を回収しなければいけません。
退職日から5日以内に、健康保険組合または全国健康保険協会へ返却します。
回収できない場合は、健康保険被保険者証回収不能届を提出する必要があります。
また、被保険者証の回収と同時に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出し、健康保険と厚生年金保険の資格喪失手続きを行わなければいけません。
住民税の未払いがある場合の手続き
外国人従業員が退職する際に、住民税の未払い分がある場合は適切な処理が必要です。
通常、住民税は前年の所得に基づいて計算され、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。
退職時に未払い分がある場合は、一括徴収するか、従業員本人が市区町村に直接納付するかを確認します。
一括徴収する場合は最後の給与から未払い分を天引きし、市区町村に納付するのが一般的です。
本人が直接納付する場合は、給与所得等に係る特別徴収税額の納期の特例に関する届出書を提出し、本人に納付書を渡す必要があります。
労働保険・社会保険の資格損失手続き
外国人従業員が退職する際は、労働保険と社会保険の資格喪失手続きが必要です。
労働保険は、雇用保険被保険者資格喪失届を退職日の翌日から10日以内に、ハローワークへ提出します。
社会保険は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を退職日から5日以内に、日本年金機構へ提出します。
手続きを適切に行えば、保険料の過徴収を防げるほか、従業員の権利を守れるメリットがあります。
ハローワークへの届出
外国人従業員が退職する際は、ハローワークへの届出が必要です。
届出は雇用対策法に基づく義務であり、外国人雇用状況の把握のために行われます。
雇用保険の被保険者である場合は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出をもって届出とみなされます。
被保険者でない場合は、外国人雇用状況届出書(離職)の提出が必要です。
ハローワークへの届出は、退職日の翌日から起算して1ヶ月以内に行わなければいけません。
在留カード番号記載様式の提出
外国人従業員が退職する際は、在留カード番号記載様式の提出が必要です。
様式は、外国人雇用状況の適切な把握と管理のために使用されます。
記入する主な情報は、以下のとおりです。
|
すべての情報を記入し、ハローワークに提出します。
この手続きは、外国人雇用状況届出と同時に行えます。
正確な情報を記載し、期限内に提出しましょう。
退職証明書の発行
退職証明書は、外国人従業員が請求した場合に発行すべき書類です。
労働基準法第22条に基づき、従業員から請求があった場合、請求された事項について証明する必要があります。
主な項目は5つです。
|
退職証明書は従業員が次の就職先を探す際や、在留資格の更新・変更の際に求められる場合があります。
従業員の要請に応じ、正確な情報を記載した証明書を速やかに発行できるよう努めましょう。
退職する外国人が行う手続き
外国人従業員も退職する際、契約期間に関する届け出と脱退一時金の請求を行う場合があります。
企業側の手続きに意識が集中しないよう、注意しましょう。
契約機関に関する届出を行う
外国人従業員は、退職後14日以内に出入国在留管理局に所属機関に関する届出を行わなければいけません。
届出は、在留資格の技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能などの就労資格を持つ外国人に義務付けられています。
記載すべき主な情報は、以下のとおりです。
|
手続きを怠ると、在留資格取消しの対象になる可能性があります。
必ず期限内に行うよう注意してください。
脱退一時金の請求を行う
帰国する外国人従業員は、年金の脱退一時金を請求できます。
脱退一時金は、日本の年金制度に6か月以上加入していた外国人が、年金受給資格期間を満たさずに帰国する場合に請求できる制度です。
請求は帰国後2年以内に行う必要があり、在職中の保険料納付月数に応じて支給されます。
請求には、脱退一時金請求書の提出が必要です。
したがって、帰国する前に日本年金機構から取り寄せておきましょう。
ただし、脱退一時金を受け取ると、その期間の年金加入期間がなくなります。
請求は慎重に検討してください。
外国人に伝えておくべき退職後のビザについて
外国人従業員が転職する場合は、在留資格(ビザ)に関する注意点を伝えておく必要があります。
日本での在留資格は特定の活動や職務に基づいて付与されているため、退職後も有効にするには一定の条件を満たさなければいけません。
一般的には3ヶ月以上働いていない状態が続くと、資格が取り消される可能性があります。
ただし、積極的に就職活動を行っている、やむを得ない事情がある場合は、例外になることもあります。
企業は外国人従業員に対して、退職後速やかに次の就職先を見つけるか、就職活動を行う重要性を伝えましょう。
また、在留期限が迫っている場合は、特定活動(就職活動)への在留資格変更を検討するよう助言するのも有効です。
資格に関する正確な情報を提供し、適切な対応を促せば、スムーズな転職や日本での滞在をサポートできます。
外国人が退職した場合は必ず3ヶ月以内に再就職が必要?
外国人従業員が退職しても、3ヶ月以内に再就職しなければならない厳密なルールはありません。
しかし、就労活動を行っていない状態が3ヶ月以上続くと、在留資格が取り消される可能性が高くなります。
一方、取り消し対象にならない可能性もあります。
|
これらのケースでは、適切な証明書類や説明を提出すれば、在留資格を維持できる可能性があります。
企業は外国人従業員に対して、退職後も在留資格の維持に注意を払い、必要に応じて入国管理局に相談するよう伝えましょう。
外国人の退職の際に企業側が注意すること
外国人の退職の際に企業側が注意すべき点は、4つあります。
|
それぞれのポイントを押さえ、問題のない退職手続きを実現させましょう。
本人が行う手続きの存在を知らせる
企業側は退職する外国人従業員に対して、本人が行うべき手続きを適切に提供する必要があります。
特に、所属機関に関する届出や在留資格の変更・更新など、在留資格に関わる手続きについては漏れなく伝えなければいけません。
また、脱退一時金の請求や国民健康保険への加入など、生活に関わる手続きの情報も提供しましょう。
従業員が退職手続きをスムーズに行えるよう、日本語以外の言語での説明や専門家への相談を勧めるなどのサポートを行うのも有効です。
届出の期限を厳守する
外国人従業員の退職に関する各種届出には、それぞれ法定の期限が設けられています。
これらの期限の厳守は、企業の法的義務です。
違反すると、罰則の対象になる可能性があります。
特に、ハローワークへの届出や社会保険の資格喪失手続きなどは、期限が短いものが多いため注意が必要です。
届出の期限を一覧にして管理し、担当者間で共有するなど、組織的な対応を心がけましょう。
また、手続きに必要な書類や情報を事前に準備しておけば、期限内で確実に提出できます。
退職する外国人の動向を把握する
退職する外国人従業員の今後(帰国するのか、日本で転職するのかなど)の把握は、適切な退職手続きを行う上で欠かせません。
帰国する場合と日本に残る場合では、必要な手続きや注意点が異なるためです。
帰国する場合は脱退一時金の請求手続きが必要ですが、日本で転職する場合は在留資格の維持に関する情報を提供する必要があります。
企業は従業員のプライバシーに配慮しつつ、今後の予定について確認しましょう。
動向に応じて、適切なアドバイスや支援を行ってください。
就労ビザの説明を怠らない
外国人従業員が退職する際は、就労ビザに関する正確な情報を提供しなければいけません。
在留資格は就労の基盤になるため、退職後の扱いについて明確に説明する必要があります。
特に、在留期間中の就職活動や、在留資格の変更が必要になる可能性を詳しく伝えましょう。
また、3ヶ月以上の未就労状態が続くと、資格が取り消される可能性がある点も説明してください。
従業員の理解を確認しながら、状況に応じたアドバイスを行うのが理想です。
専門的なサポートが必要な場合は、入国管理局への相談や行政書士への相談を勧めましょう。
まとめ
外国人従業員の退職手続きは、企業側と本人それぞれに多くの責任が伴います。
企業は雇用保険や社会保険の手続き、各種証明書の発行など、法定の義務を確実に果たさなければいけません。
退職する外国人本人も、在留資格に関する届出や脱退一時金の請求などを行う必要があります。
退職手続きでは、双方が協力し、漏れなく手続きを進める意識が重要です。
特に、在留資格に関する正確な情報提供と適切なアドバイスは、外国人従業員の今後に大きな影響を与えます。
企業は手続きを単なる義務として捉えるのではなく、グローバル人材のスムーズな移動をサポートする機会として捉える姿勢を持つ必要があります。