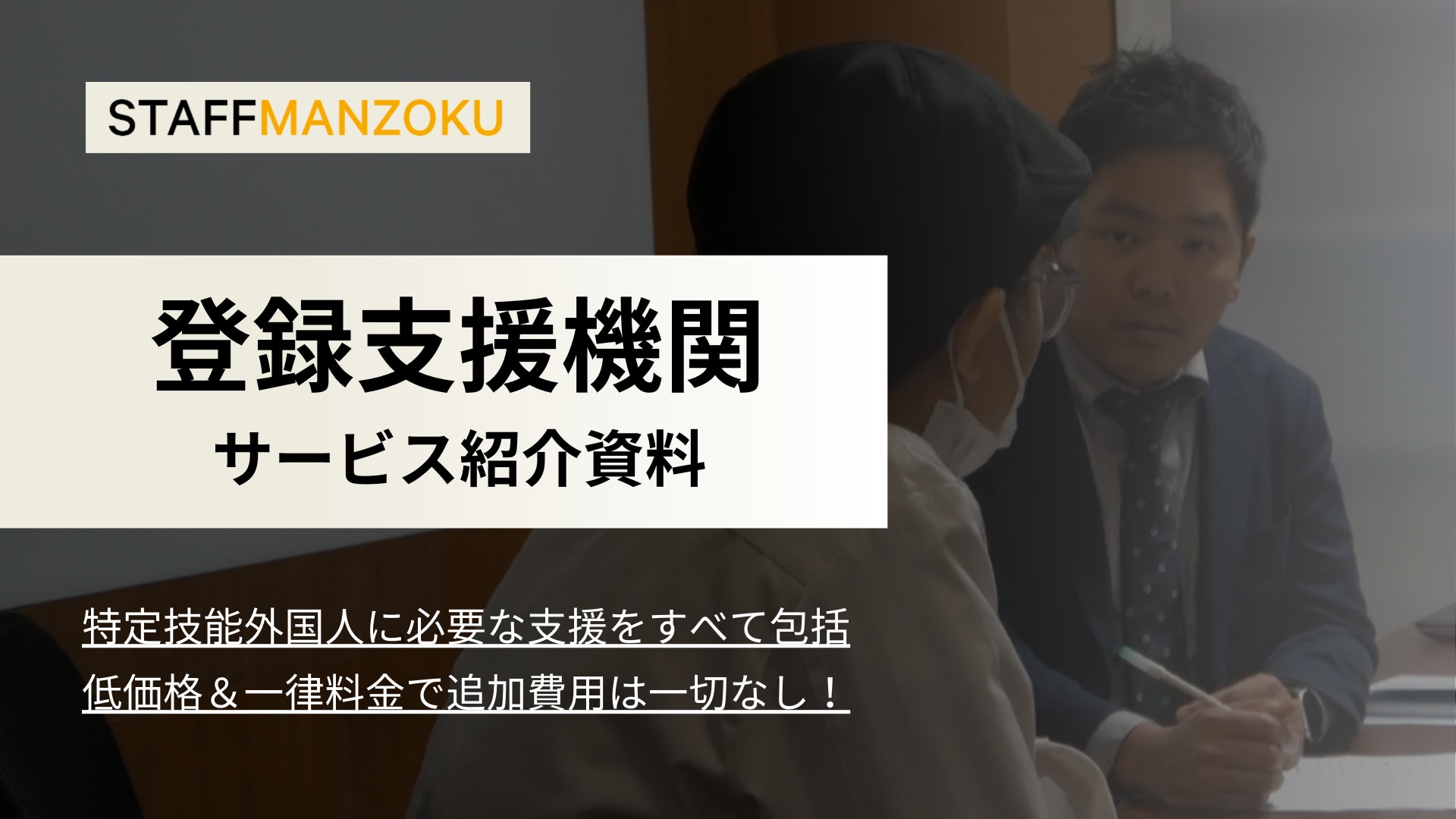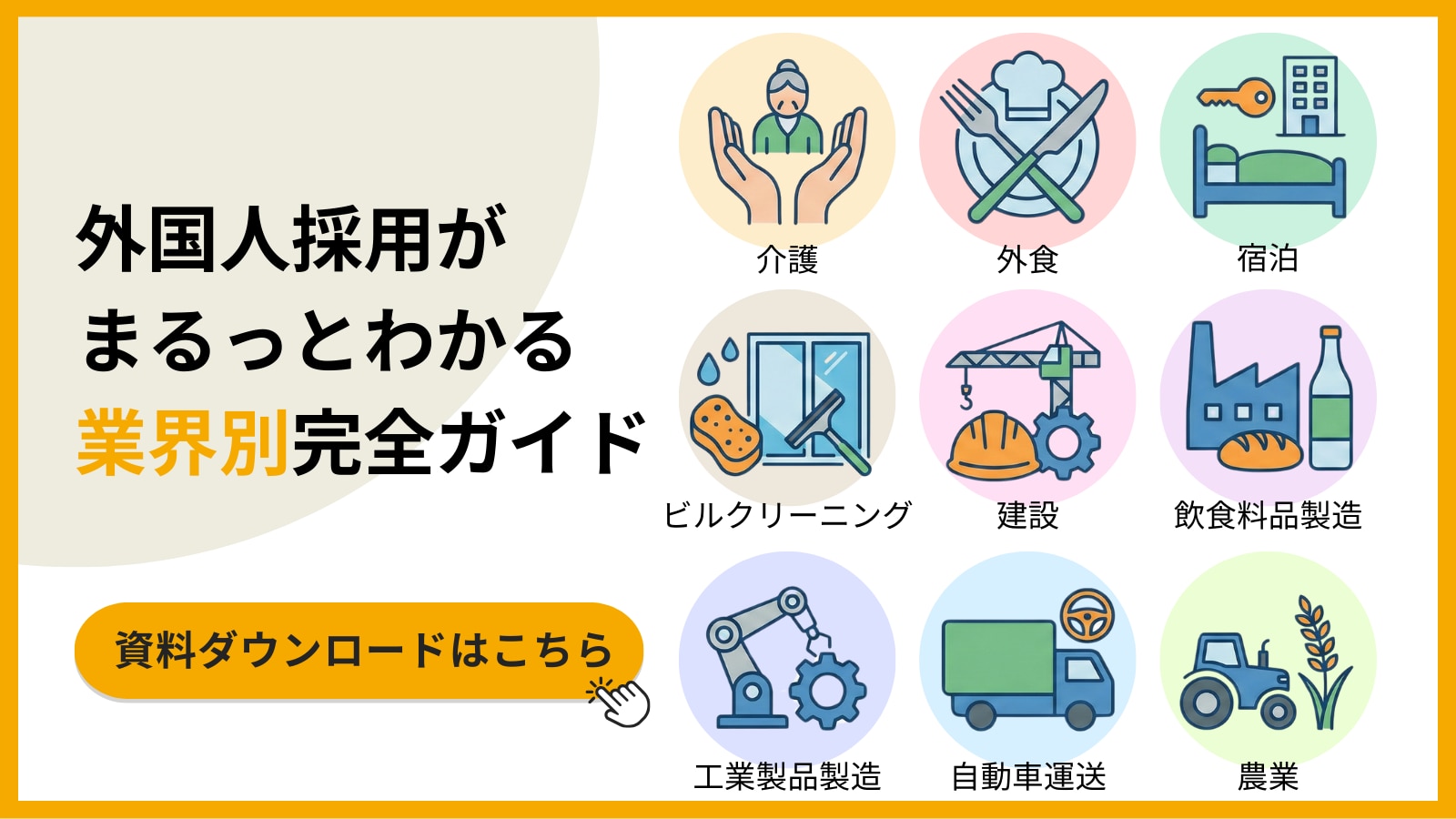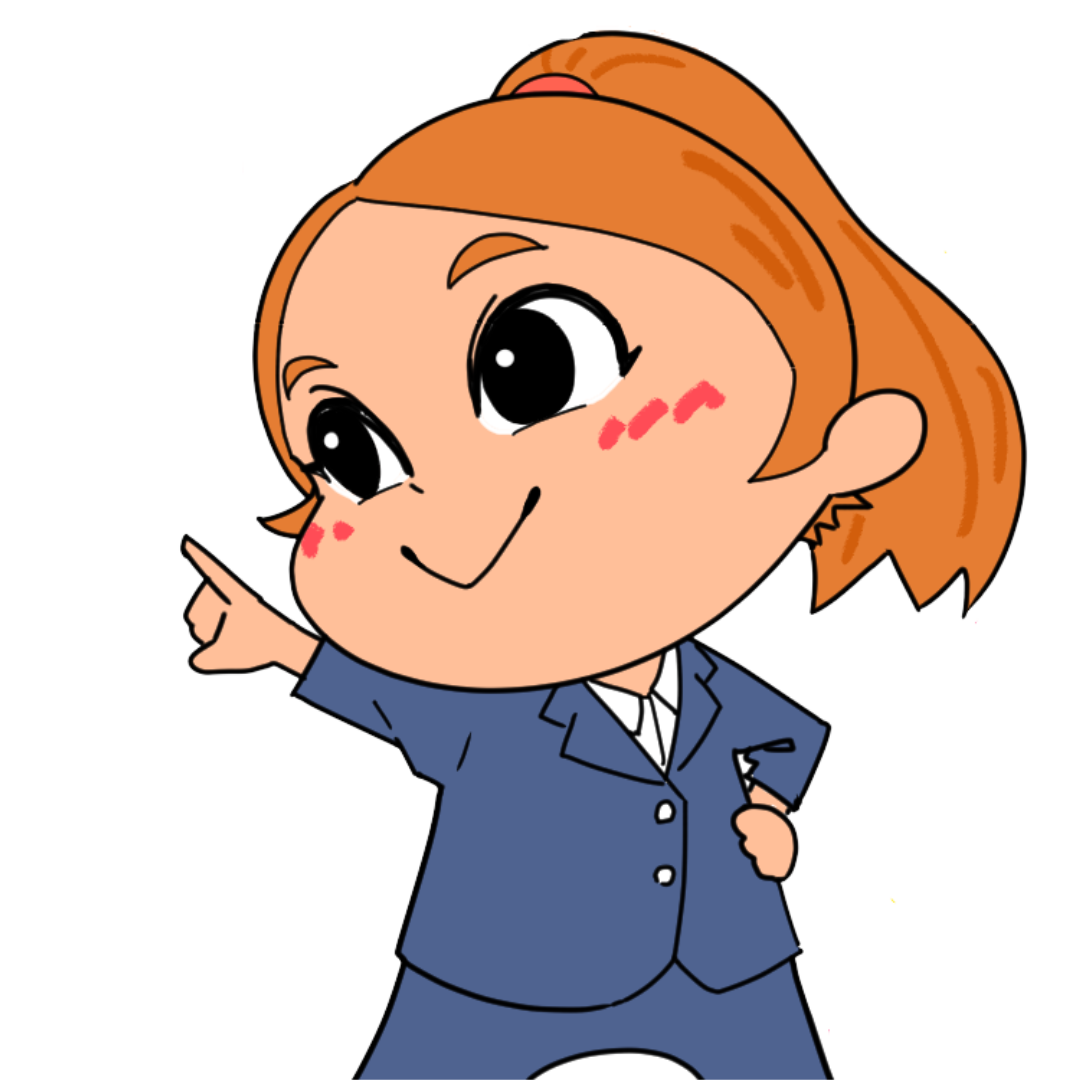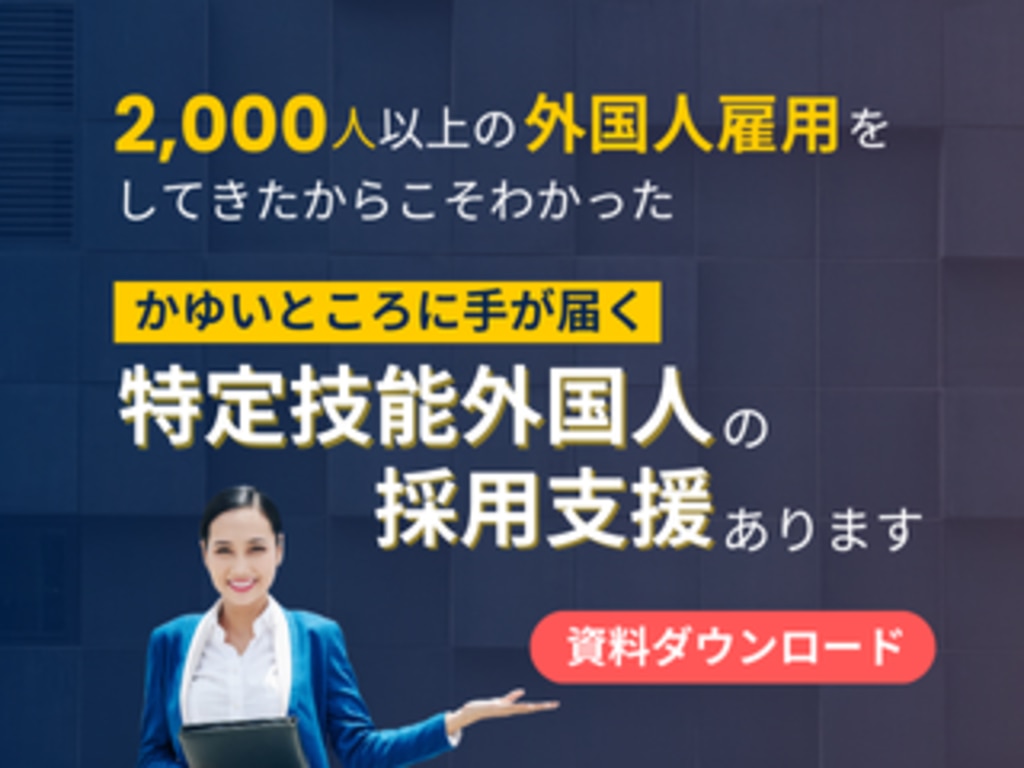永住権取得とは?永住権取得の条件と取得までの流れ徹底解説
永住権とは、外国人が在留期間や就労内容に制限がなく、日本に滞在できる権利を指します。
企業側としても、在留資格「永住者」の外国人人材を雇用すれば「一部の業務しか任せられない」といった悩みを解決できるでしょう。
本記事では永住権とはどのようなものか、取得条件からメリットまでを解説します。
なおスタッフ満足では、幅広い外国人人材の紹介が可能です。
外国人採用をお考えの企業さまは、ぜひご相談ください。
詳細ページ>>月額1.6万円の登録支援機関サービスの支援内容を見る
| 【月額1.6万円】 登録支援機関 サービス紹介資料 特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。 外国人コーディネーターの母国語対応、eラーニングによる日本語学習・特定技能2号試験、介護福祉士の学習と試験対策など、幅広い支援を提供いたします。 |
目次[非表示]
- 1.永住権とは
- 2.「技能実習」「特定技能」から日本の永住権は取得できる?
- 3.外国人が永住権を取得するための条件
- 4.外国人が永住権の取得にかかる年数
- 4.1.① 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
- 4.2.② 日本人・永住者の実子・特別養子の場合
- 4.3.③ 定住者の場合
- 4.4.④ 日本への貢献があったと認められた場合
- 4.5.⑤ 高度人材外国人として日本に滞在している場合
- 4.6.⑥難民の認定を受けている場合
- 5.外国人人材が永住権を取得するメリット
- 5.1.① 在留期限がない
- 5.2.② 配偶者が死亡してしまっても日本に在留できる
- 5.3.③ 社会的な信用を得られる
- 6.永住権が取り消されるケース
- 7.まとめ
永住権とは
永住権とは、出入国管理及び難民認定法第22条により、永住許可を認められた外国人に与えられる権利です。
永住権が認められると在留資格「永住者」を取得できます。
在留資格「永住者」を保有すれば、活動制限がなくなるため、職種・業種などの就労制限もなくなります。
しかし、在留資格「永住者」を取得するには3つの条件をクリアしなければいけません。
どのような条件かは後述しているため、ご確認ください。
永住権の取得と混同されやすいのが「帰化」です。
帰化とは、外国人人材が日本国籍を取得して「日本国民になること」をいいます。
在留資格「永住者」の取得は、外国籍・外国人のままで日本に永住することを意味します。
帰化した場合、日本人が受ける社会保障などの権利も受けられますが、母国の国籍から離脱しなければいけません。
「技能実習」「特定技能」から日本の永住権は取得できる?
詳しくは後述していますが、外国人が永住権を取得するためには原則として10年以上日本に滞在する必要があります。
またそのうちの5年間は「技能実習」「特定技能1号」を除く就労資格、または居住資格(日本人や永住者の配偶者など、定住者)での滞在でなければいけません。
そのため技能実習・特定技能1号合わせて10年間在留しても、永住許可は認められません。
ただし「特定技能2号」であれば永住権の条件を満たします。
「技能実習」「特定技能」から日本の永住権を取得するなら「特定技能2号」に移行しなければいけません。
現在「特定技能2号」に移行できる産業分野は建設分野と造船・舶用工業分野のみです。
今後、1号から2号へ移行できる産業分野が拡大される可能性はあります。
外国人が永住権を取得するための条件
外国人人材が永住権を取得するためには、3つの条件をクリアしなければいけません。
|
それぞれ詳しく解説します。
またこの3つの条件以外にも、10年以上日本に滞在する必要があります。
一部例外はありますが、詳しくは「永住権の取得にかかる年数」をご覧ください。
① 素行が善良であること
外国人人材が永住権を取得するためには、素行が善良でなければいけません。
法律・法令に違反していなければ、素行が善良として判断されます。
例えば万引き・窃盗などの前科があると永住権の許可がでません。
スピード違反や駐車違反などは、1回限りであれば素行不良と見なされない可能性があります。
しかし何度も違反を繰り返した場合は、永住許可の審査に影響すると考えられます。
② 独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
外国人人材が永住権を取得するには、日本で安定して暮らせるレベルの収入・スキルを保有していなければいけません。
収入については課税証明書や納税証明書で判断されます。
そのため、生活保護を受けている方は条件を満たしていないと判断されるので気をつけましょう。
扶養する家族がいる場合は、その人数に応じてたくさんの収入が必要です。
収入に関しては世帯単位で審査します。
配偶者やパートナーの収入が十分であれば、本人の収入が少なくても問題ないといわれています。
③ 日本国への利益になると認められること
永住権を申請する際に、その外国人の永住が日本の利益になるかを審査されます。
申告した外国人人材が日本の利益になるかの目安は、法務省のガイドラインに記載されています。
引用元:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)」
それぞれ詳しく解説します。
【アについて】
外国人が永住権を申請する際は原則として、日本に10年以上滞在している必要があります。
そのうち5年間は「技能実習」「特定技能1号」を除く就労資格、または居住資格(日本人や永住者の配偶者など、定住者)での滞在でなければいけません。
例えば留学で4年間、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で6年間日本に滞在している場合は就労資格で5年以上在留していることになります。
そのため、永住権申請の要件を満たしています。
【イについて】
「永住権を取得するための条件」でも記載したとおりに、永住権を取得するためには、法律・法令を遵守する必要があります。
【ウについて】
在留資格の種類によっては、1年・3年・5年と在留期間が異なります。
永住権を申請するためには、その資格の中で、一番長い在留期間を与えられている必要があります。
【エについて】
外国人本人が感染症や薬物中毒者でないなど、公衆衛生上の問題がないことを証明する必要があります。
外国人が永住権の取得にかかる年数
前述したとおり、外国人が永住権を取得する際は、原則として10年以上日本に滞在する必要があります。
しかし、場合によっては10年以上の在留が不要になるケースもあるのです。
この章では、以下6つのパターンについて解説します。
|
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
① 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
日本人、永住者、特別永住者(在日朝鮮人・韓国人・台湾人)と結婚しており、以下の条件に該当すれば、永住権を取得できます。
|
また配偶者が日本人の場合は「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること」の条件は不要になります。
② 日本人・永住者の実子・特別養子の場合
日本人・永住者の実子・特別養子の場合は、1年以上日本に滞在していれば、永住権の申請ができます。
③ 定住者の場合
「定住者」とは、日系人や難民、日本人の配偶者と死別・離別した外国人などを対象とした在留資格です。
在留資格「定住者」で5年以上日本に継続して滞在している場合、特例として永住権が認められます。
④ 日本への貢献があったと認められた場合
技術・スポーツ・研究などの特定分野で、特別な賞を受賞した場合は、日本に5年間滞在していれば、永住権の申請が可能です。
⑤ 高度人材外国人として日本に滞在している場合
高度人材外国人とは、専門的な技術力や知識を持つ外国人のことです。
高度人材外国人は、ポイント制による出入国管理上の優遇措置が認められています。
以下の条件に該当すれば、永住権の申請が可能です。
|
⑥難民の認定を受けている場合
難民の認定を受けており、日本に5年以上滞在していれば永住権の取得が可能です。
外国人人材が永住権を取得するメリット
外国人人材が永住権を取得するメリットは3つあります。
|
それぞれ詳しく解説していきます。
① 在留期限がない
他の在留資格には、1年・3年・5年の在留期限があります。
引き続き外国人人材を雇用する場合は、定期的に在留期間更新許可申請をしなければいけません。
しかし、在留資格「永住者」を保有すれば在留期限がなくなります。
在留期間更新許可申請の手続きが不要になるのはメリットといえます。
ただし、在留カードは7年ごとに更新が必要です。
② 配偶者が死亡してしまっても日本に在留できる
外国人人材の中には「日本人の配偶者」という条件で在留資格を保有している方もいるでしょう。
日本人配偶者が死亡した際は出国、場合によっては在留資格「定住者」への切り替えが可能です。
在留資格「永住者」を取得しておけば、日本人配偶者が死亡・離婚した場合も日本に滞在できます。
③ 社会的な信用を得られる
在留資格「永住者」を取得しておけば、素行が良好であることを証明できます。
そのため、クレジットカード作成や起業が比較的簡単になります。
在留資格「永住者」以外で、外国人が日本で起業する場合は、以下の条件を満たす必要があります。
|
永住権を取得できれば、日本人と同様に資本金1円から起業することも可能です。
永住権が取り消されるケース
外国人人材が在留資格「永住者」を取得すると、さまざまなメリットがあることがわかりました。
しかし、場合によっては永住権が取り消されるケースもあります。
永住権が取り消されるケースは以下のとおりです。
|
永住権を獲得しても、日本から国外へ出国する際は「再入国許可」「みなし再入国許可」が必要です。
許可なく出国した場合は永住権が取り消される可能性があります。
また永住許可申請時に「日本で犯罪歴があったのに申告しなかった」など、虚偽を申し立てた場合も永住権が取り消されます。
日本で処分や処罰を受けた場合は、永住権を取得しても強制送還(退去強制)となる可能性が高いです。
まとめ
在留資格「永住者」を保有している外国人人材であれば、幅広い業務を任せられます。
しかしどのように外国人人材を募集すれば良いか、わからない企業さまもいるでしょう。
スタッフ満足では、外国人人材の紹介から採用、定着までを支援しています。
外国人採用を検討している企業さまは、ご相談ください。