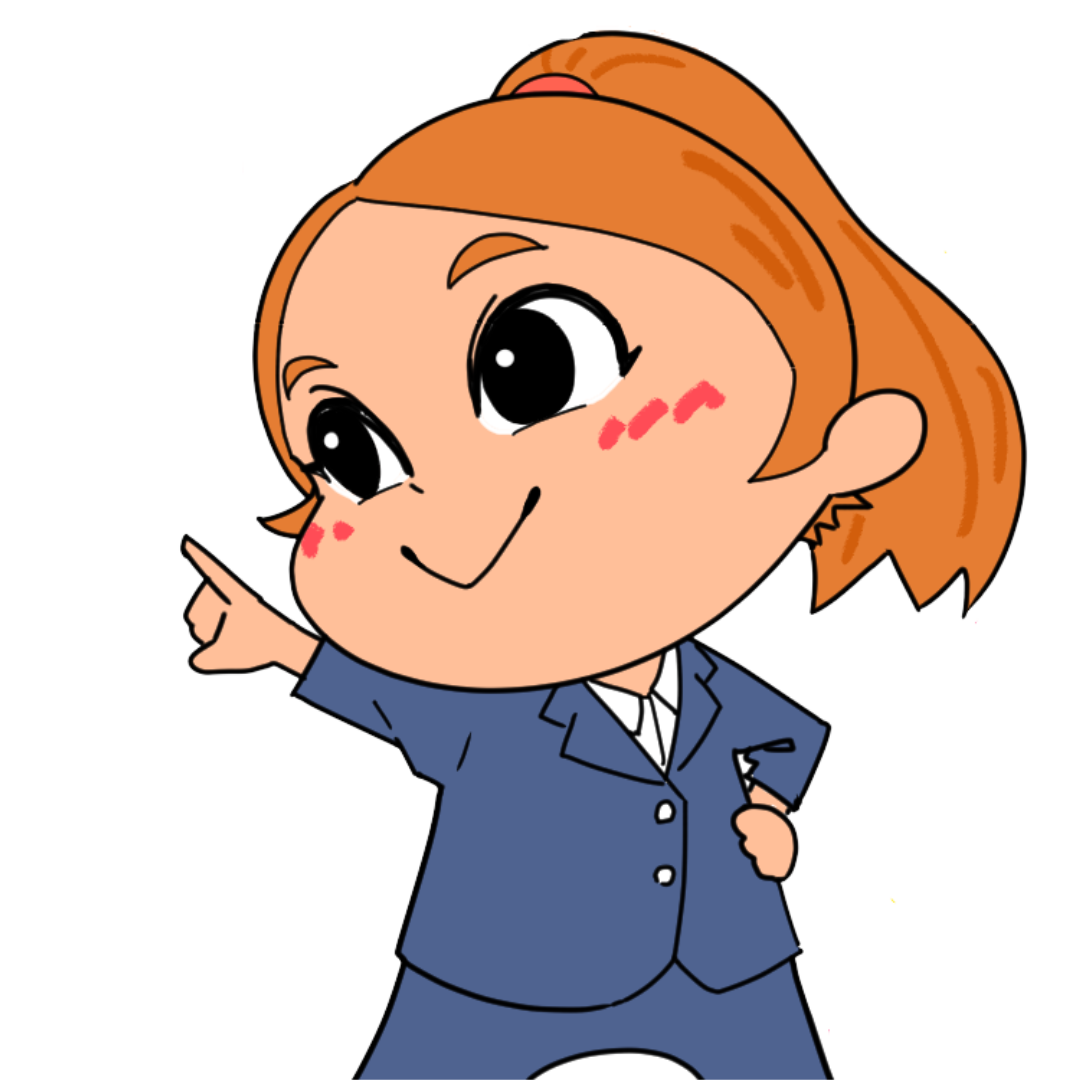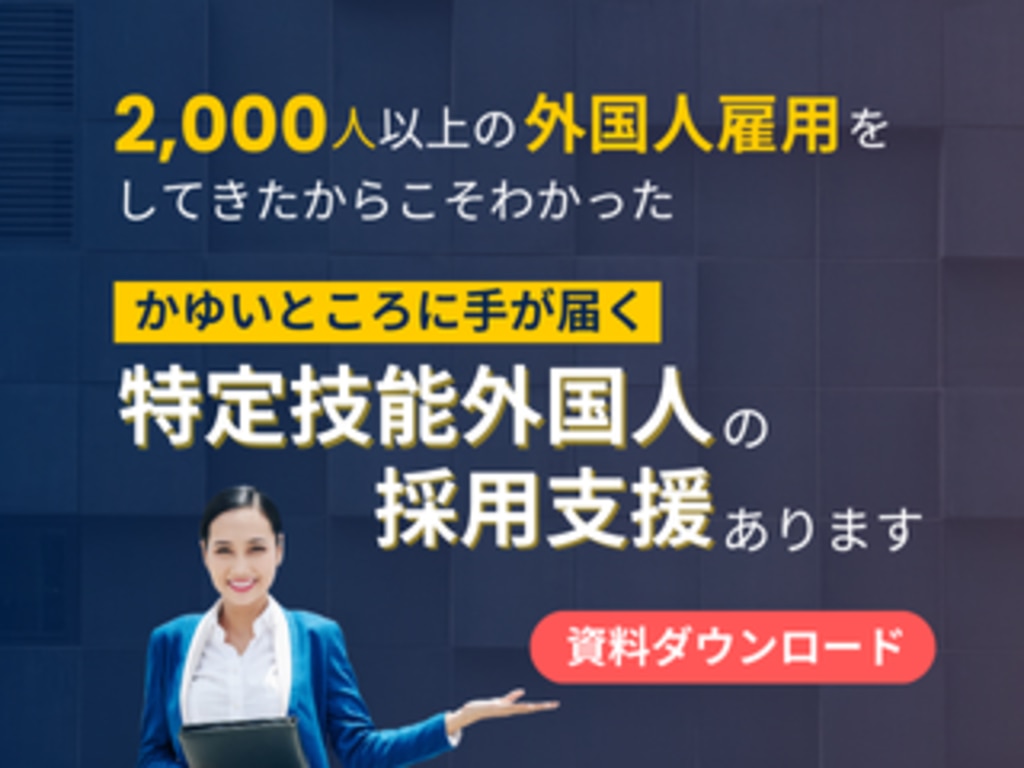日本での就労ビザが下りない!主な理由と対処法を解説
就労ビザの申請が下りない事態は、特定技能外国人の採用を検討する企業にとって重要な問題です。
業務内容の不一致や書類の不備、経済的証明の不足など、さまざまな原因があります。
採用を成功させるには問題をひとつずつ理解し、適切な対策を講じなければなりません。
必要な知識を身に着け、スムーズな受け入れを実現させましょう。
本記事では、就労ビザが下りない理由や具体的な対処法、申請時の注意点を解説します。
不許可を避けるためのポイントを押さえ、適切な採用活動を目指したい方は、ぜひ最後までお読みください。
| 【完全ガイド】日本で働ける在留資格 就労ビザに関する内容をまとめた資料です。 日本で働くことができる在留資格の概要をまとめておりますので、外国人雇用を検討する際の確認資料としてお使いいただけます。 |
目次[非表示]
就労ビザとは
在留資格は、外国人が日本で活動するために欠かせない法的資格です。
2023年末時点では日本に332万人の外国人が暮らしており、人口の2.6%を占めます。
就労ビザは職種に応じた区分があり、固有の審査基準が設定されています。
|
また、人手不足への対応として新設された特定技能は、従来の就労ビザとは異なる枠組みで運用されるのが特徴です。
雇用主には外国人従業員の生活支援や就労管理の義務が発生しますが、一般的な学歴要件は求められません。
申請の際は活動内容や雇用条件、企業の受け入れ体制などが審査されます。
要件を満たしているか慎重な確認が必要です。
日本で就労ビザが下りない主な理由
日本で就労ビザが下りない主な理由は、4つあります。
|
申請する企業側もこれらを把握し、適切な対応を取らなければいけません。
それぞれの理由を理解して、具体的な対処法を見出しましょう。
理由① 業務内容が合っていない
在留資格の技術・人文知識・国際業務では、外国人が大学や専門学校で学んだ専門分野と、従事する業務内容に関連性があるかがポイントです。
例えば、経済学を学んだ留学生の金融機関への就職は許可されやすいといえます。
一方で、法学部の卒業者のアパレル企業への就職や、大学で建築を学んだ人材のホテルのフロントスタッフへの採用は、関連性が低いと判断されます。
専門性を活かせない単純作業や、専門外の業務への従事は認められません。
企業は採用する時に応募者の学歴や専門分野を確認し、担当予定の業務との関連性を具体的に示す必要があります。
外国人の専門分野と業務内容の一致は、就労ビザの許可に欠かせません。
理由② 書類に不備がある
就労ビザが下りない理由でもっとも多いのは、申請書類の不備です。
パスポート番号や氏名のスペルミスといった基本情報の誤りは、申請者の信頼性を損なう原因につながります。
また、在職証明書や学歴証明書などの必要書類が不足していたり、提出期限に間に合わなかったりするケースも多いです。
特に、海外の大学や専門学校の卒業証明書は、取り寄せに時間がかかるため、余裕をもった準備が欠かせません。
記載内容の整合性も、審査をする上で重要なポイントです。
業務内容や給与条件などに矛盾があると、疑念を抱かれる可能性があります。
申請書類は複雑かつ専門知識が必要です。
書類を不備なく提出するなら、行政書士など専門家のチェックを受けましょう。
理由③ 十分な経済的証明ができていない
就労ビザの審査では、外国人材の経済基盤が重視されます。
入国管理局は申請者が日本での滞在中に生活に困窮しないよう、十分な給与水準や預貯金などの資金的な裏付けを求めるのが一般的です。
賃金が最低賃金に近い水準では、生活の安定性に疑問が残るため不許可となるリスクが高まります。
また、採用企業の財務状況も注目すべき審査項目です。
赤字が続く企業や設立間もない会社は、外国人材を安定的に雇用できるか懸念されます。
加えて、資金証明には給与明細や銀行残高証明書などの具体的な書類が必要です。
企業側は適正な給与水準や住宅手当などの福利厚生を整備し、経済的な支援体制を明確に示さなければいけません。
申請を行う前に、十分な経済的証明ができているか確認しましょう。
理由④ 滞在目的が不明瞭である
就労ビザが下りない理由には、滞在目的の曖昧さも挙げられます。
入国管理局は、申請者が在留資格に定められた活動に専念するかを慎重に審査します。
短期滞在から就労への切り替えを申請する際、観光目的で入国したにも関わらず就労を希望するなど、当初の目的と異なる活動は許可されません。
技能実習から特定技能への移行でも、技能実習で習得した技術と異なる業務に就こうとすると疑問が生じます。
採用企業には、外国人材に期待する役割や業務内容を具体的に示し、必要性を合理的に説明する姿勢が求められます。
特定の専門知識や技能が必要な業務を、明確な根拠とともに示せれば、滞在目的の正当性が認められやすいです。
滞在目的を明確にしてから申請しましょう。
| 【完全ガイド】日本で働ける在留資格 就労ビザに関する内容をまとめた資料です。 日本で働くことができる在留資格の概要をまとめておりますので、外国人雇用を検討する際の確認資料としてお使いいただけます。 |
就労ビザが下りなかったときの対処法
就労ビザが下りなかったときの対処法は、3つあります。
|
それぞれをチェックすれば、具体的な改善策が見えてきます。
対処法を把握し、スムーズな審査を実現させましょう。
対処法① 不許可の理由を確認する
就労ビザの申請が下りなかったときは、入国管理局から届く不許可通知に記載された理由を確認しましょう。
通知には、具体的な内容が記載されているとは限りません。
詳細を知るには、入国管理局に出向いて確認するのが最善です。
不許可の理由は、申請者自身の資格要件や経済状況、提出書類の不備など多岐にわたります。
なかには、申請者が自身の申請内容を十分に理解していなかったり、入国管理局に対して適切な説明ができなかったりする可能性もあるため、具体的な確認が必要です。
要因を正確に理解できれば、次回の申請が成功しやすくなります。
入国管理局は不許可の根本的な理由を把握しているため、正確な情報の入手を徹底しましょう。
対処法② 再申請が可能か確認する
就労ビザが下りなかったときは不許可の理由に基づいて、再申請の可能性を判断しましょう。
書類の不備や説明不足など、改善が可能な理由であれば再申請の道は開かれています。
ただし、前回と同じ内容での再申請は認められません。
指摘された問題点は、確実に修正する必要があります。
例えば、経済的証明が不十分だったなら、具体的な資金計画や給与条件の改善を示さなければいけません。
業務内容と専門性の関連が薄いと判断された場合、職務内容の調整や配属先の変更を検討します。
また、再申請のタイミングにも注意が必要です。
まずは期間を置き、行政書士に相談しつつ、申請書類の作成や要件の確認を高い精度で行いましょう。
対処法③ 在留資格の要件を再確認する
就労ビザが下りなかったときは、在留資格の要件を再確認すべきです。
入国管理局は不許可の際、一部の要件のみを指摘し、他の不備には言及しない可能性があります。
そのため、再申請時には指摘された点の改善だけでなく、在留資格の要件全体を改めて確認しましょう。
例えば、技術・人文知識・国際業務の主な審査項目は3つです。
|
特定技能では、試験合格や日本語能力に加え、雇用契約の内容や受け入れ体制の整備状況も重視されます。
申請者の過去の在留状況や活動履歴にも着目され、アルバイトの時間制限違反などの法令違反歴があると、厳しい審査になるため注意が必要です。
就労ビザの許可には、適切な在留資格の選択も検討課題といえるでしょう。
不許可とならないために企業ができること
就労ビザが不許可とならないために企業ができることは、4つあります。
|
それぞれのポイントを把握し、審査の成功率を高めましょう。
業務内容の確認
外国人を採用する際は、人材が持つ専門性と予定業務との関連性を慎重に確認する必要があります。
大学や専門学校の卒業証明書、成績証明書から履修科目を確認し、職務内容との整合性を検証しましょう。
例えば、工学部で機械設計を学んだ人材を、ITシステムの開発担当として採用するのは無理があります。
技術分野が根本的に違うため、不許可となる可能性は高いです。
また、経営学を学んだ人材を、接客業務のみに従事させるやり方も認められません。
採用時には、外国人材の専門知識や技能を活かせる職務を具体的に設定し、入国管理局に説明できる体制を整えましょう。
さらに、配属後の業務内容の変更や出向などにも注意を払い、在留資格の範囲内での活動となるよう管理してください。
業務内容と合うほかの在留資格の確認
就労ビザの種類は多岐にわたるため、最適な在留資格は業務内容によって異なります。
従来の技術・人文知識・国際業務での採用が難しいなら、特定技能など別の在留資格での受け入れを検討すべきです。
特定技能は12の対象分野が定められており、介護や外食業、建設業などの人手不足分野で活用できます。
ただし、専門的な学歴や経験が不要な代わりに、試験合格や日本語能力の証明が必要です。
また、企業内転勤や特定活動など、状況に応じて柔軟な選択ができます。
企業規模や事業内容、採用予定の外国人材の資格要件を総合的に判断し、最適な在留資格を選択すれば採用を成功させられるでしょう。
労働時間制限を厳守する
留学生のアルバイトなどの資格外活動には、週28時間以内という労働時間の制限があります。
違反すると不法就労になってしまい、在留資格の変更や更新ができなくなる可能性が高いです。
繁忙期だからといって制限を超える労働を指示すると、外国人本人だけでなく、雇用企業も処罰の対象になるため注意しましょう。
処罰を受けると、不適切な雇用管理を行う会社とみなされ、将来の外国人採用に影響を及ぼします。
そのため、労務管理システムでの勤務時間の把握やシフト管理の徹底など、労働時間管理体制を確実に整備しなければなりません。
また、複数のアルバイト先での合算時間にも注意を払う必要があります。
信頼できる派遣会社・紹介会社を選ぶ
外国人材の採用で派遣会社や紹介会社を利用する場合は、慎重な選定を心がけましょう。
最近では、実際の業務内容と異なる職種で在留資格を取得し、不適切な就労をさせる問題が増えています。
たとえば、通訳業務として技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請しながら、実際は製造ラインでの作業に従事させるやり方です。
このような不正は、受け入れ企業も不法就労を助長したとして責任を問われる可能性があります。
そのため、労働者派遣事業や有料職業紹介事業の許可を持つ適正な業者を選定し、業務内容や雇用条件を明確に確認してください。
| 【完全ガイド】日本で働ける在留資格 就労ビザに関する内容をまとめた資料です。 日本で働くことができる在留資格の概要をまとめておりますので、外国人雇用を検討する際の確認資料としてお使いいただけます。 |
まとめ
就労ビザの申請では、外国人材の専門性と業務内容の関連性の高さが重要です。
不許可を避けるには、適切な在留資格の選択、書類の完備、経済的証明の充実が欠かせません。
企業は採用計画の段階から入念な準備を行い、必要に応じて専門家のサポートを受けましょう。
派遣・紹介会社を利用する際は、コンプライアンス体制の整った信頼できる業者を選定してください。
また、採用後の労務管理体制も重要です。
特に、労働時間の制限遵守には細心の注意を払いましょう