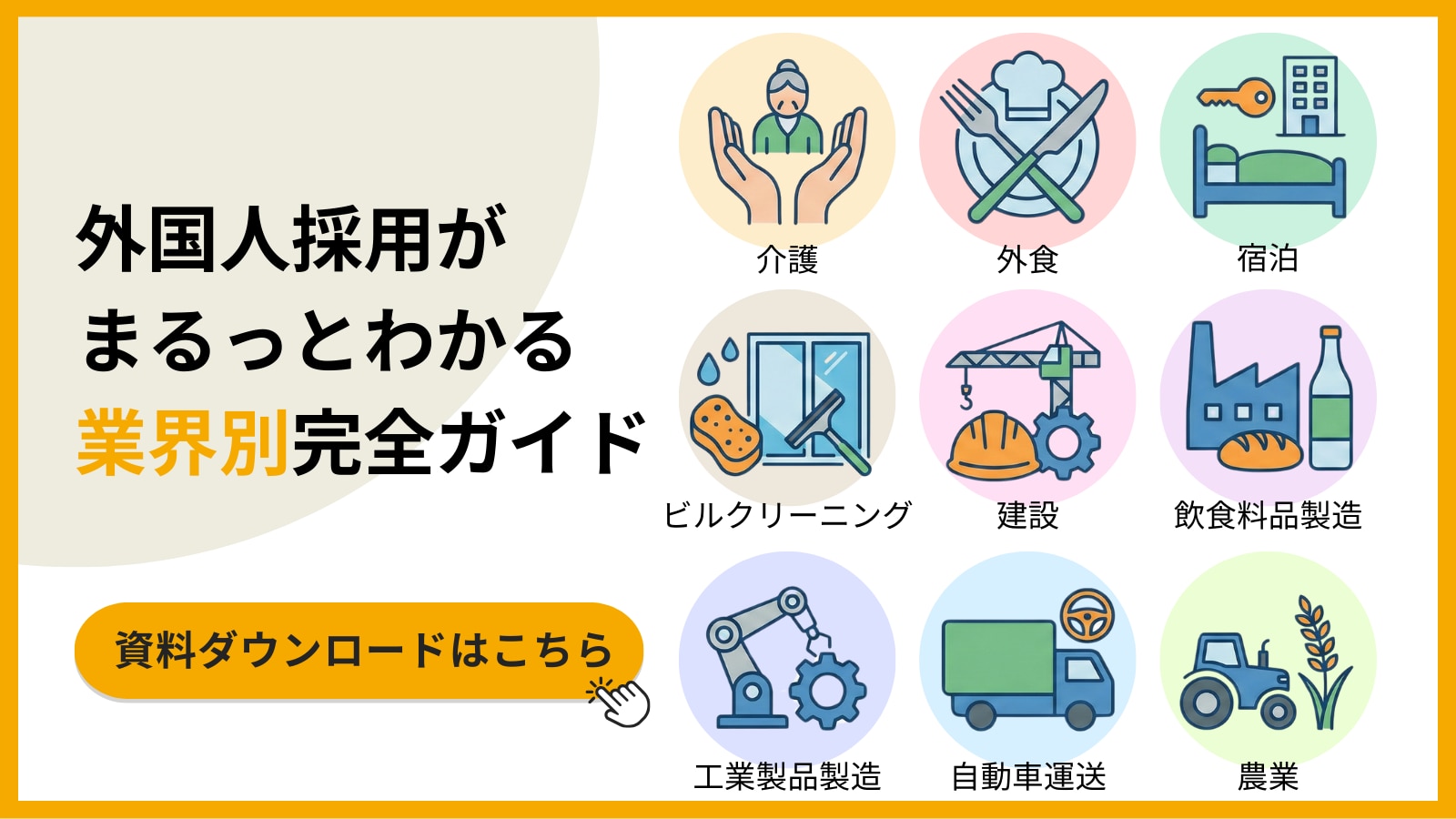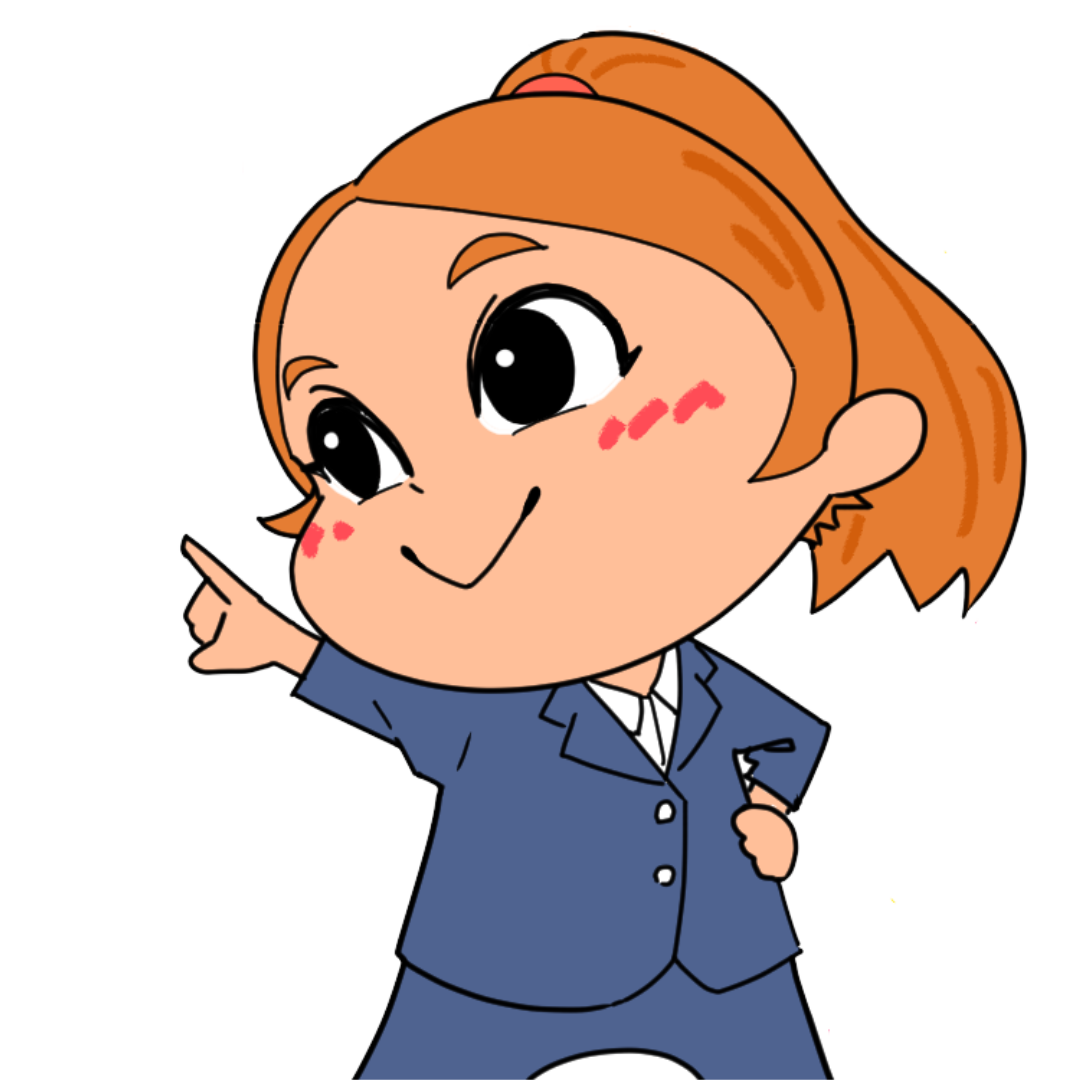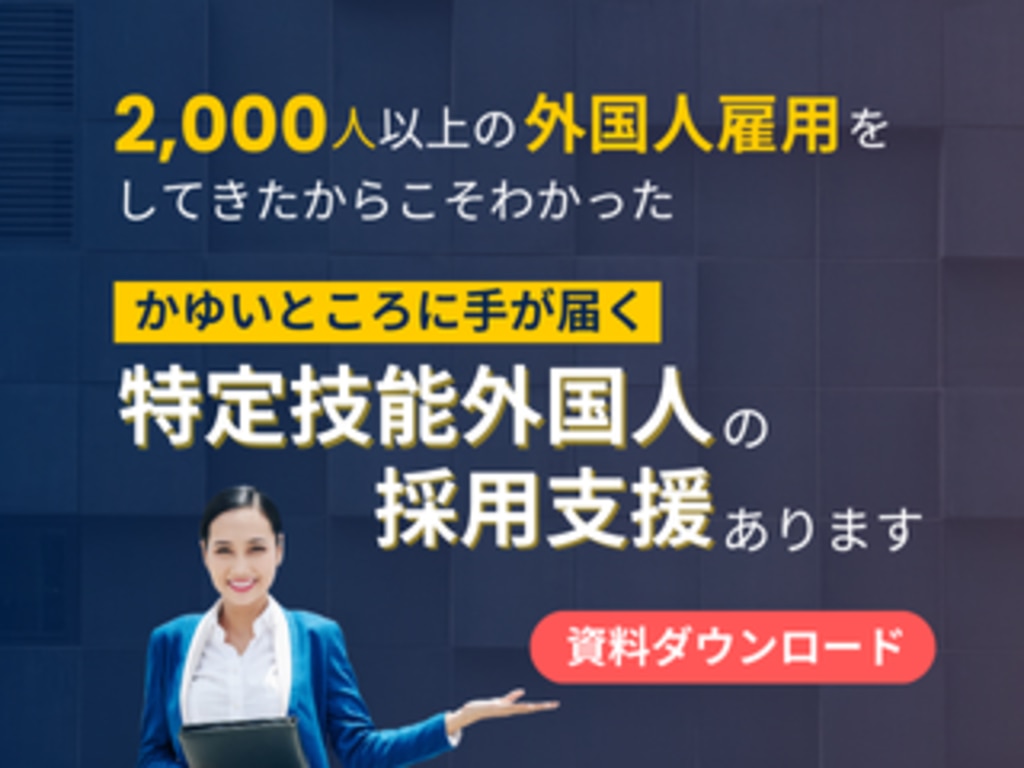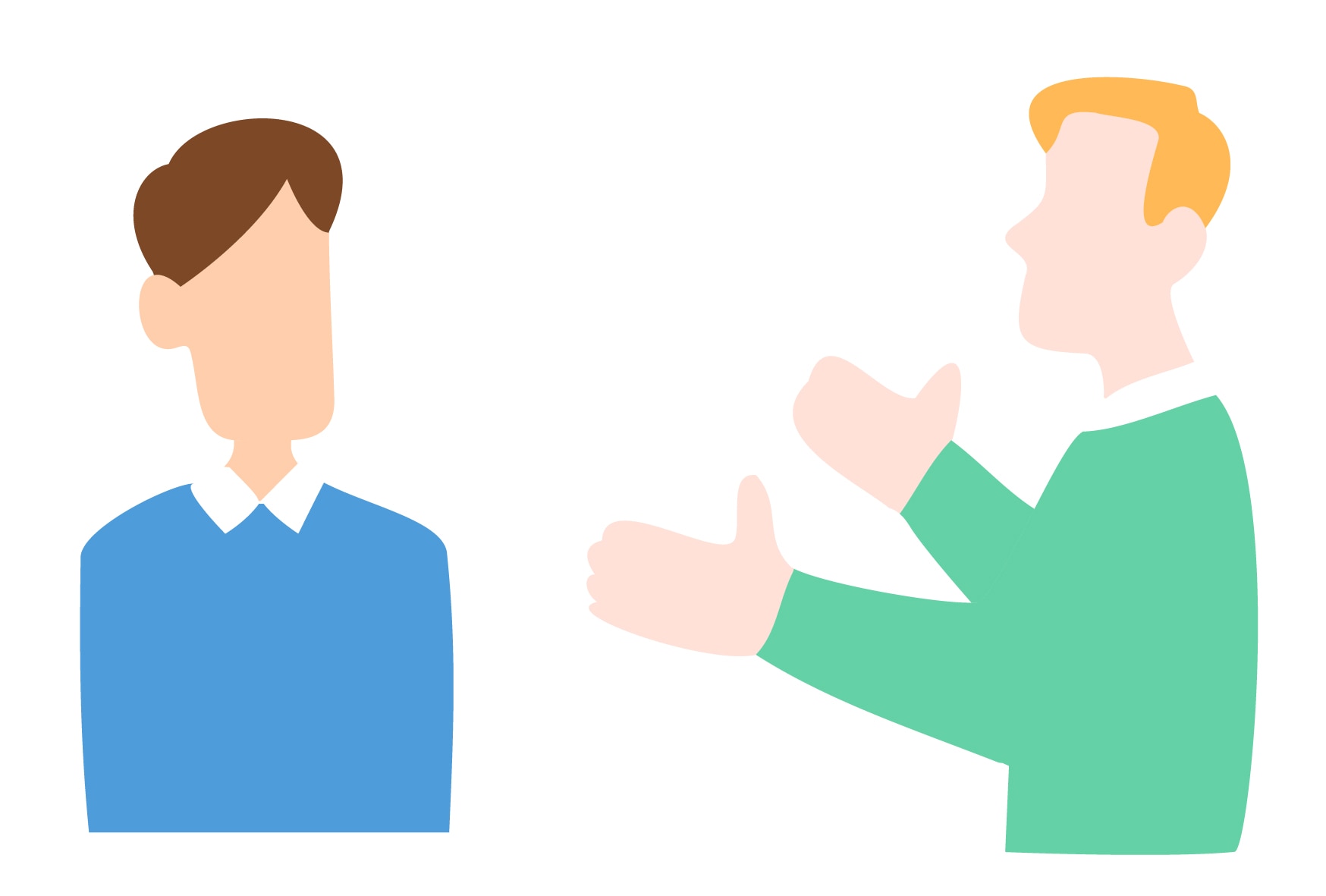
留学生のアルバイト雇用のポイントとは?就労時間制限も解説
外国人留学生は、深刻な人手不足に悩む企業からすると、アルバイトスタッフの有力候補です。
しかし、外国人留学生の雇用には、特有のルールや制限があります。
これらを知らないまま採用を進めると、思わぬトラブルを招くおそれも。。
本記事では、外国人留学生をアルバイトとして雇用する際のポイントや就労時間の制限、違反した場合のリスクを詳しく解説します。
外国人留学生の採用を検討している企業の方をはじめ、すでに雇用している企業の方も、適切な雇用管理の参考にお役立てください。
目次[非表示]
外国人留学生のうちアルバイトしている割合は?
独立行政法人日本学生支援機構の調査によると、日本で学ぶ留学生の約7割がアルバイトに従事しています。
2018年5月時点での留学生総数は約29.8万人に達し、多くの留学生が学業と両立しながら働いています。
業種別の割合は、以下の通りです。
業種 | 割合 |
|---|---|
飲食業 | 35.0% |
営業・販売(コンビニなど) | 30.2% |
工場での組立作業 | 6.1% |
ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント | 5.6% |
近年は新型コロナウイルスの影響で、飲食業でのアルバイトは減少傾向です。
一方、コンビニや工場での就労は増加しています。
このように、留学生のアルバイト就労は業種によって変動があるものの、日本の労働市場において重要な位置を占めています。
留学生を採用するメリット
企業が留学生をアルバイトとして採用するメリットは、4つあります。
|
特に小売店や飲食店では、留学生の母国語を活かした接客により、訪日外国人観光客への対応が充実します。
その結果、新たな顧客層の開拓につながる可能性があります。
また、異なる文化や価値観を持つ留学生が職場に加わると、日本人スタッフの視野が広がり、職場の活性化も期待できます。
さらに、語学力を活かしたメニューの多言語化やSNSでの情報発信など、インバウンド対応の幅も広がるでしょう。
留学生のビザ発給件数の動向
2024年度の留学生のビザ発給件数は大幅な増加を示し、過去最高を記録しました。
出入国在留管理庁の中間報告によると、中国、ベトナム、ネパールからの留学生が顕著な伸びを見せています。
2024年6月末時点では、中国からの学生が全体の約22%を占めて最多となり、ベトナムが約16%、ネパールが約5%と続いています。
留学生の件数は、2020年から発生したパンデミックの影響で一時的に減少していました。
しかし、2024年には回復基調に転じ、留学ビザの発行数は前年比61.6%増です。
文部科学省は今後も留学生受け入れ体制の拡充を目指し、日本の教育の国際競争力を高めていく方針です。
日本政府はこれらの国々と教育分野での連携を強化しており、留学生の受け入れ数は今後さらに増加するでしょう。
留学生のビザ発給件数の動向は、日本の高等教育機関の国際化とグローバル人材の育成に寄与すると期待されています。
留学生をアルバイトとして雇う際のポイント
留学生をアルバイトとして雇う際は、アルバイトが可能な在留資格があるか確認する必要があります。
さらに、就労条件を満たしているかもチェックしなければいけません。
それぞれのポイントを把握し、スムーズな雇用を目指しましょう。
ポイント①アルバイトが可能な在留資格があるのか確認する
外国人留学生を雇用する際は、在留資格の確認が欠かせません。
在留カードには、就労に関する重要な情報が記載されています。
確認すべき項目は、大きく分けると4つです。
|
カードの表面には就労制限について就労不可と記載されていますが、裏面に資格外活動許可の記載があれば、アルバイトをしても問題ありません。
これらの確認を怠ると、大きなトラブルに発展する可能性があります。
したがって、採用時には確認作業を慎重に進めなければいけません。
また、カードのコピーを取得し保管してれば、不測の事態に備えられます。
就労条件に注意する
留学生の就労には、一般のアルバイトとは異なる特別条件が設けられています。
特に重要になるのが、週28時間という就労時間の制限です。
この制限は学業に支障をきたさないための措置で、留学生が本来の目的である学業を優先できる環境を整えるためのものです。
また、風俗関係営業での就労は一切認められていません。
条件に違反した場合は留学生本人だけでなく、雇用主側にも罰則が与えられる可能性があります。
就労時間の管理は雇用主の責任になるため、シフト作成時には配慮が必要です。
次の見出しでは、これらの就労条件についてより詳しく説明していきます。
留学生の就労条件とは?
留学生の就労条件は、どの曜日から数えても週28時間以内、長期休暇中は1日8時間、週40時間までと定められています。
企業側はこれらを正しく理解し、適切な管理下のもとで就労させる必要があります。
留学生の就労時間制限は週28時間以内
留学生のアルバイトで注意すべきなのは、週28時間という就労時間の上限です。
どの曜日から数えても、週28時間以内に収める必要があります。
また、通常の労働者に適用される変形労働時間制なども、適用できません。
就労時間制限は、留学生の本分である学業を確実に優先させるための措置です。
出稼ぎ目的での留学を防ぐ役割も果たしています。
そのため、シフト管理では特に注意が必要です。
他のアルバイト先での勤務時間も含めた、総労働時間を把握しなければいけません。
長期休暇中は1日8時間、週40時間まで
留学生の就労時間制限には、例外期間が設けられています。
夏季休暇や冬季休暇など、学則で定められた長期休業期間中は就労時間が緩和される形です。
長期休業期間に限っては、1日8時間以内、週40時間以内での就労が認められています。
ただし、学則による長期休業期間に限定されているため、休講や授業のない期間は対象外です。
また、1日8時間という上限は厳格に定められており、変形労働時間制を適用して1日10時間×週4日といった勤務形態は認められません。
雇用主は長期休暇期間の開始と終了を正確に把握し、期間に応じた適切なシフト管理が必要です。
さらに、労働基準法で定められた休憩時間の確保など、基本的な労働条件を遵守しなければいけません。
就労時間制限を守らなかった場合どうなる?
就労時間制限を守らなった場合は、雇用者に対して不法就労助長罪が適用されます。
留学生に関しては、強制送還の対象になる可能性があります。
さらに、入国管理局がなぜルール違反を見抜けるのかを理解すれば、留学生の適切なアルバイト雇用を実現できるでしょう。
それぞれのポイントを把握し、スムーズな雇用とクリアな就労を実現すべきです。
雇用者には不法就労助長罪が適用される
雇用主側が留学生の就労時間制限に違反した場合、不法就労助長罪が適用されます。
3年以下の懲役、300万円以下の罰金、または両方が科せられる可能性があります。
不法就労助長罪は、留学生が資格外活動許可を得ていない状態で働かせた場合や、許可された時間を超えて勤務させた場合に適用される制度です。
雇用主が制限時間の超過を知らなかった場合でも、確認義務を怠った過失として処罰の対象となる可能性があります。
また、在留資格の確認を行わない、就労時間の管理を怠った場合も罰則の対象です。
このような事態を防ぐためにも、日々の適切な労務管理と記録の保持を徹底しましょう。
留学生は強制送還の対象になる可能性がある
留学生が就労時間制限に違反すると、強制送還の対象になる可能性があります。
制限時間を超えて就労した場合、資格外活動許可違反として扱われ、在留資格の更新や変更申請が不許可となる可能性が高くなります。
深刻な場合は強制退去処分の対象となり、日本への入国が5年間認められません。
最近では、実質的な就労目的で留学の在留資格を取得するケースが増加しています。
その結果、入国管理局は審査を厳格化しています。
このように就労時間の制限違反は、以前よりも厳しく取り締まられるようになりました。
留学生は本来の目的である学業に専念できないだけでなく、日本での就職機会を失う可能性があるのです。
なぜ入国管理局はルール違反がわかるのか
外国人に関する情報は、以下の行政機関で共有されています。
|
就労状況が把握できる仕組みは、各機関の連携によって整えられています。
特に重要なのが、雇用主が行う納税手続きの工程です。
市区町村役場から発行される納税証明書には、外国人留学生の収入額が1円単位で記載されます。
収入額と時給を照合すれば、就労時間の実態は一目瞭然です。
また、留学ビザの更新や就労ビザへの変更申請時には、源泉徴収票の提出が求められます。
この時点で就労時間の超過が発覚すれば、更新や変更が不許可となる可能性が高いです。
さらに、在留カードに記載された情報を通じて、外国人留学生の就労状況を容易に追跡できる体制が整備されています。
行政機関は緊密な情報共有によって、制限時間の超過を早い段階で見抜ける仕組みを構築しています。
週28時間を超えないための対策
28時間を超えないための対策は、3つあります。
|
対策を取り入れ、罪に問われない安全で明確なアルバイト雇用を目指しましょう。
定期的にダブルワークの報告をしてもらう
外国人留学生のダブルワークは、認められています。
しかし、すべてのアルバイト時間を合計して、週28時間以内に収めなければいけません。
この制限を遵守するには、他のアルバイト先での勤務状況を定期的に把握すべきです。
報告頻度は月1回程度を目安とし、具体的な勤務時間やシフトパターンについて確認しましょう。
また、勤務時間に変更があった場合は、随時報告してもらう仕組みも整えるべきです。他社での勤務表のコピーの提出や、所定の報告フォームへの記入を取り入れると有効です。
ダブルワークの確認を怠ると、週28時間を超過するリスクが高まります。
企業側の確認不足は、法令違反の言い訳にはなりません。
罰則の対象になる可能性もあるため、慎重な管理が必要です。
留学生が希望する時間をシフトに入れる
留学生がダブルワークを始める背景には、ひとつの職場で希望する勤務時間を確保できない実情があります。
週28時間の制限がある中で、効率的に働きたいと考えるのは自然な発想です。
そのため、採用時には希望する勤務時間を詳しく聞き取り、可能な範囲で希望に沿ったシフトを組むようにしましょう。
具体的には、授業のない日にまとまった時間を入れる、通学時間を考慮した効率的なシフトを組むなどの工夫が必要です。
また、シフトの希望は学期や授業スケジュールによって変動する可能性があるため、定期的な面談を通じて希望を確認し、必要に応じて調整を行うべきです。
労働基準法を遵守する
外国人留学生も日本人のアルバイトスタッフと同様に、労働基準法に基づく労働条件を遵守しなければいけません。
1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を確保する必要があります。
また、法定休日の確保も重要です。
毎週1日以上の休日を設定し、4週間で4日以上の休日を確実に付与します。
長期休暇中は1日8時間まで就労が可能ですが、必要な休憩時間の確保は欠かせません。
さらに、深夜勤務や休日勤務の際は割増賃金の支払いも必要です。
長時間の勤務が必要な場合は、在留資格の特定技能での採用を検討しましょう。
特定技能は、外食業を含む特定の産業分野で認められている在留資格で、週40時間までの就労が可能です。
留学生が卒業後に特定技能に切り替えれば、柔軟な勤務形態での雇用を実現できます。
また、特定技能は最長5年の在留期間が認められており、育成投資を長期的に回収できます。
ただし、特定技能の取得には一定の技能試験や日本語能力試験の合格が必要です。
まとめ
外国人留学生のアルバイト雇用では、在留カードで資格外活動許可を確認し、週28時間の就労時間制限を厳守する必要があります。
違反すると、企業側には不法就労助長罪が適用され、留学生本人も在留資格を失うリスクがあるため注意が必要です。
適切な雇用管理を実現するためには、3つのポイントを抑えましょう。
|
これらに十分な注意を払い、適切な雇用管理を心がけましょう。
不明点がある場合は、入国管理局や労働基準監督署に相談してみてください。